こんにちは!
学問ボウズです。
本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!
皆様は、「神国」や「神国思想」という語を聞いたことがあるでしょうか?
「日本は神国だ」という表現で、歴史の授業や、本や映画などで触れたことがある方が多いと思います。
「神国」とは、文字通り「神の国」ということです。
なので、「神国思想」をざっくりいえば、「日本を神の国と見なし、讃える思想」です。
もう少し詳しく、「日本の国土とそこにあるものは、すべて神々の力によって生成し、神々に護られているという思想」と表すこともできます。
では、日本は「神の国」なのでしょうか?
現代の日本人には、その感覚はあまりありません。
そのため、私たちは、「神国思想」が重要だとはあまり思っていません。
「神国思想」について、より具体的には、
「日本では、いつから、我が国が神国だと言われるようになったのか?」、
「そもそも、なぜ日本は神国なのか?そう言える理由は何か?」
などの問題について、現代人の中で深く知っている方はあまりいないのです。
しかし、日本の歴史の中では、近代にいたるまで、「日本は神国だ」と、多くの方に深く信じられ、日本人のメンタリティーを形作ってきたのです。
「神国思想」は、日本史上において、大きな役割を果たしてきた思想だといえます。
ただ、その一方で、「神国思想」が基盤になり、日本という国は、歴史上、国内でも海外でも、多くの人を傷つけてきたという面もあります。
(現代の観点から、過去の歴史に対して、軽々しく良い悪いの評価をするのは慎まなければなりませんが、)現に、識者たちの中に、「神国思想は日本の負の遺産だ」と厳しく批判する方がいるのは、まぎれもない事実です。
言うまでもないと思いますが、その際に識者たちが念頭に置いているのは、主に世界大戦です。
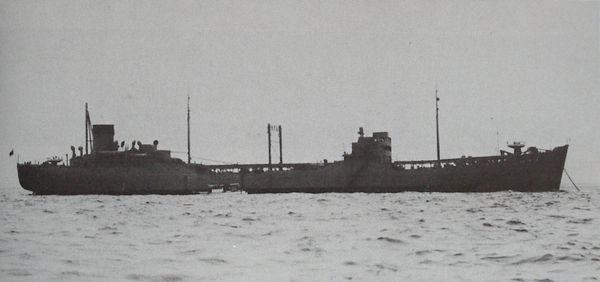
【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shinkoku_Maru-1941.jpg?uselang=ja)】
また、今でも、日本人の一部の方は、過去の「神国思想」と同じものではないですが、「日本は神に護られている、神の国だ」ということを信じています。
何が言いたいかというと、「神国思想」は、日本の歴史を学ぶ上で、ひいては今の日本人の信仰をより深く理解する上で、欠かせないものだということです。
神国思想を深く学ぶことで、日本の宗教や歴史について、より解像度を上げて理解できます。
(もっと言えば、神国思想について深く知らずに、日本の宗教史・思想史・歴史を理解することは不可能です。)
本記事では、神国思想について、その内容や、歴史・歴史的意義について、詳しく解説していきます。
ぜひ最後までお読みいただき、日本の宗教や歴史について、より深く理解する一助としていただけたらと思います。
また、ぜひ本記事での学びを踏まえ、
「今の私たちは、神国思想をどう位置付けるべきなのか?
大切な遺産なのか、批判すべき負の遺産なのか?」
などについて、ご自身で考えていただけたらと思います。
では、やっていきましょう!!
前提知識
さきほどもざっくり意味を述べましたが、前提知識として、「神国思想」の意味について、もう少し説明をしておきたいと思います。
この概説を終えた後、具体的に歴史をひも解いていくことにしましょう。
「神国」の意味について、もう少し具体的にいえば、以下の2つがあります。
⑴神々の加護の下にある国。
⑵天照大神の子孫たる、天皇の統治する国。
このうち、⑵の意味合いの「神国」は、往々にして、自国優位の、他国に対して排他的な立場を伴うものです(後に詳しくお話します)。
概して、先に⑴のような意味合いでの「神国思想」があり、後に⑵がそれに加わるというのが、歴史上の流れです。
ただし、⑴⑵の内容は時代ごとに展開があり、順番は一概には言えません。
また、このように大きく二つに分けましたが、この2つには重なりあう部分もあります。
そのため、2つに分けておいてなんですが、このような二分をすることには問題もあります。
しかし、ざっとこういうイメージを持っておいていただけると、これからの説明が分かりやすくなると思いますので、あえて二分しました。
ひとまず、「神々の護る国という⑴の意味合いと、天皇が絡んでくる⑵の意味合いの両方があるんだな」というくらいのイメージをしていただき、次に進んでいただければと思います。
次節以降で詳しく見ていきますが、最初に見取り図を描いていただいていたほうが分かりやすいと思いますので、「神国思想」の歴史を大まかに説明しておきましょう。
日本を神国と見る意識は、もともとは素朴な信仰に根ざすものでした。
ざっくりいえば、「神々がこの国を護っていてくださる。ありがたい」というくらいの考え方だったのです。
すなわち、平安時代の半ば頃までは、「神国」という語を用いるにしても、あくまで⑴「神々に護られている国」というくらいに素朴に考えていたにすぎません。
さきほど、⑵の意味合いのところで少し触れたような、「他国を排し、日本国の優位性を主張するための確固たる思想」というべきものが、当初からあったわけではないのですね。
その後、国内の政治的な統一が進み、天皇を頂点とする国家が確立してくるようになると、変化が生じてきます。
⑴「神々に護られている国」という意味に重ね合わせて、⑵「神々の中心である天照大神の子孫が、天皇として君臨する国」という意味も込めて、「神国」という語が用いられるようになったのです。
さらに、それとほぼ時を同じくして、他国や他民族に対する意識が明確になってきました。
それにより、この「神国思想」を拠り所として、他国に比して日本をすぐれた国とする主張も生まれていったのです。
「神国思想」の歴史については、大まかには、今述べたように、
「神国という語は、本来は直接排外的な思想に結びつくものではなかった。
しかし、その後、対外的な緊張が高まった時代に、日本中心の排外的な主張をあらわす語として用いられるようになった。
そして、そのような意味合いでの神国思想が、日本中に浸透していった」
という構図で理解することができます。
今ざっくり述べてきたことからも分かるように、「神国」とは、語のニュアンスや、その語が使われる背景や意図が時代ごとに変遷してきた、複雑なものなのです。
逆に言えば、複雑だから面白いのです。
では以下、その歴史的展開について詳しく見ていきましょう。
「神国思想」の歴史
当初の「神国思想」 ―平安時代半ば頃まで―
さきほど述べたように、古代には「神国」という語はあまり用いられず、用いられる場合でも、⑴「神々の護る国」の意味に限られています。

「神国」という語が最初に用いられた例を紹介しておきましょう。
それは、『日本書紀』(奈良時代に成立した日本の歴史書)におさめられている、「神功皇后摂政前紀」です。
この「神功皇后摂政前紀」では、
「日本の軍船が来攻するのを見た新羅(前57年~935年まで、朝鮮半島の南東部にあった国家)の王が、『吾聞く、東に神国有り、日本と謂ふ。亦聖王有り、天皇と謂ふ。必ず其の国の神兵ならむ』と述べた」
と記録しています。
ここで興味深いのは、新羅という他国の王が日本を神国と表現していることです。
この記述の真実性は何とも言えませんが、もし事実だとするなら、この時代には、他国の人物も、日本を神の国と見なしていたことになりますね。

また、『日本書紀』以外にも、古代において神々に奉った「告文」(神に申し上げることばを書き記した文書)にも、日本が「神国」であることを述べて、神々を祭る文章がみえます。
特に伊勢神宮(お伊勢さん)に関する記述には、神国の語が多く見えます。
では、なぜこの時代に、「神国」について言及されるようになったのでしょうか?
これについては、色々と背景を考えることができますが、中でも、「仏教が伝来したからだ」という学説が有力です。
仏教はインド発祥で、中国・朝鮮を通してもたらされました。
なので、今でこそ仏教は日本に深く根付いていますが、本来、日本にとってはあくまで外来の宗教なのです。
そのため、現に、伝来して間もない頃は、「仏教は蕃神(異国の神)を礼拝する教えだ」と見なされていました。
しかし、仏教はその後、徐々に朝廷の信仰を受けて、しだいに(具体的には飛鳥時代頃から、)多くの人の間に広まっていきました。
その一方で、日本には土着の神々の祭祀を重視していた人々もいました。
このような信仰を、神祇信仰といいます。
そういう人たちは、広まり始めた外来の仏教に対比する形で、「日本が神国である」ことを説いたのです。
このような土着の神々を重視する人たちも、仏教は仏教で素晴らしいことを認めていました。
しかし、それと同時に、
「日本には、聖なる存在として、古来の神もいます。
そのような神々はこの日本国を護ってくださっている、ありがたい存在なのですよ」
と主張したのです。
これが起点となり、「日本は神国だ」という説が広まるようになっていったというわけです。
そのため、この時代の「神国思想」は、別に仏教とケンカしようとして唱えられたわけではありません。
また、自国優位を説く思想として示されているわけでもありません。
あくまで、仏教の素晴らしさも認めながら、「仏教も良いけど、土着の神々も素晴らしいよ」と、仏教と対比して、神々の護りの素晴らしさも説くというスタンスだったに過ぎません。
ちなみに、土着の神々への信仰(神祇信仰)と仏教が対立することは、概して、鎌倉時代以降にならないと起こりません。
鎌倉時代には、「神道」が一宗教として確立するに至ったため、そこでようやく、神道と仏教は張り合うようになったのです。
それまでの時代では、神社の中に寺を作るなど、神祇信仰と仏教は基本的に調和していました。
これを神宮寺といいます。
(その調和関係の最たるものである「神仏習合」思想については、次節で触れます。)

本節のポイントをまとめると、以下の通りです。
◎日本では、つとに古代から、「日本は神国だ」ということが言われるようになった。
◎その意味合いは、あくまで⑴「神々の護る国」という程度に過ぎない。
そのため、「神国思想」は、自国優位を示す思想として確立してもいないし、日本中で盛んになっているというわけでもない。
以上のように、ここまでの時代の「神国思想」は、「日本は神々によって護られているのだ」という、素朴な考え方、ないし信仰だといえます。
では、排他的な自国優位思想としての「神国」説が歴史の表舞台に登場してくるのはいつなのでしょうか?
それが、次節に見る中世前期、すなわち平安時代末~鎌倉期にかけての時代です。
平安時代末~鎌倉時代
平安末~鎌倉という時代には、「日本は神国であること」が盛んに説かれるようになります。
またそれに伴い、⑵の意味での神国理解(「神の子孫たる、天皇の統治する国」)も強調されるようになるのです。
すなわち、この時代は、「神国思想」が高揚し、より過激になった時代だといえます。
では、なぜこの時代に「神国思想」が高揚したのでしょうか?
その理由は大きく分けて、以下の3つです。
①この時代は武家が台頭し、武家と公家との政治権力の交代期にあたる。
そのため、武家の権力に対峙する必要にかられた公家側は、天皇を頂点とする古代からの貴族体制を保持することを狙って、そのイデオロギーとして「神国思想」を強調した。
②この時代には「末法思想」が浸透し、「自分たちは救われ難い存在だ」という意識が人々に広まった。
それに伴い、僧侶や神官(神社に仕えて神事にたずさわる人)たちによって、神国思想が盛んに鼓吹された。
③この頃、蒙古襲来という国家的危機が起こった。
それが日本国民としての意識を覚醒させ、神国思想がいっそう主張されるようになった。
以上の3つの理由です。
しかし、これだけ聞いても、何のことやらよく分からないと思います。
以下、この3点について、順に詳しく説明していきます。
公家側による、イデオロギーとしての「神国思想」の鼓吹
まず第一の点、①「公家側による、イデオロギーとしての神国思想の鼓吹」から、説明していきます。
平安時代半ばまでは、日本には他国からの圧力もなく、国内も総じて平和でした。
そのため、日本の優位性や天皇の権力などについて取り立てて論じる必要性がなく、結果として「神国」についてもあまり言及されることがなかったのです。
しかし平安末になると、変化が生じます。
公家社会の権威が崩れ始めたのです。
具体的にいえば、「新たに武士が台頭し、今までの「天皇を頂点とし、それを公家が支える、朝廷中心の政治体制のみで日本が治まっている」という状況が変わり始めたということです。
現に、この時代には、鎌倉幕府や室町幕府という、武士による新たな政治体制が作り出されていきますよね。
こうした状況の中で、公家たちは、こう考えるようになりました。
すなわち、
「天皇は神の子孫であり、神々によって加護されていることを強調することで、天皇・貴族を中心とする国家の秩序を守ろう」
と。
そして、実際に活動もし始めました。
「天皇は神の子孫であり、神々によって加護されている。
そうした意味で、日本は神の国なのだ」
と、盛んに「神国思想」を喧伝し始めたのです。

「末法思想」に伴う、「神国思想」の鼓吹
では次に、第二の②「末法思想に伴う、神国思想の鼓吹」に移りましょう。
「末法思想」について踏み込んでいると、大変長くなりますので、「神国思想」の歴史にフォーカスする本記事では、必要最低限の解説をするにとどめます。
概して言えば、「末法思想」とは、お釈迦様(釈尊)の滅した後の時代を、順に「正法」「像法」「末法」の3つに区分する仏教史観です。
末法とはどういう時代かというと、釈尊の教えだけが残り、修行も悟りも得られなくなるような、仏教でいえば最悪の、荒廃した時代です。
釈尊の入滅は何年のことだったのか、また正法や像法はそれぞれ何年間なのかについては諸説ありますが、日本では末法初年を平安中期の1052年とする説が主流になりました。
そのため、1052年以降は、
「もう末法になってしまった。
それゆえ、仏法はいっそう廃れていくし、私たちはとうてい悟りを得がたい」
とする認識が、当時の人々の間に広まることになったのです。
ここまで読んで、皆さまはこう思われないでしょうか。
「末法思想については分かった。
では、なぜこの末法思想が神国思想を呼び起こすことになるのか?
あまり繋がっていないじゃないか」
と。
この疑問はもっともです。
しかし、「神国思想」と「末法思想」は密接に繋がっています。
順を追って説明しましょう。
そもそも日本には、「末法思想」が強く意識されるようになる前に、「粟散辺地」という自国意識がもともとありました。
これを「粟散辺地説」といいます。
「粟散辺地」とは何かというと、「辺境にある粟を散らしたような小国」ということで、仏教の淵源であるインドや、仏教の本流となった中国などの大国に対する、辺境の日本を指します。
このように、日本には古くから、自分たちの国を、「大国のはずれにある劣った場所」と見なす、いわばマイナスの自国意識があったのです。
そのため、さきほど「末法思想が平安中期以降に広まった」と述べましたが、このことは、そもそもあった「日本=粟散辺地」というマイナスの自国意識の上に、さらに「今現在=末法」というマイナスの時間意識が加わったことを意味します。
言ってみれば、この時代の日本人は、「私たちは救われ難い」とする二つの説を受容するという、ダブルパンチを食らったのです。
悪条件+悪条件という、最悪の状況ですね。
こう聞くと、「当時の日本人は、こうしたダブルパンチにより大ダメージを受けたんだろう…」と思いたくなりますが、実はそうではありません。
ここが興味深いところです。
当時の人々は、ダメージを受けつつも、結果的に逆の方向に進み、「自分たちは救われる」ということを盛んに主張していったのです。
もう薄々感づいている方もいらっしゃるでしょうが、その際のカギとなったのが「神国思想」です。
「末法思想」や「粟散辺地説」と連動する形で、「神国思想」が盛んになり、日本国の意義が主張されるようになったのです。
このような「末法思想と、粟散辺地説&神国思想」の関わりの媒介になった、一つの考え方があります。
これも神国思想を学ぶ上で重要な要素なので、紹介しておきます。
それは、仏教が日本で神祇信仰と関わる中であらわれた、「本地垂迹説」です。
「本地垂迹説」とは、概して日本の神々と仏菩薩との習合(いわば融合)を説き、「日本の神々は仏が日本へ降りてきたもの」と見なす考え方のことです。
これについては、別記事で詳しく解説していますので、もっと詳しく知りたい方は、ぜひ合わせてご覧ください↓
本記事では、簡単に意味を確認した上で、次に進みます。
「本地垂迹説」は、だいたい平安後期頃に生まれました。
今述べたように、「本地垂迹説」は、「日本の神々は仏が日本へ降りてきたもの」という意味がおおもとです。
しかし、その後、時代がくだるにつれて、このようなおおもとの意味の上で、本地垂迹をめぐって、さらに踏み込んだ考え方が行われるようになります。
それが、
「救われ難い土地・時に生きる私たち(日本人)は、仏の教えが何たるかをよく理解できない。
だからこそ、仏さまはわざわざ、そんな私たちが帰依しやすい、(私たちのレベルに見合った)神の姿を取って日本に降りて来てくださったのだ。
仏さまがここまでしてくださっているのだから、私たちは必ず救われる」
という考え方です。
さらに、こうした考え方がもう一歩進んで、
「救われ難い土地だからこそ、この日本国では仏がわざわざ神として顕現する(「本地垂迹」)という、究極の神仏の慈しみが実現されたのだ。
となれば、こうした観点からいえば日本は意義深い、素晴らしい国ともいえるのだ」
という思想に至ります。
すなわち、ここでは、
「日本は、神仏の救いが、本地垂迹を通して、究極的に行われる地である。
その意味で、神国だ」
という考え方が明確に生まれているのです。
このとき、「神国思想」の鼓吹が起こっているといえましょう。
現に、一例を挙げれば、鴨長明(1155年~1216年)『発心集』、無住(1227年~1312年)『沙石集』などの、鎌倉期や以後の時代に大きな影響を与えた文献では、
「今の日本は、末法かつ辺地として救われ難い場所かつ時代である。
だからこそ神仏の利益がねんごろなのだ」
と主張し、神仏の慈悲が深く注がれる日本国の意義を示しています。
これらの文献では、こうした主張を踏まえ、最終的に
「末法であれ辺土であれ必ず救われる。
だから、神仏の双方に帰依せよ」
と勧めていくのです。
このように、平安末頃から、神国思想が、粟散辺地説・末法思想とセットになって鼓吹されたのです。
もっとも、「粟散辺地説・末法思想とセットで神国思想が説かれた」といっても、最初のうちは、「仏・菩薩の力だけでは教化しきれない、辺境かつ末法の日本国を、神が降りてきて救ってくださる。
なんとありがたいことか。
その意味で日本は神国なのだ」
という程度のことを主張するだけでした。
しかし、時代がくだるにつれて、「神がわざわざ救いに来てくださる日本国(神国)こそ、一番すごい」と、自国優位意識がいっそう付加されていくようになります。
こうして、⑵の意味での「神国思想」が、しだいに人々の間に浸透していったのです。
ちなみに、少し細かい話になりますが、補足しておきたいことがあります。
実は、数十年ほど前の研究においては、「神国思想によって粟散辺地説・末法思想を乗り越えた」と、「神国思想」と「粟散辺地説・末法思想」の対立関係で理解されることが一般的でした。
こうした「粟散辺地説・末法思想vs神国思想」という単純な対立構造で見たほうが、理解しやすいのは確かですね。
しかし、単にそう見ることはできません。
関係性としては、「神国思想」と「粟散辺地説・末法思想」の両者には、融合している面も大いにあるのです。
ここまでの説明で、私がこだわって、「セットになった」というような表現を使ってきたのは、このためです。
どういうことかというと、さきほど『沙石集』などの例を挙げたように、「日本は粟散辺地であり、今の時代は末法だ」とする意識が高まれば高まるほど、「そんな国・時代をも救おうという神仏の慈悲が深く降り注ぐ国」として、神国思想がいっそう後押しされて出てくるわけです。
また逆に、神国思想が鼓吹されればされるほど、「今の日本は、本来であればこれほど救われ難いのだ(なのに神仏が救いに来てくれた)」という、粟散辺地説・末法思想の強調も、連動して起こっていくのです。
つまり、神国思想と末法思想・粟散辺地説は、お互いがお互いを生み出し高める基盤となり、いわば螺旋状になっているという面も大きいのです。
そのため近年の研究では、
「神国思想と、粟散辺地説・末法思想の関係は、単なる対立構造にはおさまらない。
両者には、融合的な面も大いにあるのだ」
という、新たな指摘が行われています。
とはいえ、当時の神国思想についての言説には色々なものがありますから、一つの観点から括ることはできません。
「神国思想によって粟散辺地説・末法思想を乗り越えた」と面もあり、その図式が完全に間違っているわけではありません(その図式だけで理解するのがまずいということです)。
そのため、「これ以上話が複雑になると困る」という方は、さしあたり、「神国思想によって粟散辺地説・末法思想を乗り越えた」という古くからの学説に沿って理解していただいてもOKです。
余裕のある方は、「2つの説をセットと捉えるという新たな研究も出てきているんだな」という程度でも良いので、近年の研究の学説についても、ぜひ頭の片隅に入れておいていただければと思います。
このことを補足しておきたく、少し脱線しました。
では最後に、第三の③「蒙古襲来による、神国思想の鼓吹」について、次節で見ていきましょう。
蒙古襲来による、「神国思想」の鼓吹
第三の③「蒙古襲来による、神国思想の鼓吹」に移ります。
時代的には、①「公家のイデオロギーとしての、神国思想の鼓吹」と、②「末法思想に伴う、神国思想の鼓吹」がすでに起こった上で、③が起こります。
詳しく言えば、①②によって日本を神国として高く評価する意識が高まっていたところに、極めつけの出来事として、③が起こったということです。
具体的に見ていきましょう。
鎌倉時代の半ばに、元の軍勢が来襲します。
有名な蒙古襲来です。
元寇ともいいますね(1274年と1281年の2回の襲来です)。
日本史上、よく知られている大事件ですね。
日本にとっては初めての、大規模な外敵の襲来でした。
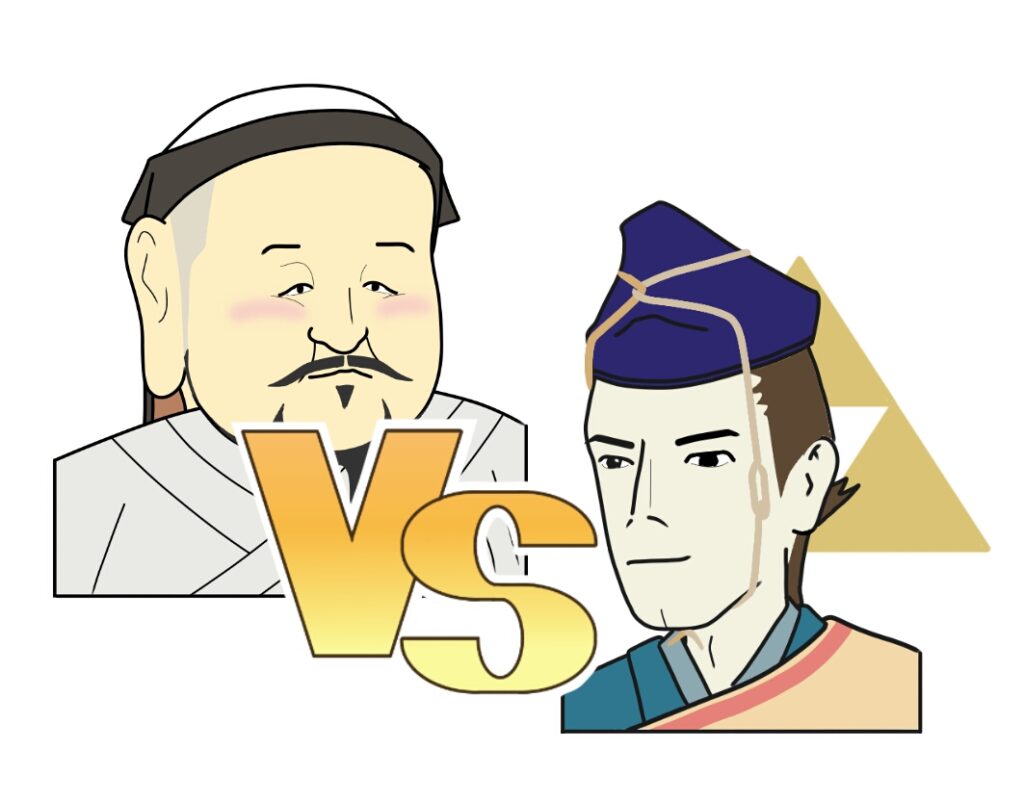
この時、元軍を驚き恐れた幕府や朝廷は、外敵を調伏する(抑え込む)ために、数々の祈祷を行いました。
現に、公家は武家の力よりも、寺社の祈祷に敵国降伏の効果を期待していました。
また、武力で元軍に相対する武士たちも、積極的に、神々に日本国の無事を祈願したのです。
公家も武家も、その双方が、いわゆる神頼みをしたということです。
今の私たちからすると、国中が神頼みをすることを不思議に思われるかもしれませんが、この時代には、これほど神仏が身近だったのですね。
宗教が深く根付いていたともいえます。
いずれにしても、こうした中で、「日本には古来から神々の加護があったのだから、今回の祈祷にも必ず応えてくださる」と、神国思想が強調されることになったのです。
そして、ついに元の襲来が起こりました。
日本軍が苦戦し、国中の不安が高まっていたそのとき、突如として大風が吹き、敵国の船団を壊滅させ、元軍を追い返しました。
この風が神風と呼ばれたことは有名ですね。
これは、当時の人たちにとっては、まさに「私たちの祈願に応えて、神々が神風によって日本を救ってくださった」という出来事でした。

こうして元寇は、日本史上外敵と相まみえ、神の力でそれを追い返した最大の出来事ととして、「神国思想」を大いに鼓吹させることになりました。
また、後に詳しくお話しますが、元寇は、後世において「神国思想」が鼓吹される時に、その強力な根拠ともなります。
後世の「神国思想」への影響という点でも、元寇は、重要な出来事だといえるのです。
以上、平安末~鎌倉時代における「神国思想」の隆盛を見てきました。
ここまでのポイントをまとめると、以下の通りです。
◎平安末~鎌倉時代において、「神国思想」が隆盛した背景には、大きく3つの要素がある。
◎第一に、公家が、武家に対抗して、天皇を中心とする政治制度を維持するために、そのイデオロギーとして、「神国思想」を鼓吹し始めた。
◎第二に、「末法思想」が浸透する中で、それと連動する形で、「日本は末法の地ではあるが、逆に言えば、神仏の救いが究極的に行われる地(神国)なのだ」と盛んに主張されるようになった。
◎蒙古襲来の中で、外敵を神風が追い返すということが実際に起こったため、「やはり日本は神に護られた国なのだ」という認識が深まった。
以上のように、鎌倉時代頃には、いくつかの要因により、自国優位意識を伴う「神国思想」が隆盛し、多くの人々の間に広まったのです。
そのため、この時代は、「神国思想」の歴史の上で、まことに重要な時期だといえます。
では、この後の時代にはどうなったのでしょうか?
全てを紹介はできませんので、主要なものをピックアップして、見ていくことにしましょう。
戦国時代
その後の「神国思想」の展開として特筆すべきは、室町時代末・戦国時代です。
室町末期に対外関係が複雑になった時、キリシタン(室町末頃に日本に伝えられた、キリスト教ローマカトリックの信徒)に対して、「日本は神国だ」という主張が盛んに行われたのです。
現に豊臣秀吉(1537年~1598年)は、日本が神国であることを踏まえ、「異教徒は取り締まるべきだ!」と主張しました。
秀吉のキリシタン弾圧には、色々な要素があったといわれていますが、少なくとも秀吉は、表向きの理由として、神国思想を出すことによって、キリシタンの禁圧を正当化したのです。

また秀吉と神国思想との関わりについて、もう一点重要な出来事があります。
すなわち「唐入り」です。
「唐入り」とは、秀吉が明(当時の中国)の征服を目指して、手始めに朝鮮に攻め込んだ、侵略戦争のことです。
秀吉は、唐入りの際、粟散辺地説、すなわち「インド・中国という大国―はずれの地である日本」というマイナスの自国意識を、完全に裏返した、自国優越主義的な神国思想を打ち出しました。
つまり秀吉は、下位の身分から天下人に駆け上がった自身のように、粟散辺地である日本が三国全域の覇者にのし上がることを夢見たのです。
思い切って表現するなら、「下等な粟散辺地による、他の大国への下剋上」とでも言えるかもしれません。
もっとも、先ほど述べたように、すでに元寇の頃などから、自国優位かつ排他的な神国思想が生まれていたといえます。
しかし秀吉は、それをいっそう明確化して強調し、さらにそれを現実化しようとしました。
これは、秀吉の特色です。
現に秀吉は、朝鮮や明、さらにその後の世界征服という大掛かりな目標を立て、実際の出兵までも行ったのです。
秀吉の他国侵略を支える基盤となったのが、他国に対して排他的な神国思想であることや、そのような秀吉の持つ排他的な神国思想の内容を示す資料がありますので、御紹介しておきましょう。
秀吉は、朝鮮出兵を控えた天正19年(1591)に、インド総督に向けて、次のような内容の書簡を送っています。
「我が国は神国である。
神はあらゆる存在の根源である。
この神はもともとインドに現れた。そのときの教えを仏法という。
その後中国にましました。そのときの教えを儒教という。
そして日本に至って、その教えを神道と言うようになったのである。
ということは、神道を知れば仏法を知り、儒教を知ることになるのだ」。
ここで秀吉は、神道を根源に据え、「神道こそがインドで生まれた仏教も、中国で生まれた儒教も包摂する」という考え方を示しています。
もっとも、この書簡の内容だけ見れば、単に「神道の意義づけを試みた主張」と見なすことも可能かもしれません。
しかし、ここで重要なのは、これがインド総督に向けての発言であることです。
すなわち秀吉は、この書簡で、「神道がインド・中国の宗教や思想を包む」という考え方を示すことで、「日本(神国)は本来インド・中国を統率する覇者である(そうならねばならない)」ということを、他国へ伝えようとしているのです。
このように秀吉は、インド・中国の征服、ひいてはその前段階としての朝鮮への侵略を正当化するためのイデオロギーとして、「神国思想」を用いているのです。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Documentary_painting_of_the_Battle_of_Hansan_Island.jpg?uselang=ja)】
本節の内容をまとめると、以下の通りです。
◎秀吉は、朝鮮・明・インドの征服を目指していた。
その際に秀吉がよりどころにしたのは、「神や神道こそが根源だ」という思想である。
◎つまり、この時代には、「神国思想」が、他国への侵略を正当化するイデオロギーとして機能することになった。
「神国思想」の持つ排他性が、この時代にいっそう強まったといえる。
さきほど見たように、すでに鎌倉時代の「神国思想」にも、自国優位性や、他国の排他性という要素が加わっていました。
そのため、秀吉の打ち出す「神国思想」については、その淵源は鎌倉時代にあるといえます。
しかし、「神国思想」が、現実に侵略の正当化に使われ始める(ひいては、現実に侵略行為まで行われ始める)というのは、この時代の「神国思想」の大きな特徴だといえるでしょう。
江戸時代
江戸時代に入ると、神国思想は儒教思想と結合して、水戸学(常陸国の水戸藩に始まる学風)などの「国粋主義思想」を生み出すことになりました。
国粋主義とは、自国の歴史や文化などが他国よりもすぐれているとして、それを守り発展させようとする主張のことです。
現代風に、簡単に言ってしまえば、過度なナショナリズムです。
こうして神国思想は、「日本中心主義」を掲げた思想家たちによって、活性化されていったのです。
これらの日本中心主義者たちの打ち出した「神国思想」においては、「単に統治者たる天皇のみならず、国民も神々の子孫である」との考え方が強調されました。
すなわち、いわゆる選民思想(自らの民族を至上とする思想)に繋がる考え方が、ここで打ち出されたのです。
(これは、後に見る、戦時中の日本の思想に繋がるものです。)

こうした江戸時代における神国思想の高まりには、歴史的に大きな意味があります。
なぜなら、「神国思想」が、有名な幕末の尊王攘夷運動(天皇を尊び、異国を追い払おうとする思想や運動)に重要な精神的基盤を与えることになったからです。
幕末の志士たちは、天皇を尊び、他国を排斥しようとし、そのことに命を懸けました。
そうした志士たちを奮い立たせたのが、「天皇は神であり、国民は神の後裔であり、日本は神のまします特別な国なのだ」という神国思想だったのです。
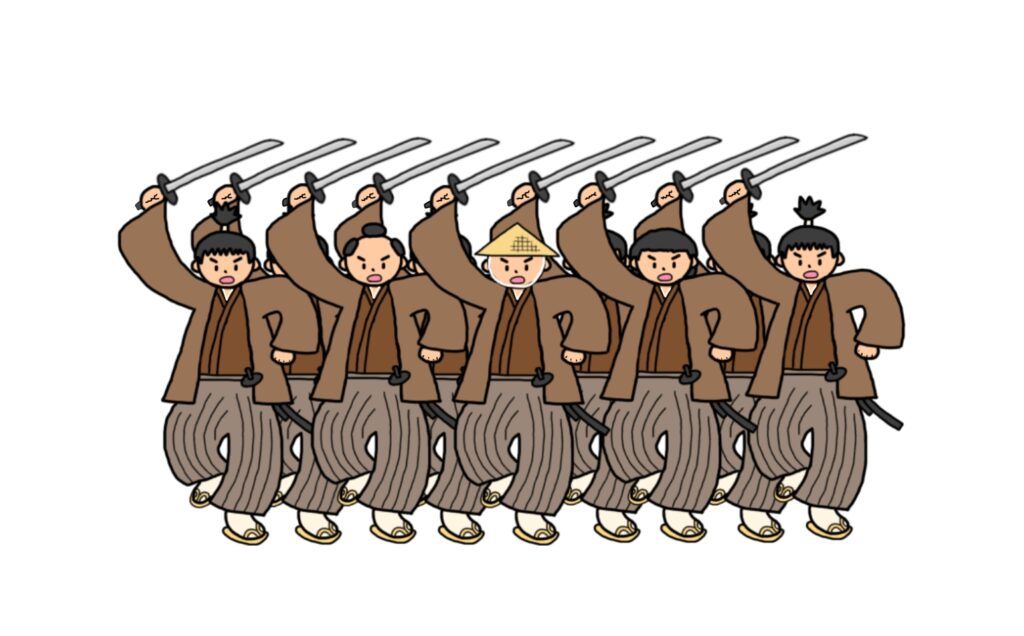
ちなみに、さきほどの元寇のところで少しだけ触れましたが、こうした「異国を排斥しよう」とする攘夷運動において、盛んに引き合いに出されたのが元寇です。
当時の人々にとっては、元寇は、いわば「神国である日本が、神の力により他国を追い払う」ということの具現化であり、大変重要な出来事でした。
だからこそ、この出来事が、重要な根拠と見なされ、盛んに引き合いに出されたのです。
本節の内容をまとめると、以下の通りです。
◎江戸時代には、「神国思想」が攘夷運動の中で、盛んに打ち出されていった。
この時代の「神国思想」も、秀吉の時代と同様に、異国に対する排他性が強いといえる。
明治時代以降
その後、明治維新を経て、日本は対外戦争の時代に突入することになります。
「神国思想」は、このような相次ぐ戦争の際に、国民の心情を統一する役割を担いました。
「神国思想」が負の遺産といわれるときには、よくこの時代が引き合いに出されます。

さきほども述べたように、「神国思想」はある意味で選民思想を伴うものです。
昭和のファシズム体制下においては、特にこうした選民思想が強調され、「大東亜共栄圏」の建設(欧米の植民地支配にかわって、日本を盟主として東アジア世界を支配すること)に向けて、国民の精神を団結させるための基盤として、大きな役割を果たしました。

大東亜共栄圏の範囲をあらわす切手(1942年12月発行)
【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DaitouaKyoueiken.JPG?uselang=ja)】
すなわち、「異国に対して、神国日本を、神孫である天皇を、ひいてはその末裔である日本国民を守る!」ということを原動力として、日本は大戦争の道を突き進んでいったのです。
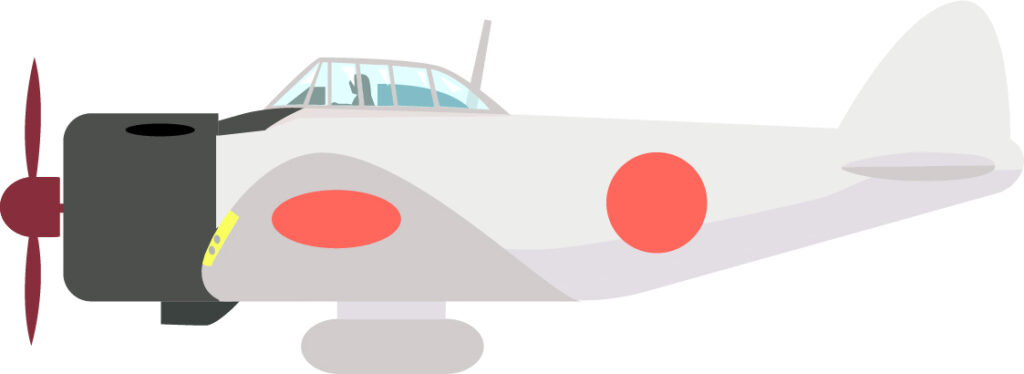
結果、日本は世界大戦に敗れ、GHQの管理下に置かれることになります。
それにより、敗戦後から今に至るまで、しだいに「神国思想」は歴史の裏に影をひそめることになったのです。
ここまでのポイントをまとめると、以下の通りです。
◎近代になると、「神国思想」は排他性をいっそう強め、選民思想にもつながった。
それにより、日本は、「欧米を退けて大東亜共栄圏を築く」という狙いのもと、世界大戦に突き進むことになった。
◎しかし、結果は敗戦となり、「神国思想」は歴史の表舞台から姿を消していった。
最後に
以上、「神国思想」のルーツや、現代に至るまでの、歴史的展開を解説してきました。
冒頭にも述べたように、「神国思想」には賛否両論あります。
しかし、私は神国思想が良いか悪いかを簡単に議論するために、本記事を書いたのではありません。
神国思想は、良くも悪くも、過去の日本を大きく動かした重要な思想です。
そのような神国思想について、「ルーツから歴史までしっかりと学び、評価はどうあれ、その内実を深く理解していただきたい」と思ったからこそ、本記事で解説を行ったのです。
グローバル化の進む中、過去の日本の重要な思想について深く理解している人が今の日本に増えることには、大変大きな意味があると私は思います。
人間関係などもそうだと思いますが、批判をしたり、好き嫌いを判断したりする際には、その前にそのこと(あるいは人)をきちんと知ることが重要です(改めて言うようなことではありませんね)。
「神国思想」も、本記事を踏まえて、好意的に見るか、嫌悪感を懐くかは、人それぞれあって良いのです。
大事なのは、好きか嫌いかはどうあれ、それを判断する前に、「神国思想」そのものについて、客観的にきちんと知ることです。
現在は、聞きかじりの知識や偏ったイメージのまま、過去の思想を論じたり、好き嫌いを判断したりすることがよくあり、そういうことが起こりすぎていると、私は思っています。
当り前のことですが、どんな場合でも、内容を深く知った上で判断するということが大切だと思います。
「神国思想」のような複雑な思想については、そういう取り組みがとりわけ必要だと思います。
本記事が、その一助になれていたら、大変うれしく思います。
参考文献とお勧めの書籍
【参考文献一覧】(年代順)
本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。
いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。
学恩に心より感謝いたします。
◎黒田俊雄『神国思想と専修念仏』(黒田俊雄著作集 第4巻、法藏館、1995年)。
◎鍛代敏雄『神国論の系譜』(法藏館、2006年)。
◎岡野友彦『北畠親房 大日本は神国なり』(ミネルヴァ日本評伝選、ミネルヴァ書房、2009年)。
◎伊藤聡『神道とは何か 神と仏の日本史』(中公新書2158、中央公論新社、2012年)。
◎片岡耕平『穢れと神国の中世』(講談社選書メチエ545、講談社、2013年)。
◎佐藤弘夫『「神国」日本 記紀から中世、そしてナショナリズムへ』(講談社学術文庫2510、講談社、2018年)。
◎齋藤公太『「神国」の正統論 『神皇正統記』受容の近世・近代』(ぺりかん社、2019年)。
◎佐藤弘夫『アマテラスの変貌 中世神仏交渉史の視座』(法蔵館文庫[さ2-1]、法藏館、2020年)。
◎佐藤弘夫『日本人と神』(講談社現代新書2616、講談社、2021年)。
◎伊藤聡『日本像の起源 つくられる「日本的なるもの」』(角川選書653、KADOKAWA、2021年)。
【お勧めの書籍】
では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。
内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。
◎佐藤弘夫『「神国」日本 記紀から中世、そしてナショナリズムへ』(講談社学術文庫2510、講談社、2018年)
東北大学名誉教授であり、日本の古代・中世の思想史の大家である佐藤弘夫先生の御著書です。
この書では、「神国とは何なのか?」について、古代→中世→近世→近現代と、時代ごとの変容を、詳細に整理しています。
「神国思想」がどのように形成されてきたのか、またその論理はいかなるものなのかについて、詳細に学ぶことができます。
佐藤先生の御著書は、いずれも、たくさんの情報を示しながらも、読みやすく、かつ分かりやすく書かれているのですが、本書もそうです。
「神国思想」をめぐる多くの史料に触れながら、内容をしっかり理解することができます。
本記事でも、本書から多くを学びました。
お勧めしておきます。
◎伊藤聡『日本像の起源 つくられる「日本的なるもの」』(角川選書653、KADOKAWA、2021年)
神道研究の大家である、伊藤聡先生の御著書です。
この書は、「神国思想」だけを扱った書ではありません。
「神国思想」だけではなく、「従来、私たちが持っている日本的というイメージ(日本像)は、どのようにして形成されてきたのか?」や、「日本人はこれまで、世界の中に、自国をどのように位置づけてきたのか?」などについて、時代ごとに分析し、整理した良書です。
そのため、内容も、「神国思想」、大国中国との関わり、天竺(インド)への憧れ、日本の文字、「武の国」という日本像など、多岐にわたります。
「神国思想」は第一章で重点的に扱われていて、様々な観点から、多角的に分析しています。
特に、豊臣秀吉と「神国思想」との関わりをめぐる分析は大変興味深く、本記事を書くうえで、大変大きな学びを得ました。
また、さきほど述べたように、他の章では、「神国思想」以外の観点から、「日本像」の起源や歴史を明らかにしていますので、全体を読めば日本の思想史について、様々な観点から学ぶことができます。
そうした意味でも、本書はとてもお勧めです。
本記事はここまでです。
ではまたほかの記事でお会いしましょう!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!
本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!
また、いいねの数が大変励みになります。本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押して応援していただけると、とても嬉しいです!

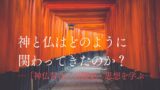




コメント