こんにちは!
学問ボウズです。
本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます。
現在の日本では、浄土宗・浄土真宗・時宗は、大変有名な宗派ですよね。
これらは、同じく法然(1133年~1212年) を元祖として生まれた宗派です。

しかし、宗派として分かれていることからも窺えるように、教えの内容はかなり違います。
皆さんは、これらの教えの違いについて、どのくらい知っていらっしゃるでしょうか?
でも、こう聞くと、「そんな厳密に知らなくてもいいじゃん。なんとなくでいいじゃん」と思われる方がいるかもしれません。
もちろんそれも一理あります。
「知らないとやばい、だから絶対知っておくべき」というものでもないかもしれません。
でも宗教の問題は、私たちが普通考えている以上にデリケートです。
信心深い信者の方にそういう態度でのぞむと、傷つけたり、不快な思いをさせてしまう恐れもあります。
浄土宗・浄土真宗・時宗は、今現在、信者の方々が多くいる宗派である以上、きちんと理解しておくに越したことはありません。
何より、三者三様でとにかく面白いので、単純に楽しむという目的で気軽に読んでいただきたいです。
もちろん、この3つの宗派の共通点、相違点を説明する本やサイトはすでにいくつかあります。
でも、誰が一番すごいということを言うために、偏った説明がされていることが多いです。
これだと、誤解を招きます。
本記事では、中立的に、なおかつ違いが分かりやすいように説明していきたいと思います。
3つの宗派の違いを学びながら、その多様さを楽しんでいただければと思います。
浄土教とは何か
浄土宗・浄土真宗・時宗は、大きくは全て浄土教という括りに入ります。
まず、浄土教とは何かについて確認しておきましょう。
浄土教とは、「阿弥陀仏の浄土(極楽浄土)に生まれなさい」と勧める教えです。
阿弥陀仏の浄土に往き生まれることを、往生といいます。

三つの宗派ともに、この大枠は変わりません。
浄土教が日本に浸透していく中で、法然が浄土宗という宗派を開いて、いわば浄土教に特化した宗派を確立させ、浄土真宗と時宗はそれを根幹にして派生していったわけですから、このことは当然といえば当然です。
しかし、これら三つの宗派は、同じ浄土教系の宗派であるとはいえ、修行と信心をどのように理解するか、往生や成仏(悟りをひらいて仏になること)をどのように理解するかなどの点で、各々個性的な考えを示しているのです。
これは、「同じ浄土教なのになぜなのか?法然を崇拝し、法然から教えを受けついでいるのになぜ?なのか」と、非常に興味深い問題です。
以下、順に詳しく見ていきましょう。
修行と信心についての理解の違い
修行・信心とは何か?
浄土宗、浄土真宗、時宗で勧める修行とは、お念仏です。
念仏行ともいいます。
阿弥陀仏の名を称え呼びかける、「南無阿弥陀仏」ですね。
阿弥陀仏の名は「名号」とも言います。
「南無阿弥陀仏」のうち、「南無」とは「帰依します。お願いします」という意味で、「阿弥陀仏」とは、言うまでもなく阿弥陀仏の名そのものです。
つまり、「南無阿弥陀仏」は、「阿弥陀仏に帰依します」という意味なのです。

仏教では、悟りを開くために修行を大変重視します。
そのため浄土教においても、念仏を行うことが大変重要視されます。
とはいえ、修行のみではまだ不完全です。
修行と双璧をなすほど大切なものとして、信心という要素もあります。
信心とは、浄土教でいうと、「うそやいつわりのない心で、阿弥陀仏の救いを深く信じて、極楽浄土に往きたいと願う心」のことです。
「信心をおこして、南無阿弥陀仏と称えれば、すなわち信心と念仏行の2つをそなえれば必ず往生できる。だから信心と念仏の2つが大事なのだ」というのは、浄土宗・浄土真宗・時宗のいずれも同じです。
ただし、この3つの宗派は、「修行と信心をどのようにして起こすか」という点で、明確に異なるのです。
以下、浄土宗・浄土真宗・時宗の順で見ていきましょう。
浄土宗の理解
まず、浄土宗はどう考えるかから見ていきましょう。
浄土宗では、「往生を願う人が、みずから信心をおこし、念仏行を行うのだ」と理解します。
客観的に見て、一番イメージのしやすい考え方だと言えましょう。
「普通そうだろう」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
浄土真宗の理解
一方、浄土真宗では、浄土宗とは明確に異なる理解をします。

浄土真宗では、「阿弥陀仏が衆生(生きとし生けるものたち)に対して、すでに名号を通して働きかけているのであり、衆生はそのおのずからなる救済を受けとめれば良いのだ」と説きます。
もう少し具体的にいうと、さきに述べたように、法然は「修行者である私が南無阿弥陀仏と称えること」を前提に考えていました。
これに対して親鸞は、「実はその前に、もう阿弥陀仏のほうから、南無阿弥陀仏という名号を通して、『私に帰依せよ』と衆生一人一人に呼びかけているのだ」と理解するのです。
すなわち、衆生のはたらきかけよりも、阿弥陀仏のほうが先だということです。
そのため衆生は、「自身が起点となり、信心を起こし、念仏を行う」というのではなく、「すでにもたらされている阿弥陀仏の呼びかけに応えれば良い」ということになるのです。
親鸞は、念仏について以上のような理解をしており、これは親鸞の教理体系の核となっています。
「南無阿弥陀仏」についてもう少し詳しくいえば、浄土真宗において「南無阿弥陀仏」とは、浄土宗のように単に「阿弥陀仏に帰依します」という意味を持つのではないということです。
「南無阿弥陀仏」の真意とは、「私に帰依せよ」という阿弥陀仏の呼び声であると同時に、それに行者が「はい」と任せる応答という、呼びかける阿弥陀仏と応える衆生双方の関係を表すものということになります。
親鸞の教えは複雑でイメージしにくいところがあるので、少し難しい感じた方もいらっしゃると思います。
そういう方はひとまずざっくりと、「浄土真宗では、阿弥陀仏のほうが衆生のはたらきかけよりも先ということを強調する」というイメージを持っておいていただければOKです。
また今までは念仏について重点的に述べましたが、「浄土真宗では、阿弥陀仏のほうが衆生のはたらきかけよりも先ということを強調する」というのは、信心についても同様です。
浄土真宗では、「信心は衆生が起こすものではなく、阿弥陀仏がもたらすものだ」と説きます。
私たちは穢れた心ばかりで、清らかな信心なんて起こせないけれども、そんな私たちに阿弥陀仏が清らかな心をもたらしてくれるというのです。
このように浄土真宗では「信心はたまわるものだ」と考えるため、信心のことを敬語表現で「ご信心」というときもあります。
以上、詳しめに親鸞の念仏・信心理解について説明してきました。
法然と親鸞の間で、理解がかなり違っていることがお分かりいただけたかと思います。
少しややこしいですが、師と弟子の間でもこれほど教えが変容しているのが、浄土教思想史のおもしろさです。
時宗の理解
では時宗ではどうなのでしょうか。
一遍の教説も大変特徴的です。
まず念仏行から見ていきましょう。
一遍が説く念仏行は、さらにスケールが大きいものとなります。
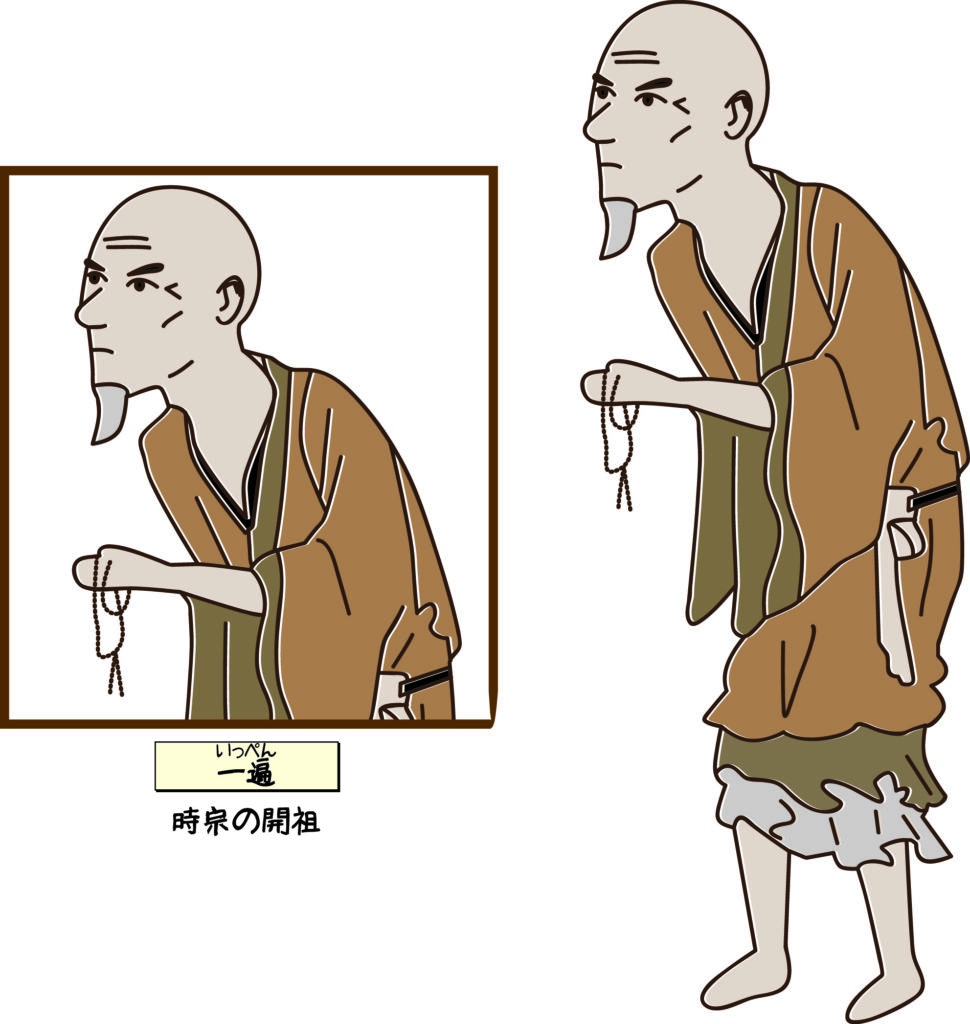
どういうことか、説明していきます。
一遍においては、念仏行はどちらがどちらに働きかけるということではありません。
一遍は、「南無阿弥陀仏と称えれば、衆生も阿弥陀仏そのものも、その中で渾然と一体化する」と捉えます。
つまり「南無阿弥陀仏の中には、私もなく仏もなく、ただ南無阿弥陀仏だけが響きわたるような世界が開ける」というのです。
さきに述べたように、浄土宗や浄土真宗では、南無阿弥陀仏は行者と阿弥陀仏のどちらかに属するものでした。
法然は「衆生の側から称えて阿弥陀仏に呼びかけるもの」として理解し、親鸞は「阿弥陀仏の方から衆生に呼びかけるもの」と見なしていましたね。
一遍においては、「南無阿弥陀仏」(名号)は、こうした衆生ー阿弥陀仏の二項関係のいずれに属するものでもありません。
名号は、その両方を包み、一体化させる、根源的な場所というべきものなのです。
以上のように一遍は、「南無阿弥陀仏が全てを包み、全世界が南無阿弥陀仏だけになるような境地」を説きました。
こうした全てを包む「南無阿弥陀仏」を、「独一の名号」といいます。
一遍思想においては、名号は仏すらも超えて、真理そのものとして全てを包んでいるのです。
一遍の思想もなかなかにイメージしにくいものだと思われます。
しかしこれはあくまで宗教的な境地の話です。
言い換えれば、修行の中でおのずと感じられてくる(修行者の眼前にのみ立ち現れてくる)宗教的な世界なのです。
なので、論理的にどういう境地かを事細かに説明できるものではありません(もっといえば、そうすべきものでもありません)。
この点を踏まえていただければ、時宗の説く壮大な世界観も受け入れやすくなるでしょう。
以上、法然・親鸞・一遍の念仏と信心についての理解を見てきました。
ここで改めて、三者の理解の相違点をまとめておきましょう。
法然…行者がみずから信心を起こし、南無阿弥陀仏と称えて、行者の方から阿弥陀仏に呼びかける。
親鸞…すでに阿弥陀仏の方から名号を通して行者に呼びかけているため、行者は信心をいただき、その呼び声に応答するだけで良い。
一遍…南無阿弥陀仏と称えれば、その中で行者と阿弥陀仏が一体化し、南無阿弥陀仏だけが鳴り響くような世界が生まれる。
往生や成仏についての理解の違い
往生と成仏の関係
では次に、往生や成仏についての理解の違いを見ていきましょう。
往生とは、阿弥陀仏の西方浄土に生まれること。
成仏とは、釈尊(お釈迦様)や阿弥陀仏などに同じく、仏になる(悟りを開く)ことですね。
仏教は総じて「お釈迦様のようにこの世界で修行して、成仏しなさい」と説きます。
今の日本の天台宗や真言宗などの多くの宗派は、本来こうした「この世で成仏する道」を教える宗派です。
これに対して浄土教は、「お釈迦様が亡くなってからもはや大変長いときが経っており、釈尊の教えも衰退している。そのためこの私にはもう、この世界で修行して成仏する能力はない」と考えます。
そのため、「一旦、阿弥陀仏の浄土に往かせてもらい、浄土で阿弥陀仏に導かれながら修行して、仏にならせてもらおう」と考えるのです。
要は、いきなり成仏を目指すのではなく、阿弥陀仏の浄土に往生するという段階を一旦経由するイメージです。
これが浄土教における往生と成仏の関係です。
そのため、往生がゴールではなく、往生してからまたある程度時間をかけて修行を重ねて成仏するというのが本当のゴールなのです。
こういった理解が、インド・中国の浄土教におけるスタンダードな立場でした。
日本においても、浄土宗までは主にこのような理解をしていました(後に詳しく述べます)。
しかしその後、浄土真宗と時宗では新たな理解が行われるようになっていくのです。
順に見ていきましょう。
浄土宗の理解
浄土宗では、「信心を起こして念仏を行えば、臨終に阿弥陀仏がやってきて、浄土に迎え取ってくださる」と理解します。
そして、「浄土に往生した後に、阿弥陀仏の説法を聞き、阿弥陀仏に導かれて修行して、ようやく仏になる」と考えるのです。

先ほど、「浄土教におけるスタンダードな理解は、往生して、その後時間をかけて修行を積み、ようやく成仏するという考え方だった」ということを述べました。
浄土宗でも、このオーソドックスな立場を取り、浄土に往生したとはいえ、それで全てが完成するのではなく、その後長い時間をかけて、だんだんと仏になっていくと理解するのです。
もちろん、修行といっても、阿弥陀仏に導かれて、清らかな浄土という最高の環境で行うものなのですから、厳しく辛いものではありません。
任運に、安らかに進むような修行です。
その点で、他の宗派が説くような忍耐のいる修行とは異なるといえます。
とはいえいずれにしても、「成仏するには修行を積むことが必要だ」とする考え方については、浄土宗も他の宗派と同じように、これをベースにしているといえるのです。
「イメージしやすい考え方だ。仏教では修行を重視するのだから、普通こうだろう」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、親鸞と一遍においては、この理解が大きく変わるのです。
浄土真宗の理解
浄土真宗では、「往生即成仏」を説きます。
「往生=成仏」、すなわち往生したらすぐに仏になるということです。
さきにお話ししたように、浄土真宗では、信者はすでにこの世界で、阿弥陀仏からの「ご信心」をいただいた存在です。
そのため信者は、身はこの世の身のままであり、煩悩(貪りや怒りなどの心のけがれ)だらけですが、心には清らかな信心をそなえた、尊い存在だともいえます。
これを踏まえて親鸞は、「正像末和讃」で、
「真実信心うるゆえに すなはち定聚にいりぬれば
補処の弥勒におなじくて 無上覚をさとるなり」
とうたっています。
大まかにこの意味を示すと、
「真実の信心を得て、定聚(仏になることが定まっている位)に至ったのだから、
補処(次の一生で仏になれる位)の弥勒と同じとなり、必ず悟りを開くのだ」ということです。
弥勒菩薩は、釈尊の後、次の仏としてこの世界に降ってきてくださる、大変高位な存在です。
親鸞は、「信心をいただいた者は、この尊い弥勒菩薩と同じだ」とまで言っているのですね。

このように浄土真宗の信者は、この世にいる凡夫(仏教的な能力や知識にとぼしい者)でありながら、菩薩の性質も兼ね備えているような尊い存在です。
こういう尊い存在が、この世界の命を終えて、阿弥陀仏の浄土に往くわけですから、もはや長い修行など必要なく、すぐに仏になることができるのです。
言い換えれば、阿弥陀仏の力によって、往生した一瞬のうちに阿弥陀仏と同じ覚りを得られるるということです。
まとめると法然の考え方は、「往生し、それから成仏」とするものだといえます。
これに対して、親鸞は「往生即成仏」と見るのです。
文字ずらでいえば大した違いはないようにも思えますが、実態としてはかなり大きな変化が起こっているといえましょう。
時宗の理解
では一遍はどうなのでしょうか。
先ほど、「一遍は全てが南無阿弥陀仏に包まれる世界を説いていた」ということを説明しました。
一遍は、この境地に至れば、死後ではなく今ここに、往生や悟りが実現するといいます。
つまり一遍は、死後に往生するという、浄土宗や浄土真宗の理解とは明確に異なる立場を取るのです。
もう少し詳しくいえば、一遍は「南無阿弥陀仏と称えるなかに、浄土もあり往生もあり、さらにその中で阿弥陀仏と一体化して成仏する」と考えています。
これは、「往生や成仏は死後である」という法然や親鸞らの理解をひっくり返す、斬新な理解だといえます。

三者の理解をまとめてみましょう。
法然…死後に往生し、さらにそこから時間をかけて成仏する。
親鸞…死後に往生し、往生すると即座に成仏する。
一遍…今のこの身のまま、往生し成仏する。
このように、浄土宗→浄土真宗→時宗と新たな宗派が生まれていくにつれて、だんだんと往生や成仏までの時間やハードルが消えていくという傾向にあるのです。
ちなみに「速疾性」をいっそう求めていくというのは日本仏教の特徴ですので、今お話しした法然・親鸞・一遍の思想の相違も、もっと広い視野で考えるべき事柄だといえます。
今回はもう大変長くなっていますので、また別の記事で、日本仏教全体から俯瞰して考えるということに挑戦したいと思います。
最後に ―浄土宗・浄土真宗・時宗のどれが一番すごいのか?―
ここまでの学びを踏まえ、「浄土宗・浄土真宗・時宗のどれが一番すごいのか?」という問題について、最後に考えることにしましょう。
これは昔からよく議論されているテーマですが、主に「一遍が完成させたから一遍が一番偉い。親鸞が大きく変えたから親鸞が一番偉い」などという結論になりがちです。
そうなると、法然はたいしてすごくないことになります。
現に、これまではそういう評価が行われることが多かったのです。
顕著な例が教科書です。
数年前まで、高校の倫理や日本史の教科書では、「親鸞が法然の他力の教えを深めた」というような記述がされてきました。
しかし「教えを変えたからすごいのか」ということから問い直すべきでしょう。
三者の教えは、みなそれぞれ体系的です。
三者三様でそれぞれに特色がありながら、各々の教理体系としては全体として矛盾なく構築されています。
いわば、三者三様に完成された思想なのです。
それを後世の人間が、「誰がすごい、すごくない」と安易にいうべきではないのだろうと思われます。
排他的にならず、(稚拙な言い方かもしれませんが)「みんな違ってみんなすごい」ということを認めるべきだと思います。
私も本記事では、そういう思いで中立的に記述をしてきました。
教科書問題についても、近年、浄土宗の研究者によって批判が行われ、しだいに改正に向かっています。
みなさまが過去に使っていた教科書から(もし学生さんが読んでくださっているのであれば、現在使っている教科書から)、法然や親鸞についての記述がしだいに改められているのです。
中立を重視する学問・教育の姿勢として、あるべき姿だと思います。
もちろん、本記事を読んでくださった皆様の中で、「法然・親鸞・一遍のうちの誰が好き、誰の教えに一番親近性を感じる」という感情は人それぞれあって良いです。
そのほうが楽しく学べますし。
ただし客観的に学ぶときには、偏らず中立的に日本仏教・浄土教を深く学ぶということを行っていただきたいと思います。
本記事がそのお役に立てたなら、とても嬉しいです!
参考文献一覧とお勧めの書籍
【参考文献一覧】(年代順)
本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。
いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。
学恩に心より感謝いたします。
◎神子上恵龍『弥陀身土思想の展開』(1968年)。
◎高橋弘次『法然浄土教の諸問題』(改版増補、山喜房佛書林、1994年)。
◎釈徹宗『法然親鸞一遍』 (新潮新書439、新潮社、2011年)。
◎阿満利麿『法然入門』(ちくま新書918、筑摩書房、2011年)。
◎浄土宗総合研究所編『現代語訳 法然上人行状絵図』(浄土宗、2013年)。
◎浄土宗総合研究所編『浄土宗の「浄土三部経」理解 法然上人と親鸞聖人の相違をめぐって』(浄土宗、2014年)。
◎竹村牧男『親鸞と一遍 日本浄土教とは何か』(講談社学術文庫2435、講談社、2017年)。
◎浄土宗総合研究所編『法然上人のご法語』1~3(文庫版、浄土宗出版、2021年~2022年)。
◎加藤智見『図説 極楽浄土の世界を歩く! 親鸞の教えと生涯』(青春出版社、2022年)。
◎紅楳英顕『親鸞聖人はどんな教えを説いたのか? 浄土真宗の開祖・親鸞入門』(22世紀アート、2024年)。
◎林田康順監修『法然と極楽浄土』(図説ここが知りたかった!、青春出版社、2024年)。
【お勧めの本】
では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。
内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。
まず、釈徹宗『法然親鸞一遍』 (新潮新書439、新潮社、2011年)です。
宗教学の専門家で、相愛大学の学長の釈徹宗先生のご著書です。
法然・親鸞・一遍の教えを詳細に分析した良書です。
この一冊を読むだけで、三者の教えの要点や相違点がよく分かります。
次に、竹村牧男『親鸞と一遍 日本浄土教とは何か』(講談社学術文庫2435、講談社、2017年)です。
東洋大学名誉教授・筑波大学名誉教授で、仏教研究者で知らない人はいない、大変有名な竹村先生の御著書です。
特に、親鸞と一遍の思想を比較考察した本です。
法然は主題としてはいませんが、浄土教とは何かというところから論を始めているので、法然も含めて浄土教全体の理解を深めることができます。
本書の特色は、逐一、原文・現代語訳を示して、詳細に解説したうえで、論を進めていくことです。
個人的には、初めて読んだとき、竹村先生の真摯な学問姿勢が窺えて、大変感動したのを覚えています。
基礎を学びたいけど、原文にもきちんと触れたいという方には、うってつけだけと思います。
また、法然や親鸞の著作などの有名な浄土教文献の原文(書き下しや現代語訳など含む)に挑戦されたい方は、お勧めの書を別記事で詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
記事はこちらです↓
本記事はここまでです。
ではまたほかの記事でお会いしましょう!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!
本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!
また、いいねの数が大変励みになります。
本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!
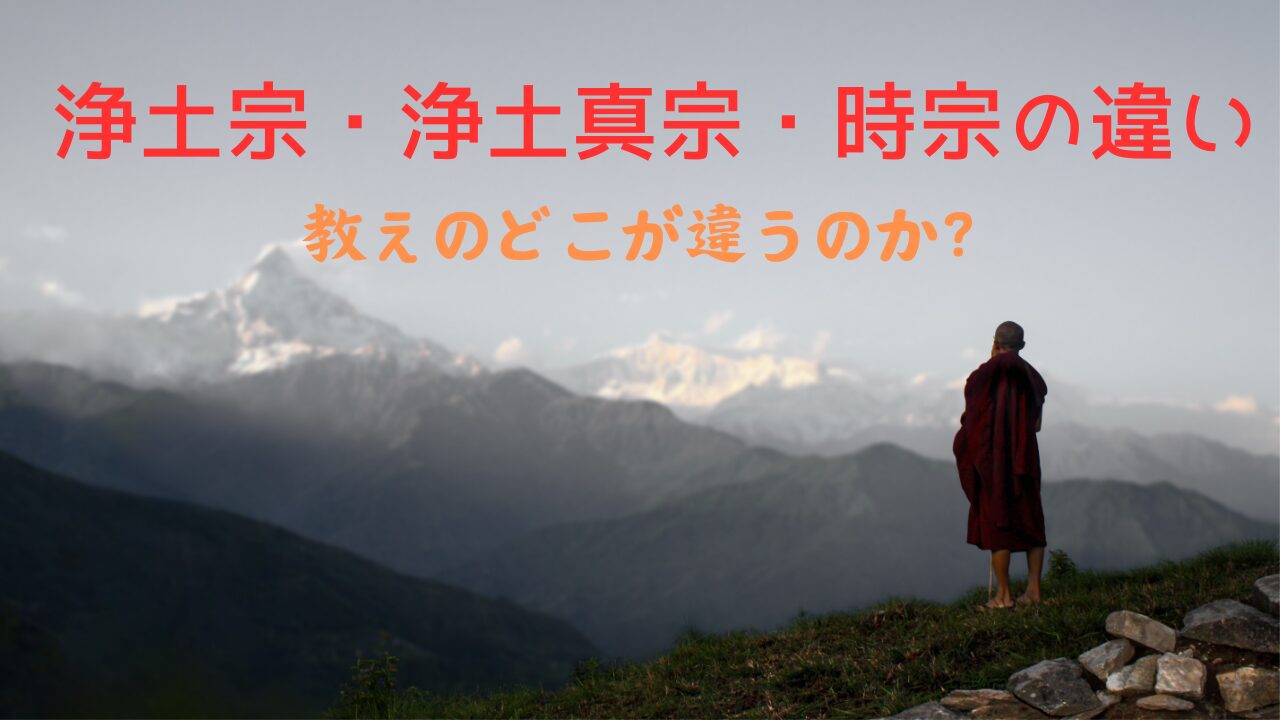





コメント