こんにちは!
学問ボウズです。
本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!
本ブログを読んで、様々な観点から浄土教について触れてこられた皆様の中には、「ぜひ自分で、浄土教関連の原典を読んでみたい」と思った方もいらっしゃると思います。
そこで本記事では、原典にトライする際に有用な書籍を全般的に紹介します。
具体的には、
「浄土三部経」(『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』)
源信『往生要集』
法然の著作
親鸞の著作
一遍の著作
の順番でいきます。
原典といっても、もとは漢文や古文で書かれていますので、研究者であっても読むのが大変です。
手っ取り早いのは、現代語訳から始めることです。
今回紹介する中には、原文と現代語訳や注釈(解説)が全て示されている、有用な書もあります。
こういう全てセットになった書が、一番使いやすいですよね。
今回は、なるべくこれ系統の本を紹介していきます。
もし、原文と現代語訳がセットになった書がない場合は、それぞれが載っている書を紹介します。
ちなみに、研究者は、厳密に原典に当たる必要がありますので、
経典なら『大正新脩大蔵経』『卍続蔵経』、
浄土宗系の文献なら『浄土宗全書』、
源信の著作なら『恵心僧都全集』、
法然の著作なら『昭和新修法然上人全集』
などというように、厳密に校訂された原文を載せている書を用います。
しかし、手軽に原典に触れたい場合には、今からお示しするものを使っていただくほうが、何倍も効率が良いです。
以下に記す情報を、ぜひ皆様が手軽に原典に触れる際の参考にしていただければと思います!
「浄土三部経」の原文・現代語訳
浄土宗の立場からの現代語訳
まず、「浄土三部経」関連のお勧め書から見ていきましょう。
まず前提知識として、『無量寿経』『阿弥陀経』はサンスクリット語の原典と、そこから漢文に訳したもの(漢訳)が残っています。
『観無量寿経』のサンスクリット語原典は残っていません。
「浄土三部経」には、現在のところ、原文と訳がセットになった書で、入手しやすいものはあまりありません。
そのため、現代語訳を中心に紹介していき、最後に原文が載っている書を紹介します。
基本的に今出ている訳書は、漢訳からの現代語訳です。
ここで注意すべきは、「浄土三部経」の訳し方は、浄土宗と浄土真宗という二つの宗派によって異なるということです。
宗派によって、伝統的にどう読んできたかが異なるので、現代に訳すときもいくつか相違点があるのです。
もっとも個人的には、そういうところにまで細かくこだわるのは、研究をする立場の人たちだけで良いと思います。
全体としては、それほど大きな違いはありませんし、まずは手に取り、触れてみることが大事です。
あまり気にせずに、手軽に入手できる訳書からスタートするのが良いというのが、私の思いです。
しかし、読者の皆様の中には、「できれば気にしておきたいな」という方や、「家が~宗なので、一応そっちに合わせておきたい」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですので、念のため、浄土宗と浄土真宗に分けて、順番に訳書を紹介していくことにします。
ではまず、浄土宗の立場からの訳を見ていきましょう。
お勧め本は以下です。
・浄土宗総合研究所編『浄土三部経 現代語訳』(浄土宗、2011年)
浄土宗総合研究所という、浄土宗の第一級の研究者の先生を集めた研究所があります。
その研究所に所属する多くの先生たちを動員して、「浄土三部経」を訳したのが、本書です。
(原文は付いていません。)
経典の直訳だけでは分かりにくい箇所については、括弧内で補ったり、詳しい註を付すなど、分かりやすくするために種々に工夫されています。
聞いた話では、「僧侶の方はもちろん、一般の方にも読んでいただけるように一生懸命作った」ということです。
薄めで持ち運びもしやすいので、そうした点でもポイントが高いです。
ぜひ手に取ってみていただければと思います。
浄土真宗の立場からの現代語訳(原文付き)
次に、浄土真宗の立場からの訳です。
・浄土真宗本願寺派総合研究所編『浄土三部経 原文・現代語訳・解説』(本願寺出版社、2013年)
(安易になぞらえると怒られるかもしれませんが、)さきほどの浄土宗総合研究所の浄土真宗バージョンともいうべき、浄土真宗本願寺派総合研究所の先生方が作成した訳書です。
訳だけではなく、原文(書き下し)も載せているのが、ポイント高いです。
原文と訳を合わせて読むことで、いっそう理解が深まります。
その他の現代語訳
また、別の訳も紹介しておきます。
・大角修訳・解説『全文現代語訳 浄土三部経』(角川ソフィア文庫、KADOKAWA、2018年)
大角先生は、仏典翻訳家・仏教評論家として、研究書はもちろん、一般向けの本を執筆するなど、仏教に関する多彩な活動をしている方です。
近年、数々の経典を精力的に現代語訳しておられます。
まさに仏典翻訳家というにふさわしいお方です。
本書もその一環です。
さきほどの浄土宗総合研究所や浄土真宗本願寺派総合研究所の訳は、宗派としての解釈を大事にして、宗派の訳として矛盾がないよう、きっちり訳したものです。
これらに対して大角先生は、仏典翻訳家らしく、読みやすさやリズムに焦点を当てて、華麗に訳しておられます。
個人的には、大角先生は、4世紀末頃に彗星の如く現れ、数々の経典を流麗な漢文に訳し、中国仏教の発展の基礎を築いたことで知られる、鳩摩羅什に重なって見えます。
読みやすく、読んでいて楽しいという点では、この書が一番だと思っています。
「日本の浄土教と文化」に関するコラム(合計18編)や、「浄土教の小事典」も付していますので、浄土教全般の入門書としても有用です。
原文(漢文・書き下しの両方)・サンスクリット原典からの現代語訳
もし、「訳だけでは物足りたい。原文(漢文や書き下し)が読みたい」という方や、「漢訳からの訳だけでは満足できない。サンスクリット原典からの訳が読みたい」がおられたら、以下の岩波文庫がお勧めです。
・中村元・紀野一義・早島鏡正『浄土三部経 上 無量寿経』(岩波文庫 青 306-1、岩波書店、1990年)
・中村元・紀野一義・早島鏡正『浄土三部経 下 観無量寿経・阿弥陀経』(岩波文庫 青 306-2、岩波書店、1990年)
「浄土三部経」の漢訳とその読み下しと、『無量寿経』『阿弥陀経』のサンスクリット原典からの訳が載っています。
少し古いですが、有名な中村元先生をはじめ、当時の第一級の仏教学者のお仕事です。
サンスクリット語で書かれた原典からの翻訳も載せていますので、漢訳と比べることもできます。
ちなみに、サンスクリット→漢訳の段階で結構変わっていますので、比べながら読むと面白いですよ。
(上に『無量寿経』、下に『観無量寿経』『阿弥陀経』をおさめています。)
以上、4種の書を紹介してきました。
最後の岩波文庫は、サンスクリット原典からの訳や、原文にもしっかり触れたい方向けの、少しマニアックな書かもしれません。
まずは浄土宗・浄土真宗の研究所や、大角先生などによる漢訳からの訳で、読みやすいものにトライしてみるのが一番良いと思います。
それぞれに個性や長所がありますので、ぜひ御自身にあったものをセレクトしていただければと思います!
源信『往生要集』の原文・現代語訳
現代語訳
次に、平安中期の源信(942~1017)『往生要集』の訳です。
源信『往生要集』は、985年に撰述され、日本浄土教の礎となった書物です。
日本の浄土教を研究する上では、深く読んでおくべき文献です。
『往生要集』は十章にわたり、分量が大変多く、難解な箇所も多くあります。
そのため、訳すのはとても大変なのですが、近年梯先生が完訳をしてくださいました。
・梯信暁訳注『新訳往生要集 付詳註・索引』上下(法藏館、2017年)
『往生要集』自体が長いので、二冊にわたっていますが、それほど分厚くもなく、軽く持ち運びもしやすいです。
何より、梯先生の訳が全体的に分かりやすいのと、注が詳しいのが、大変魅力的です。
(原文は付いていません。)
『往生要集』の訳は、過去に石田瑞麿先生が出されています(『往生要集1 日本浄土教の夜明け』[平凡社、1963年]、『往生要集2 日本浄土教の夜明け』[平凡社、1964年])。
しかし、現在は入手しにくく、かつ全体的に難しい訳となっています(こちらにも原文は付いていません)。
梯先生はなるべく平易な言葉を使って、丁寧に訳してくださっていますので、大変読みやすいです。
原文
もし原文を見てみたいという方がおられたら、以下の岩波文庫をお使いください。
原文(書き下し)が載っています。
・石田瑞麿編『往生要集』上下(岩波文庫 青 316-2、岩波書店、1992年)
ただし、やはり『往生要集』は原文だけでは難しいので、現代語訳からスタートするのがよいと思います。
法然関係の文献の原文・現代語訳
法然『選択本願念仏集』の現代語訳
浄土宗の立場からの訳
では、法然(1133~1212)関連の文献に移りましょう。
まず、法然の主著『選択本願念仏集』についてです。
これについても、さきの「浄土三部経」と同様に、大きく浄土宗と浄土真宗の二種の訳があります。
それほど違いはないのですが、一応、分けて示しておきます。
まず、浄土宗の先生による訳です。
・法然著、石上善應訳・注・解説『選択本願念仏集』(ちくま学芸文庫 [ホ14-1]、筑摩書房、2010年)
石上先生は大正大学名誉教授、前淑徳短期大学学長であり、仏教界ではとても有名な先生です。
本書では、『選択本願念仏集』の訳に加えて、註や解説も付してくださっており、その点でも有用です(原文は付いていません)。
何より、文庫サイズで手軽に読めるのがポイント高いです。
浄土真宗の立場からの訳(原文付き)
次に、浄土真宗の先生のによる訳・解説です。
・浅井成海『選択本願念仏集』(聖典セミナー、本願寺出版社、2017年)
浅井先生は、龍谷大学名誉教授であり、親鸞を中心に、広く日本の浄土教研究において大きな業績をあげられた先生です。
本書は少し分厚いですが、原文・現代語訳・解説(講読)の構成となっているので、原文や解説と照らし合わせて読めるのが良い点です。
何より、浅井先生の解説が毎度詳細なので、とても勉強になり、理解が進みます。
その他の訳(原文付き)
最後に、宗教学者として有名な阿満利麿先生の訳書を挙げておきます。
これは、浄土宗や浄土真宗などの、どの宗派に基づくというよりも、客観的に、素直に原文に向き合って作られた訳です。
・阿満利麿訳・解説『選択本願念仏集 法然の教え』(角川ソフィア文庫351、角川学芸出版、2007年)
まず、『選択本願念仏集』の文章を少しずつ分けて、現代語訳→解説となっています。
この訳と逐一の解説がの最初から最後まで終わった後、今度は原文(書き下し)が最初から最後まで一気に続くという構成になっています。
そのため、現代語訳で内容がざっと頭に入った後に、改めて原文(書き下し)に当たり、自分で原文を味わえます。
個人的には、逐一原文と訳を対照させたほうがいいような気もしますが、この構成は、これはこれで便利です。
訳も分かりやすく、私の周囲でも評判が良いです。
以上のように、『選択本願念仏集』の訳だけでいっても、色々な個性や特色のある書が並んでいます。
ぜひ、御自身に一番合うものを見つけていただければと思います!
法然『一百四十五箇条問答』の現代語訳(原文付き)
次に御紹介するのは、『一百四十五箇条問答』の訳です。
『一百四十五箇条問答』とは、法然が行った問答を記録したものです。
内容も豊富であり、また内容も興味深いので、法然研究においては有名な文献です。
『一百四十五箇条問答』についても、(さきほども紹介した)石上善應先生が訳してくださっています。
・石上善應『一百四十五箇条問答 法然が教えるはじめての仏教』(ちくま学芸文庫 ホ 14-2、筑摩書房、2017年)
『一百四十五箇条問答』の訳としては、これが唯一の書ですし、訳も分かりやすいので、一読の価値ありです。
原文と訳が交互に示されているので、対照させながら読めます。
その他の法語の現代語訳(原文付き)
法然は『選択本願念仏集』以外の書を、自ら撰述してはいません。
しかし、法然は数々の法語を残しており、それが弟子によってまとめられています。
代表的なものを挙げると、『念仏大意』『浄土宗略抄』『九条殿下の北政所へ進ずる御返事』『鎌倉の二位の禅尼へ進ずる御返事』などです。
こうした法語からは、当時の人々に対して、法然が直接口で、もしくは手紙で伝えた教えを知ることができます。
いずれも相手を慮りつつ、教えのエッセンスを示すものであり、とても味わい深いです。
さきほど紹介した、『一百四十五箇条問答』もその一例です。
『一百四十五箇条問答』以外の法語についても、浄土宗総合研究所の先生方が、近年訳をしてくださいました。
以下の計四巻です。
・浄土宗総合研究所編『法然上人のご法語 1消息編』(文庫版、浄土宗出版、2021年)
・浄土宗総合研究所編『法然上人のご法語 2法語類編』(文庫版、浄土宗出版、2021年)
・浄土宗総合研究所編『法然上人のご法語 3対話編』(文庫版、浄土宗出版、2022年)
・浄土宗総合研究所編『法然上人のご法語 4伝語・制誡編』(文庫版、浄土宗出版、2022年)
いずれも文庫の形になっていますので、手軽に読めます。
また、原文と現代語訳が交互に示されていますので、原文と照らし合わせながら読めます。
そういう点でも魅力的で、お勧めです!
法然の伝記(『法然上人行状絵図』)の原文・現代語訳・絵
現代語訳
法然の一生を記した伝記として、有名な『法然上人行状絵図』があります。
全部で48巻ありますので、『四十八巻伝』ともいいます。
また、天皇の仰せによって撰述されたので、『勅修御伝』ともいいます。
『法然上人行状絵図』は大変膨大なもので、法然や弟子たちの生きざまが詳しく描かれていて、とても興味深いです。
やはり誰かのことを知る際には、言ったことだけではなく、その人の人生やエピソードも知るべきだと思います。
そうした意味でいえば、『法然上人行状絵図』は、法然を深く学ぶ上で、必読の書です。
ではまず、現代語訳から紹介します。
膨大な48巻全体を、浄土宗総合研究所の先生方が、10年ほど前に訳してくださいました。
・浄土宗総合研究所編『現代語訳 法然上人行状絵図』(浄土宗、2013年)
原文や絵は付いていませんが、そのかわりに膨大な四十八巻の内容が一冊にまとまっていて、大変有用です。
原文と絵(少々)
もし原文自体を読みたいという方がおられましたら、以下の岩波文庫の上下巻がお勧めです。
・大橋俊雄『法然上人絵伝』上下(岩波文庫 青 340-3、岩波書店、2002年)
本書に原文が全て載っています。
また、一部の絵も入っています(ただし、モノクロ版です)。
本書は原文を読むには便利ですが、原文と簡単な註だけですので、古文に慣れていないと、やはり少し読みづらいです。
最終的に原文に挑戦するにしても、まずはさきほど紹介した『現代語訳 法然上人行状絵図』を読んでみてからのほうが良いと思います。
絵(全体)
ここまで紹介した書は、『法然上人行状絵図』の絵を見るには使えません。
では、じっくり見てみたいという方はどうすればよいのかについても、お示ししておきます。
浄土宗出版による以下の書がお勧めです。
・仏教読本編纂委員会編『ビジュアル法然上人』(浄土宗、2000年)
本書では、法然の生涯を、『法然上人行状絵図』のカラー写真を使いながら解説しています。
48巻全ての絵が載っているわけではないですが、主要なものをカラーで見れるのが、ポイント高いです。
(何より安すぎてびっくりします。)
Amazonや楽天などでは買えないので、浄土宗出版のリンクを貼っておきます。
絵に関心のある方は、ぜひ見てみていただければと思います。
ただし、『ビジュアル法然上人』にも、48巻全ての絵が載っているわけではありません。
もし、絵を全部見たいというすごい方がいらっしゃいましたら、以下の書をお使いください。
・小松茂美・神崎充晴執筆『法然上人絵伝』(続日本絵巻大成 1~3、中央公論社、1981年)
2と3は古本でも売られてないですね…。
1も入手しにくいです…。
図書館などでご覧ください💦
『法然上人行状絵図』については以上です。
最後に、念のために『続日本絵巻大成』という研究者が使うようなレベルの本まで紹介してしまいましたが、ひとまずこれらで、『法然上人行状絵図』に触れる手段は網羅できていると思われます。
親鸞関係の文献の原文・現代語訳
主著『教行信証』の原文・現代語訳
訳(原文付き)
では、親鸞(1173~1262)の著作に移りましょう。
(浄土真宗関連の書は、編纂しているのが本願寺派か大谷派かなどで分かれていますので、どちらの流派でも、同一内容で良書を出している場合は、並べて紹介します。それ以外の場合は、煩雑になるため、今回はそこにはあまりこだわらず、入手しやすく、読みやすいものをピックアップして紹介することとします。)
まず、親鸞の主著『教行信証』については、以下の訳がお勧めです。
・本願寺教学伝道研究所編『顕浄土真実教行証文類』上下(文庫版、本願寺出版社、2011年)
文庫なので、手軽に読めます。
また、右頁に原文(書き下し文)、左頁に現代語訳という構成なので、原文と訳を対比させながら読み進むことができて、有用です。
ちなみに、これは本願寺派(西本願寺)の訳です。
流派の違いにこだわりたい方もいらっしゃるでしょうから、大谷派(東本願寺)の訳も挙げておきます。
・教学研究所編『解読教行信証』上下(真宗大谷派宗務所出版部、2012年~2022年)
この書では、上段に原文を、下段に書き下しを載せていますので、対照させながら読むことができ、大変勉強になります。
この書では、上段に原文を、下段に書き下しを載せていますので、対照させながら読むことができ、大変勉強になります。
前掲の本願寺派の書籍と、まさに甲乙つけがたい、有用な書です。
自分は本願寺派・大谷派のどちらだと、きちんと認識しておられる方は、ぜひ自分の流派の訳を読んでいただくと良いと思います。
他宗派の方など、あまり流派意識がない方は、いずれもお勧めですので、ぜひ手軽に手に取れるほうを選んでいただければと思います。
訳(原文なし)
また、『教行信証』にはこれまで種々の訳が出されています。
色んな訳を比べてみるのも面白いですが、昔のものは入手し難くなっているのが現状です。
しかしそうした中で、近年、真継伸彦先生の現代語訳全集だけは新装版が出されて、俄然入手しやすくなりました。
(原文は付いていません。)
・真継伸彦訳『現代語訳 親鸞全集』1巻「教行信証」上(新装版、法藏館、2023年)
・真継伸彦訳『現代語訳 親鸞全集』2巻「教行信証」下(新装版、法藏館、2023年)
真継先生は、当初は西洋思想の研究に没頭していましたが、25才頃に親鸞の著作に出会い、親鸞にものめり込んだ人です。
研究者というより、文学者として有名ですね。
次節に紹介するように、親鸞の著作全体を訳しておられます。
真継先生は土台が文学者ですので、そうした自身の立場から、訳もかなり工夫しておられます。
いわば本書の訳は真継先生のこだわりの結晶であり、味わい深いです。
その他の著作の原文・現代語訳
訳(原文なし)
親鸞には、主著『教行信証』以外にも、『愚禿鈔』や『尊号真像銘文』などの数多くの著作があります。
いずれも、親鸞の思想を学ぶ上で、大変重要な文献です。
さきほど少し述べたように、こうした『教行信証』以外の親鸞著作についても、真継先生が全体的に訳しておられます。
いずれも真継先生のこだわりが注がれた訳です。
親鸞の文章はもちろん、真継先生の訳に引き込まれる書です。
・真継伸彦訳『現代語訳 親鸞全集』3巻「宗義・註釈」(新装版、法藏館、2023年)
・真継伸彦訳『現代語訳 親鸞全集』4巻「和讃・書簡」(新装版、法藏館、2023年)
・真継伸彦『現代語訳 親鸞全集』5巻「言行・伝記」(新装版、法藏館、2023年)
ちなみに、上掲の全5巻はまとめ買いもできるようです↓
原文
ただし、前掲の真継先生の全集には原文が付いていません。
もし原文に触れたい方は、以下の書を参照ください。
・聖教編纂室編『真宗聖典』(大判、第ニ版、真宗大谷派 東本願寺出版部、2024年)
親鸞の伝記の現代語訳(原文・絵付き)
親鸞の生涯を表した伝記として有名なのは、『本願寺聖人親鸞伝絵』(略して『親鸞伝絵』)という絵巻物です。
これは、親鸞の曾孫に当たる覚如(1271~1351)が制作したものです。
『本願寺聖人親鸞伝絵』では、親鸞の生涯の主要な場面が、文章と絵で交互に表されています。
『本願寺聖人親鸞伝絵』に触れるためのお勧めの書は、以下です。
・沙加戸弘『はじめてふれる親鸞聖人伝絵(御伝鈔・御絵伝)』(東本願寺出版、2020年)
この書では、『本願寺聖人親鸞伝絵』の順に従い、本文と絵を交互に掲載して、絵ごとに詳細な解説を、本文ごとに現代語訳を付しています。
担当されたのは、大谷大学名誉教授で、仏教文学がご専門の沙加戸先生です。
訳も読みやすいですし、何より『本願寺聖人親鸞伝絵』の絵が丸々おさめられていますので、めくるだけで楽しいです。
大変お勧めです。
一遍関係の文献
一遍の法語の現代語訳・原文
訳(原文付き)
最後に、一遍(1239~1289)関連の書です。
一遍は「すべてを捨てる」ということを大切にした僧侶ですので、著作を残してはいません。
しかし、口で人々に直接伝えた、法語が残っています。
一遍の研究は法然や親鸞に比べて少なく、訳もあまり多くありません。
現在入手しやすく、かつ質の高い、一遍の法語の現代語訳としては、以下の書がお勧めです。
・ 橘俊道・梅谷繁樹訳『一遍上人全集』(新装版、春秋社、2012年)
橘先生と梅谷先生という、有名な一遍研究者のお二人が訳しておられます。
もとは2001年頃に出された訳ですが、近年新装版が出版され、入手しやすくなりました。
一遍の法語(『播州法語集』)に加えて、下に紹介する一遍の伝記(『一遍聖絵』)の訳も入っていますので、これ一冊だけでも通読すれば、一遍のことについてかなり詳しく学ぶことができます。
原文と対照する形で載っていますので、原文と訳を比べながら読むことができるのも長所です。
原文
また、原文だけですが、手軽に手に取れる岩波文庫でも出ています。
まずは上掲の現代語訳付きの書から読み始めたほうがよいと思いますが、原文だけでOKという方向けに、一応あげておきます。
・大橋俊雄校注『一遍上人語録』(岩波文庫 青(33)-321-1、岩波書店、1985年)
一遍の伝記の原文・現代語訳・絵
『一遍聖絵』の訳(原文付き、絵なし)
一遍には、大きく分けて二種の伝記があります。
すなわち、『一遍聖絵』12巻と、『一遍上人縁起絵』10巻です。
いずれも一遍の生涯や教えを知る上で重要です。
特に、前者の『一遍聖絵』12巻は国宝となっています。
博物館などで目にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この二つの主要な伝記については、ありがたいことに、いずれも現代語訳があります。
まず『一遍聖絵』については、前掲の『一遍上人全集』(新装版、春秋社、2012年)に訳が載っています(絵は入っていません)。
『一遍上人縁起絵』の訳(原文・絵ともになし)
もう一つの伝記(『一遍上人縁起絵』10巻)については、以下の現代語訳が最近出版されました。
・ 『一遍上人縁起絵』現代語訳研究会編『一遍上人縁起絵全十巻 現代語訳』(法藏館、2022年)
絵や原文は入っていませんが、読みやすく現代語訳されていますし、詳細な語註も付いています。
全10巻の訳ですが、分厚くなく、手軽に持ち運べるサイズ・仕様となっていて、そこも良い点です。
原文
また、『一遍聖絵』の原文については、手軽に手に取れる岩波文庫からも出ています。
現代語訳があったほうが良いと思いますが、一応載せておきます。
・大橋俊雄校注『一遍聖絵』(岩波文庫 青33-321-2、岩波書店、2000年)
『一遍上人縁起絵』については、手軽に原文や絵に触れることができるような書は、現状ありません。
今後の出版を期待しておきたいと思います。
絵(全体)
もし『一遍聖絵』の絵をじっくり見たいという方がおられましたら、入手しにくいですが、以下をお使いください。
・望月信成編集担当『一遍聖絵』(新修日本絵巻物全集11、角川書店、1975年)
図書館などにも置いてあるはずです。
最後に
以上、各文献について、手軽に原文や現代語に触れることができる書籍を御紹介しました。
ベストは、原文・現代語訳・注釈が一冊で読めることですが、全てがそういう本ではありません。
そのため、一つの浄土教文献についても、いくつかの書籍を紹介してきました。
色々紹介しましたが、まずは入手しやすいものを使って、とにかく原文や現代語訳に触れてみるというのが一番です。
いずれの書も、執筆者・訳者の先生が工夫して書かれた、近年の知の遺産です。
ぜひ、読者の皆様それぞれの関心から、手に取っていただければと思います。
もし追加で教えて欲しいことや要望などがございましたら、ぜひコメントや、XのDMなどにてお知らせいただけますと幸いです!
本記事はここまでです。
ではまたほかの記事でお会いしましょう!
最後まで御覧いただき、誠にありがとうございました!!
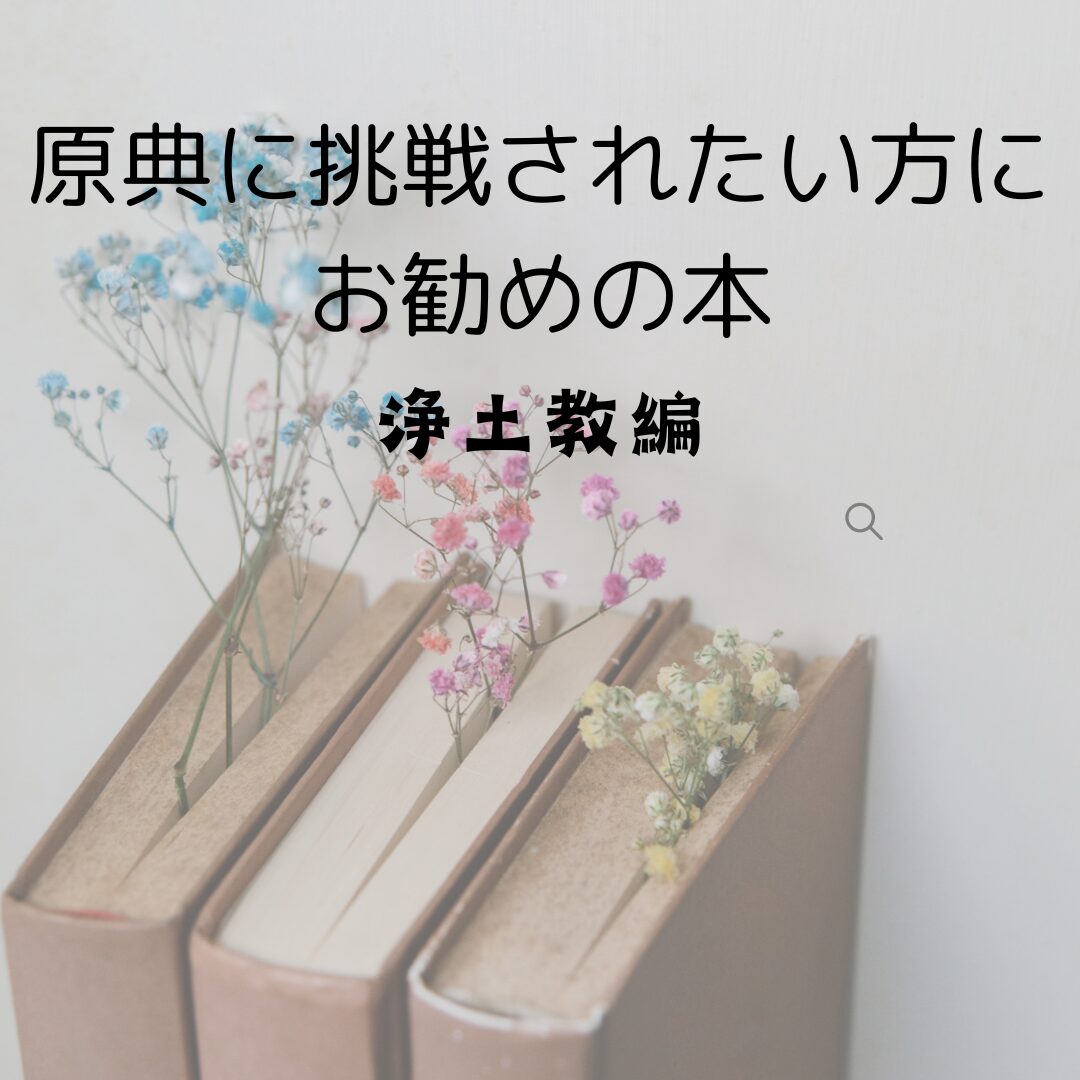




































コメント