こんにちは!
学問ボウズです。
本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!
本記事では、手軽に浄土教を学べるおすすめ本を御紹介します!!
「浄土教について勉強したいけど、どの本を読んだら良いか分からない…」という方はたくさんいらっしゃると思います。
私は研究者として、日々、浄土教文献に触れています。
読むのは原典や研究書がメインですが、解説書・入門書にも、過去から最新のものに至るまで、必ず目を通すようにしています。
(僧侶・研究者として当然のことですので、あえて言うまでもないですが…。)
そうした中で、「この本良いな、周りにお勧めしたいな」という解説書・入門書に出会うことがあります。
今回はぜひ、それらのおすすめ本をまとめてお伝えしたいと思います。
基本的に、私の独断と偏見によりますが、なるべく知人などにも聞いて、色々な人の意見も踏まえつつ選びました。
また、内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなど、諸々の点に配慮しました。
少なくとも私は、自信をもってお勧めできる、有用な書だと思っています。
浄土教を学んでみたいというお気持ちのある方は、ぜひ手に取ってみていただければと思います。
①平岡聡『浄土思想入門 古代インドから現代日本まで』
①は、有名な仏教学者の平岡先生の御著書、『浄土思想入門 古代インドから現代日本まで』(角川選書608、KADOKAWA、2018年)です。
平岡先生は、京都文教大学教授・京都文教大学学長などを歴任された学者の先生です。
平岡先生は、近年、日本仏教関連の解説書を連続的に執筆しておられます。
いずれも分かりやすく、内容も豊富で、とても質の高い本です。
その精力的なご執筆ぶりに、畏れを抱くほどです…。
『浄土思想入門』(以下、紹介する本を本書と呼びます)では、浄土教の展開について、コンパクトな一冊でまとめています。
目次は以下の通りです。
序 章 現代社会における浄土教の意義
(一)現代とはいかなる社会か
(二)現代社会を生き抜くために──物語の必要性
第一章 インド仏教史
(一)初期仏教からアビダルマ仏教へ
(二)大乗仏教の出現
第二章 浄土教の誕生
(一)浄土教前史
(二)浄土経典──浄土三部経と般舟三昧経
第三章 インドと中国における浄土教の理解
(一)インドの浄土教家──龍樹・世親
(二)中国の浄土教家──曇鸞・道綽・善導
第四章 鎌倉時代までの日本仏教
(一)通史
(二)浄土教の展開
第五章 法然の浄土教
(一)生涯と思想
(二)法然門下──聖光・隆寛・証空
第六章 親鸞の浄土教
(一)生涯と思想
(二)親鸞の継承者──覚如・蓮如
第七章 一遍の浄土教
(一)生涯と思想
(二)一遍と法然・親鸞との比較
第八章 近代以降の浄土教家
(一)浄土宗系──山崎弁栄・椎尾弁匡
(二)浄土真宗系──清沢満之・曽我量深・金子大栄
終 章 浄土教が浄土教であるために
このように、インドに遡り、インド→中国→日本で、浄土教がどのように展開したのかを一冊でまとめています。
特に、法然をターニングポイントとして、「法然以前・以後」で浄土教がどう変わったのかについて明確に整理していますので、浄土教の展開の歴史がよく分かります。
古代インド・中国における浄土教から近代まで、スケールの大きな内容を分かりやすく論じている、大変すぐれた書だと思います。
平岡先生には、『浄土思想史講義』という書もあり、それも良書なのですが、初学者には少し難しい内容となっています。
『浄土思想史講義』で触れた内容について、さらに平易に、入門書として書いたのがこちらの本です。
難易度は低めですので、浄土教について、まだあまり詳しくないという方は、ぜひ『浄土思想入門』から始めてみていただければと思います。
一応、『浄土思想史講義』のリンクも貼っておきます!
②岩田文昭『浄土思想 釈尊から法然、現代へ』
②は、宗教学者の岩田文昭先生の御著書『浄土思想 釈尊から法然、現代へ』(中公新書2765、中央公論新社、2023年)です。
岩田先生は、生粋の浄土教自体の専門家ではありません。
もともとはフランス哲学がご専門で、その分野で大変有名な方です。
最近は浄土教や近代仏教に関心を持っておられ、研究を進めておられます。
言ってみれば、本書はガチガチの専門家ではない著者がつくった本ということですが、だからこそ浄土教について深く調べ、分かりやすくまとめておられます。
詳しい専門家であればあるほど、難しい語を使うなどして、独りよがりに書いてしまうものです。
岩田先生は生粋の専門家ではないからこそ、読み手に寄り添い、平易に書くという、簡単そうで大変難しいことができでいるのだと思われます。
目次は、以下の通りです。
第1章 物語の力と浄土思想
第2章 中国の浄土思想
第3章 平安浄土思想から法然へ
第4章 法然門下の諸思想
第5章 親鸞の浄土観と物語論
第6章 二十世紀の新たな物語
終章 物語は現代に続く
ちなみに、岩田先生はもう大阪教育大学の名誉教授までなられた大先生なのですが、浄土教の専門家や僧侶の方々に、わざわざ自ら教えを請いに行ったといいます。
そのため、専門外の内容についても落とし込んでいて、正しい内容を分かりやすく書いてらっしゃいます。
その真摯で謙虚な学問姿勢に、頭が下がります。
本書も、難易度は低めです。
個人的には、前掲の平岡先生の本ではあまり論じられなかった、法然(1133~1212)の門下の証空(1177~1247)についてもしっかり言及しておられ、法然門下の教えのどこが違うのかを明確に論じている点が魅力的でした。
また、宗教学者としての著者の真骨頂は、随所で存分に発揮されています。
それが、「物語としての浄土教」という、浄土教を物語として捉える試みです。
岩田先生は、こうした分析法をフランス哲学から学びながら、浄土教を物語という新たな観点から考えていこうとされています。
さきほど述べたように、本書は浄土教の入門書として大変有用ですが、それと同時に、岩田先生独自の「浄土教への宗教学的なアプローチ」についても学ぶことができます。
まさに一石二鳥であり、こうした点でも、この書は大変お勧めです。
③大角修『浄土三部経と地獄・極楽の事典 信仰・歴史・文学』
③は、仏教評論家・仏典翻訳家として知られる大角修先生がまとめた、浄土教の事典『浄土三部経と地獄・極楽の事典 信仰・歴史・文学』(春秋社、2013年)です。
本書は、通史を一まとめにする解説書というより、浄土教の各テーマ(経典・阿弥陀仏・時代ごとの浄土教と文化との関わりなど)について詳しくまとめた事典形式の本です。
この点で、前掲の平岡先生や岩田先生の本とはタイプが異なっています。
テーマごとの解説ですので、各内容について深掘りしていて、いずれも興味深いです。
事典と聞くと、大きくて重たく、読む気が失せるようなものに思われるかもしれませんが、分量もそれほど多くなく、ソフトカバーで手軽に読めます。
目次は、以下の通りです。
第1部 浄土三部経を読む―現代語抄訳
(浄土三部経を読む前に 阿弥陀経(一巻)―極楽国土の荘厳 観無量寿経(一巻)―欣求浄土 ほか)
第2部 浄土教の事典
(浄土経典の成立と広まり 浄土三部経の仏・菩薩・場所 浄土教の基礎用語 ほか)
第3部 日本の浄土教・文化史事典
(飛鳥・奈良時代 平安時代 鎌倉時代 ほか)
難易度はやや低めという感じです。
前掲の①や②を学んで通史を学び、浄土教の全体像がざっと頭に入ったうえで、「もう少し各テーマについて詳しく知りたいな」と思った方には、本書がとてもお勧めです。
教理だけではなく、浄土教をめぐる文学や美術などの、いわゆる浄土教文化にもフォーカスしているので、読んでいて様々な観点から浄土教を学ぶことができます。
これ一冊読めば、浄土教にかなり詳しくなれます。
個人的には、特に本書の中で、お盆や徳川家康の黒本尊など、様々な内容をまとめたコラムがとても面白かったので、お勧めです。
④梯信暁『インド・中国・朝鮮・日本 浄土教思想史』
④は、平安時代の浄土教の大家である、梯先生の御著書『インド・中国・朝鮮・日本 浄土教思想史』(法藏館、2012年)です。
インドから日本に至るまでの、浄土教思想の展開(思想史)を、丁寧に辿っています。
目次は、以下の通りです。
1 浄土教経典の思想
2 インドの浄土教論書
3 中国における浄土教教理研究の開始
4 隋唐宋代の浄土教
5 新羅時代の浄土教
6 奈良時代の阿弥陀仏信仰
7 平安初・中期の阿弥陀仏信仰
8 叡山浄土教の展開
9 院政期の浄土教
10 法然とその門下
梯先生は、現在、第一級の浄土教の専門家ですので、本書では、普通の解説書ではあまり触れないような人物や思想にもしっかり言及しています。
個人的には、はじめて読んだとき「これほど多くの人々が、浄土教に関わってきたのか」と、感動を覚えました。
他の概説書(ひいては研究書に至るまで)は往々にして、法然や親鸞やそれに関する人物に焦点を当てますので、それ以外の人物や文献については、どうしても記述が乏しくなります。
前掲の①②などもそういう傾向にあります。
一方、梯先生はこうした状況に問題意識を持ち、「従来あまり光の当たっていなかった人物や思想にも注目する」という立場から、長年日本の浄土教研究を引っ張ってこられました。
だからこそこの本では、一貫して広い視野から、浄土教思想史を描き出すことができているのです。
その該博な知識は、さすがの一言です。
とても真似できません。
様々な人物や文献に触れていますので、全体として、やや難しい印象を受けるかもしれません。
しかし、逆に言えば、浄土教思想史の全体像がよく分かるということです。
難易度は中級レベルですが、それほど分厚いわけでもありませんので、すっきり読み通せると思います。
個人的には、まずは①~③などのやさしい入門書から始めていただき、最終的にはぜひ本書を読んでいただきたいと思います。
もちろん、すでに知識のある方は、一発目から本書を手に取っていただいてOKです!
最後に
以上、4つの書を紹介しました。
いずれにも個性や長所があり、どれが一番良いとかは一概に言えません。
しかし、少なくとも私は、全部買って読んだ結果、どの書に対しても、「読んでよかった。手元に置いておきたい書だ」と感じました。
有名な先生方が丁寧に書かれていますので、当然と言えば当然なのかもしれません。
今回紹介した本で、皆様の浄土教についての関心や学びがいっそう深まれば、これほど嬉しいことはありません!
ぜひ、手にとってみていただければと思います。
本記事はここまでです。
もし追加で教えて欲しいことや要望などがございましたら、ぜひコメントやXでのDMなどにてお知らせいただけますと幸いです!
ではまたほかの記事でお会いしましょう!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!






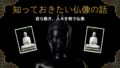
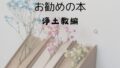
コメント