こんにちは!
学問ボウズです。
本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!
「日本人は無宗教である」というフレーズを、近年よく耳にします。
現に、日本人の方の7割ほどが、「信仰や信心を持っていない」と公言しています(国際比較調査グループISSPの2019年の調査)。
世界の中でみても、日本は人口に占める「無宗教」の割合が非常に高い、珍しい国なのです。
では、これはなぜなのでしょうか?
日本では、古代に仏教が伝来し、室町期には神道が成立し、戦国時代以降はキリスト教も受容し、それら全てが広く国中に広まるなど、かつては宗教大国でした。
また、今でも数多くのお寺や神社、教会が全国にあります。
中でも、お寺は「コンビニより多い」と言われるほど、大変多いです。
なのに、ここからなぜ、「大半が無宗教」という今の状況になったのでしょうか?
また、そもそも日本人は本当に無宗教なのでしょうか?
「7割が無宗教だ」というのは、あくまで国民のアンケート結果から導き出された結論に過ぎません。
単に自分でそう思い込んでいるだけで、客観的に見れば「実は無宗教とはいえない」という可能性もあります。
「日本人は無宗教だ」という発言を聞くことがよくありますが、その際に私はいつも、この2つの大きな問いが残り、しっくりこなさというか、違和感というか、消化不良な印象があります。
みなさんはいかがでしょうか?

個人的に、こういう根本的な問いにすら十分に答えられていない状況で、単に「日本人は無宗教だ」という発言を鵜呑みにして、安易にそういう理解をしてしまうのは危険だと思います。
少し前の安部元首相の事件など、宗教に関連するいたましい事件が、現代には多く起こっています。
私たちは今、改めて、「日本人と無宗教」という問題について、深く考える必要があるでしょう。
今回は、この問題について、近年の研究を踏まえて詳しく解説していきます。
日本人が自らを「無宗教だ」というのには、歴史的な経緯や理由があります。
最後まで読んでいただければ、「なぜ日本人は無宗教なのか?」についてよく理解できます。
その理解を踏まえることで、「今後の日本人は宗教とどのように関わっていくべきか?」を、一人一人がより深く考えることができるでしょう。
それにより、一人一人が宗教についての理解を深め、いわば宗教リテラシーを高めることが、より良い日本の未来に繋がります。
ぜひ最後までお付き合いください。
では、やっていきましょう!
なぜ日本人は自らを「無宗教だ」と言うようになったのか? ―その歴史的経緯―
現代の日本人の特徴
まず、「日本人が自らを無宗教と言うようになったのはなぜか?」というところから、確認していきましょう。
あまり知られていませんが、その背景には、歴史的経緯があります。
現代の日本人の特徴として、「特定の宗教に属するということをかなり嫌がる」ということがあります。
言い換えれば、今の日本人、(もっと正確にいえば)近代以降の日本人には、自分と宗教教団から一線を引こうとする傾向が強いのです。
では、それはなぜなのでしょうか?
一言でいえば、その理由は、宗教に対する意識が偏った形で固まってしまったためです。
日本には、「宗教とは危ないものだ」という、偏った見方が根強いのです。
その背景には、いくつかの歴史的な原因があります。
これについて掘り下げていきましょう。
「宗教=創唱宗教」という理解の浸透
「創唱宗教」と「自然宗教」
歴史的な原因の1つとして、「宗教=創唱宗教」という理解の浸透があると考えられています。
これを聞いただけでは、何のことやらよく分からないと思いますので、順を追って詳しく見ていきましょう。
「宗教=創唱宗教」という理解とはどういうことかを理解するためには、2つの概念を想定しておくことが必要です。
すなわち、「創唱宗教」と「自然宗教」です。
「創唱宗教」とは、特定の人物(開祖)が、特定の教義を唱えて、それを信じる人がいる宗教のことです。
教祖と経典と教団が、三者とも重要な要素として存在し、その三つが全体を形作ることで成り立っているような宗教です。
キリスト教や仏教などの伝統宗教から新興宗教までがその範囲に入ります。
他方、「自然宗教」とは何かというと、いつ、だれによって始められたかもわからない、自然発生的な宗教のことです。
「創唱宗教」とは逆に、特定の教祖も経典も教団も存在しないような宗教です。
祖霊信仰(先祖の恵みに対する信仰)や、アニミズム(あらゆるものに聖なる霊魂が宿るという信仰)などがここに入ります。
もっと身近な例としては、厠神(便所の神)や、道端にあるお稲荷さんの祠などがあります。
こういう例のほうがわかりやすいですね。

普通私たちが考えている「宗教」は、「創唱宗教」です。
なので、「祖霊信仰やアニミズムや厠神なども宗教なのですよ」と言われると、戸惑うかもしれません。
しかし、学術的には、「自然宗教」も「宗教」の一つなのです。
また、「日本人と宗教」という問題を考える上では、このように「宗教」を広く捉えることには重要な意味があります。
これについては、後に詳しく説明しますので、ひとまず次に進みましょう。
ここまで確認してきたように、宗教には、「創唱宗教」と「自然宗教」の2種があります。
では、日本人は「創唱宗教」と「自然宗教」のいずれに属するのでしょうか?
概していえば、「自然宗教」です。
もちろん「創唱宗教」の影響もある程度はみられます。
しかし、概していえば、日本人の信仰のベースは「自然宗教」なのです。
現に、今でも日本の人々は往々にして土地や家の神々を大切にしますが、それに関する教義はあまり発達していないという場合が多いですよね。
こうした土着の神々への素朴な信仰は、広い意味では神道といえるかもしれないし、民間信仰といえるかもしれませんが、要は自然発生的・風習的な宗教であることは事実です。
(これを「宗教」と呼ぶことに違和感があるかもしれませんが、)このような素朴な宗教を受け入れて、その信仰の中で生きているのが日本人という人種なのです。
歴史的にいえば、日本人という農耕民族は、もともと、日本の神々に豊作を祈るという、「自然宗教」の中で生きていました。
そして、時代がくだってはじめて、海外から仏教(6世紀の伝来)や、キリスト教(16世紀の伝来)などの、「創唱宗教」の影響を受けたといえるのです。
しかし、時代ごとに「創唱宗教」が伝来し、その影響を受けたにもかかわらず、日本人には、もとからの「自然宗教」のほうがなじみ深いものでした。
そのため、外来の宗教がしっかりと根付くことはなかったのです。
以上、「宗教には2種があること」、「日本人は立派な自然宗教者である」ということを確認しました。
これが、「日本人と宗教」を学ぶ上での前提知識です。
では、この前提知識を踏まえて、より深く掘り下げていきましょう。
ここまで読んでこられた皆さんは、ここでこう思われませんか?
「ということは日本人ってかなり宗教的な民族なんだ。
じゃあなぜみんな無宗教と言うの?」
と。
本節のポイントはここにあります。
なぜ「自然宗教」には馴染んでいる日本人が、「私は無宗教だ」というのでしょうか?
これは大変重要な問いです。
それにはある理由があります。
すなわち、今の日本人が、「宗教」と聞けば「創唱宗教」を思い浮かべ、「自然宗教」には思い至らないからです。
もっといえば、そういった「宗教」のカテゴリー認識を植え付けられているからです。
この起源は明治時代にあるといわれていますので、具体的に見ていきましょう。
近代の政府による植えつけ
明治政府は、発足当時、新たな国づくりを目指し、ある宗教政策を行いました。
それが、「神道の国教化」です。
ここで目指された「神道」とは、いわゆる神社で神々に祈るような神道(「神社神道」)ではありません。
そのような「神社神道」を全てとりまとめ、皇室崇拝と結び付けた、新たな宗教です。
通称、「国家神道」と呼ばれるものです。
「国家神道」は、結局、当初の明治政府の狙いとは外れて、国教にされることはありませんでした。
しかし、事実上の国教として、近代日本における宗教のトップに君臨していたのです。
奇妙なのは、この「国家神道」が、実質的には国教であったにも関わらず、政府によって、「宗教ではない。宗教を超えたものなのだ」とされていたことです。
そして、このような「事実上の国教に位置する宗教が存在しながら、その宗教が非宗教として位置づけられている」という奇妙な状態が、結局ずっと(敗戦に至るまでずっと)行われたのです。
では、なぜ政府は、国家神道を「非宗教」として位置づけたのでしょうか?
それは、国家神道と信教の自由とが矛盾しないようにするためです。
どういうことかというと、「天皇を崇敬する国家神道は宗教ではなく、日本人みんなのしきたりなのだ」とすることで、国家神道を全宗教者に行きわたらせることができますよね。
「国家神道は非宗教であり、しきたりだ」とすれば、仏教を信仰していようとキリスト教を信仰していようと、すべての日本国民に、神社や学校での国家神道の儀礼に参加することを強制できるのです。
そのため政府は、「国家神道」を全国民に浸透させ、「国家神道」によって国全体を統率するために、他の諸宗教を越える「非宗教」「超宗教」として、「国家神道」を特別視したのです。

【Wikimedia Commonsより(File:Hitlerjugend visit to Yasukuni Shrine State Shintō wreath procession kannushi 1938.png – Wikimedia Commons)2025.2.16】
この「国家神道」をどのように評価すべきかは人によって意見が異なります。
日本を世界戦争に向かわせた最悪のものとする人もいますし、ある程度高く評価する人もいます。
いずれにしても、これについては、ここで論ずることではありません。
「日本人の無宗教」を考察する本記事で重要なのは、「国家神道」を「非宗教」と主張する過程で、その対概念となる「宗教」が明確化されていったことです。
どういうことかというと、近代政府は、「国家神道」を「宗教を超えたもの」と位置付けるために、まず宗教とは何かを規定する必要に迫られたのです。
その際、政府は、「宗教と定義できるのは、キリスト教や仏教など、高度に体系化された教義を持つものだ」と、はっきりと宗教を規定したのです。
さきほど宗教の2種を確認した皆さんは、ここでいう宗教が、「創唱宗教」を指すことがお分かりになるでしょう。
つまり、当時の政府は、宗教として「創唱宗教」だけを想定するという、狭い規定をしてしまったのです。
またそれにとどまらず、政府は、それまで日本に浸透していた、土着の神々への崇拝や民間信仰などに対して、「これは宗教ではない」と一掃したのです。
すなわち、日本にあった「自然宗教」が、この時排除されてしまったのです。
こうした政策も、全ては「国家神道」を他の宗教を超えた頂点に位置づけるためでした。
その賛否はどうあれ、いずれにしても、このように近代において、「自然宗教」が「宗教」という枠組みから排除され、「宗教は創唱宗教だ」というように、狭くガッチリと宗教の定義が行われてしまったのです。
そのため、これ以降、日本人は主に「宗教」という呼称で、「創始者の名前が明らかであり、組織化された教団があるもの」という理解をするようになりました。
すなわち、「宗教」として、「創唱宗教」以外のものが意識にのぼりにくくなったのです。
もっといえば、意識的にせよ無意識的にせよ、「自然宗教」の信仰の中で生きていても、そのことを「宗教」という言葉で表現することができなくなったということです。
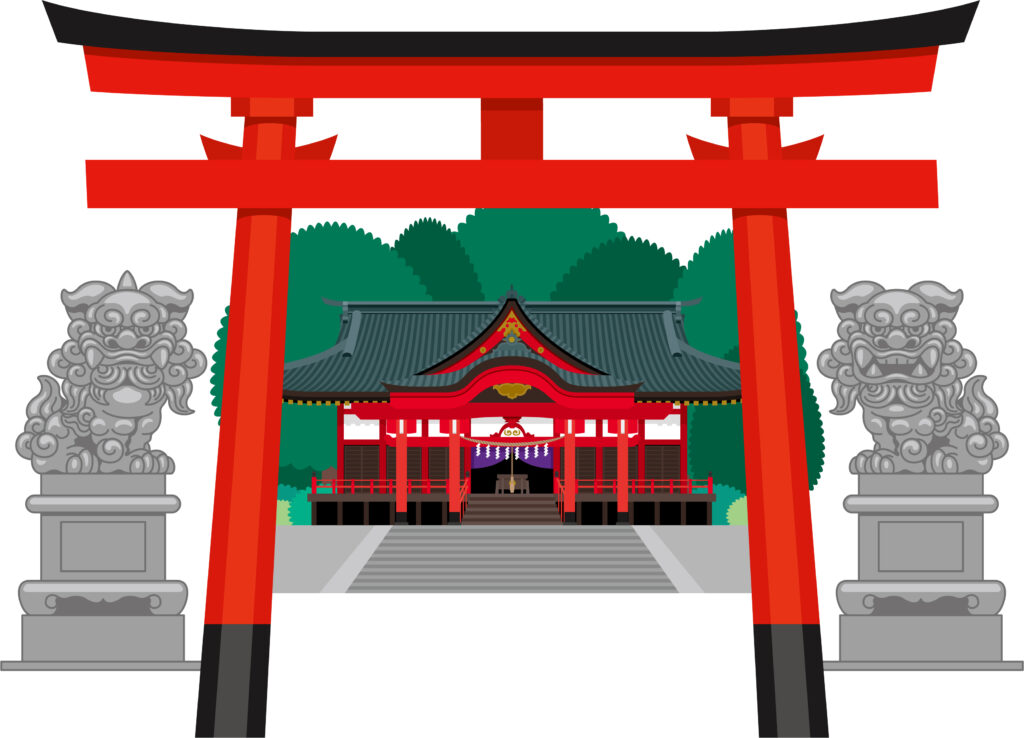
こうして、近代を転換点として、それ以降の日本人は、「本当は創唱宗教よりも自然宗教のほうになじみがあるのに、それは宗教ではないと考える」という、いびつな状況に陥ってしまいました。
日本人としては、根っこの部分で「自然宗教」のほうに馴染みがあるわけですから、今の日本人は概して、強い「創唱宗教」に出会うと、何か戸惑ってしまい、「自分はこの宗教にはなじめない」と考えてしまいます。
しかし、根っこの部分で馴染みがある「自然宗教」については、宗教とは見なしていません。
そのため、今の日本人は、往々にして、「あなたの信仰する宗教は何?」と聞かれると、「私は無宗教です」と言うしかないのです。
以上が、日本人の大半が自らを無宗教とする、第一の理由です。
もう一つ重要な理由がありますので、次節で説明したいと思います。
「宗教=ネガティブなもの」という理解の浸透
第二は、「宗教=ネガティブなもの」とする理解の浸透です。
今の日本人には、この理解がかなり根強くあります。
そのルーツを探ってみると、古くは一向一揆など、戦国時代にまでさかのぼることができるでしょう。
しかし、一番わかりやすいのは、そして一番影響が大きかったのは、まだ記憶に新しい、オウム真理教の引き起こした事件だといえます。

オウム真理教事件では、新興宗教の暴走により、多くの人が被害に遭いました。
それにより、「宗教は怖い、危ない」というイメージが、多くの人々に浸透していったのです。
また、最近の、統一教会が絡んだ安倍元首相への襲撃事件も、それに拍車をかけたといえるでしょう。
オウム真理教などの新興宗教も、「教祖―教理―教団」という3つの要素で成り立つ限り、一つの「創唱宗教」だといえます。
そのため、新興宗教が危ないというイメージは、「創唱宗教が危ない」という認識に繋がります。
結果として、今の日本には、仏教であれ、キリスト教であれ、新興宗教であれ、とにかく「創唱宗教」から距離をとろうとする人がいっそう増えているのです。

先ほど述べたように、近代以降の日本人は「宗教=創唱宗教」という理解を植え付けられているわけです。
なので、「宗教は危ない。距離をとるべき」と考えている人が、もう「私は宗教者ではありません。無宗教です」と言うようになるのは、ある意味当然の流れです。
ちなみに、このような考え方は、私も分かります。
私は僧侶ですし、浄土教を信仰していますので、「私は無宗教です」などとは絶対に言いませんし、言えませんが、「宗教は危ない」、より正確には「危ない宗教もある」というイメージを持っています。
なので、もし僧侶でなく、浄土教を信仰していなければ(そういう世界線にいるのなら)、たぶん自分は、多くの人と同じように、「私は無宗教です」と言うのだろうと思っています。
というか、何らかのグループで「私は無宗教です」と言って、周囲から引かれるのが怖いですね…。
別の観点からいえば、「周囲から引かれてしまうのではないか」と考えるほど、今の日本には、「宗教は危ないもの」というイメージが根付いているということでもありますね。
色々と述べてきましたが、要は、現代の日本人は往々にして、宗教の危なさを深く認識しています。
そのため、「危ない創唱宗教なんかに入ってはいません」ということを伝えるために、「私は無宗教です」と、(過剰なほど熱を込めて)断言しているのです。
さて、ここまで読んでいただいた皆さまには、「なぜ日本人が無宗教を主張するのか」について、その主要な2つの理由をお分かりいただけたと思います。
ここまでの内容全体を踏まえ、まとめておきましょう。
◎現代の人たちは、「創唱宗教」よりも「自然宗教」のほうになじみがあるのに、それは宗教ではないと認識している(近代に「国家神道」が出てきた関係で、そういう認識を植え付けられることになった)。
これが第一の理由である。
◎さらに、近年、新興宗教の悲惨な事件などを通して、多くの日本人が、「創唱宗教は危ない」という認識を持っている。
だからこそ、宗教と線を引くために、「無宗教だ」と主張するようになった。
これが、第二の理由である。
ではここから、もう少し踏み込んで考えていきたいと思います。
「本当に日本人は無宗教なのか?」という問題です。
今まで述べてきたように、日本人が自らを「無宗教だ」というときの「宗教」とは、総じて何らかの実定の宗教(「創唱宗教」)を指します。
「日本人は宗教を怖いものと見なす」というのは、より正確にいえば、「日本人は、集団化・確立した宗教やその教団を怖いものと捉えて、線引きしようとしている」ということです。
しかし、本当に「宗教=創唱宗教」なのでしょうか?
繰り返しになりますが、これは明治時代に作られた考え方に過ぎません。
その理解は一旦置いておいて、ニュートラルになって、掘り下げて考えてみる必要があるでしょう。
「宗教とは何か?」「日本人は無宗教なのか?」再考
「自然宗教」としての宗教理解
結論からいえば、少なくとも今の日本人は無宗教だと言い切れません。
さきほどから処々で述べているように、宗教を「創唱宗教」と考えるのは狭く偏った理解です。
なので、宗教を再定義して考えるべきです。
宗教には様々な面があり、「宗教とは何か?」について、明確に、万人共通の形で決めることはできません。
研究者ごと、人ごと、地域ごとなど、色々な定義があって良いのです。
というか、そういう広い枠組みで考えないと、宗教という壮大で不可思議なものを捉えることなどできません。
私は、「宗教=創唱宗教」ではなく、「自然宗教」も含めて考えるべきだという立場です。
「自然宗教」という表現だと固く聞こえますので、もう少し馴染みのある言葉で、習俗と言っても良いでしょう。
ここでいう習俗とは、何らかの俗信、迷信、呪術、伝統的な慣習や価値観、社会的な習慣、民間信仰などに至るまで、全てを含むものとイメージしてください。
俗信にせよ、慣習にせよ、価値観にせよ、今自分がいる共同体(諸集団や家族)、ひいては個人に至るまで、その生き方や行動を支え、あるいは逆に制約しているものであれば、全て習俗と見なします。
習俗(自然宗教)が生き方を支える、言い換えれば、習俗に基づいて生きているというのは、これだけ聞いても少しイメージしにくいかもしれません。
しかし、私たちは、何らかの習俗に、かなりの影響を受けています。
自覚的にせよ、無意識にせよ、習俗に基づいて、自分の生き方を決めるというケースは多々あるのです。
まだ納得のいかない方もいらっしゃると思いますので、具体例を挙げてみましょう。
例えば、習俗の代表例として、先ほど挙げた祖先信仰やアニミズム、厠神、お稲荷さんなどがあります。
色々取り上げているときりがないので、祖先信仰を取り上げ、具体的に見ていきたいと思います。
今ではだいぶ違う意見も出されてるようになりましたが、少し前までは、
「結婚するのが普通だ。
それが人としての幸せなのだ」
という考え方が主流でした。
少し前の日本人は、基本的に、
「結婚しなくてはならない。
子孫を残さなくてはならない」
というような意識を持っていたのです。

では、そういう意識はどこから来たのでしょうか?
キリスト教世界でいえば、それは、「神から与えられた命の再生産をするのが義務だから」ということになるでしょうが、日本では、そこまでキリスト教が広く浸透しているわけではありません。
では、「子供を残さなくてはならない」という意識の根底にあるのは何だったのかというと、その人が所属している、社会や共同体の習俗です。
より具体的にいえば、
「結婚して、子孫をのこして、家を継続させ、家を守らないといけない。
そうしなければ、この家のご先祖様に顔向けできない」
というような考え方です。
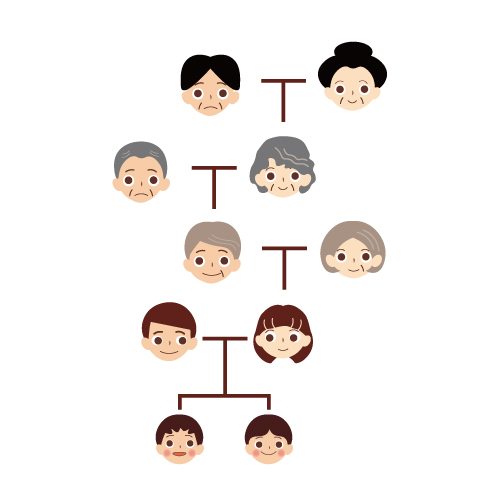
これは、立派なというか、典型的な先祖崇拝(祖先崇拝)です。
こういう先祖崇拝や家の重視というのは、仏教やキリスト教などの、特定の宗教の教えから来ているものではありません。
(もちろん、日本の歴史の中で、お彼岸の行事などのように、仏教と先祖崇拝が自然に結びついたこともありますが、本来は別のものです。)
今挙げた、「結婚して子孫を残して、ご先祖様に恥ずかしくないように生きねば」という考え方のように、「創唱宗教」ではなくても、日本の社会で脈々と伝わり、現代の私たちの生き方に影響する宗教的な価値観というのは確かにあります。
これが、習俗(「自然宗教」)なのです。
また、ある学説によれば、「この他にも、亡き人が草葉の陰から見守っているとする風習や、盆踊りなどの行事、夜這いなどの性的な慣習も、全て習俗に当たる」といいます。

また、「おてんとさまが見ているから悪いことはできない」などというのも、何か特定の「創唱宗教」の厳格な教えではないのに、私たちが漠然と感じている宗教的な考え方だといえます。
これも、昔からある習俗(「自然宗教」)の影響です。
私たちは総じて、こういう習俗(「自然宗教」)は宗教ではないと考えていますよね。
さきほどの結婚の話でいえば、
「この家の血を絶やしてはならない。
ご先祖様に恥ずかしくないようにせねば」
と考える人は、今の若い方々の中にも多くいらっしゃいます。
でも、それを「宗教の教えだ」と考えている人は誰もいないでしょう。
もっといえば、日本人は、このような価値観を当り前のものとして受け入れていることが大半なので、自分の考えが何から来ているかを疑問視すること自体がほとんどないと思われます。
百歩譲って、仮にそうした問いを持ったとしても、
「両親や、祖父母、ひいてはもっと前の世代から伝えられてきた社会的な慣習だ。
伝統的な文化である。
しきたりである」
という認識をするくらいで、「これが宗教だ」とは考えないでしょう。
だからこそ、今の日本人は、「私には宗教がない(無宗教だ)」と、何の疑いもなく、はっきり言うことができるのです。
本節の内容をまとめておきましょう。
◎宗教は、「自然宗教」、すなわち習俗も含めて考えるべきである。
◎現代の日本でも、習俗をよりどころにして生きている人は多い。
では、これを踏まえると、「日本人は無宗教だ」ということは正しいのでしょうか?
もう薄々お分かりになっている方がほとんどだと思いますが、次節で改めてきちんと述べたいと思います。
日本人は本当に無宗教なのか?
ここまでお話してきたように、日本には種々の習俗が根付いており、今の世代すらもそこから大きな影響を受けて生きています。
習俗であれ何であれ、自分以外の何かを拠りどころにし、それによって自分の生き方を決めるということは、宗教と通ずるものです。
「日本人の宗教性」といっても良いでしょう。
先ほどから、「日本人は自然宗教者である」ということを繰り返し述べているように、「宗教=創唱宗教」という狭い宗教理解にこだわらなければ、多くの日本人は立派な宗教者なのです。

【Wikimedia Commonsより(File:2009年、明治神宮で初詣 2.jpg – Wikimedia Commons)】
特定の教団に属すか属さないか、すなわち「創唱宗教」の信者かどうかで考えるだけでは、日本人の宗教性を捉え切ることはとうていできません。
「日本人と宗教」について考えるためには、宗教というものをもう少し広く捉えるべきだということを、ここまで読んでくださった皆様には深く理解していただけたと思います。
本記事では、このような考えのもと、「宗教は、習俗も含めて、個人や共同体の生き方を支え、規定するもの」と考えるという立場を取ってきました。
人間は、生きていく以上、人間関係などはもちろん、老い、病、そして死など、生死において出てくる様々な問題に付き合っていかねばなりません。
そうしたときに、それを乗り越えて生き、そして命が尽きる時を迎えるために、その指針となるものが必要です。
その代表が「創唱宗教」であることは事実ですが、同時に、「自然宗教」もその役割を果たし得る、立派な宗教なのです。
以上の内容を踏まえると、以下のように考えることができるでしょう。
◎少なくとも現段階では、「日本人は無宗教だ」とは言い切れない。
◎私たちは今後、安易に「日本人は無宗教だ」と繰り返すのではなく、「宗教は何か」ということをもう一度考え直し、その上で、「日本人は本当に無宗教なのか」を論じていくべきである。
今後、「日本人と宗教の関係」はどうなるのか?
以上のように、「日本人は今も、実は宗教(「自然宗教」)との関わりの中で生きている」といえます。
多くの日本人が「自然宗教」の影響を受けて生きている以上、「日本は無宗教の国だ」とは一概にいえないでしょう。
ただし、さきほどのまとめで、「少なくとも現段階では無宗教ではない」と書いたように、今後は分かりません。
なぜなら、今後は「自然宗教」すらも消滅してしまう可能性もあるからです。
これについて、最後に踏み込んで見ていきましょう。
宗教離れが叫ばれる近年、段々と仏教やキリスト教などの、「創唱宗教」から離れる日本人が増えています。
耳の痛い話ですが、私も僧侶として、これをひしひしと感じています。
そして、ポイントなのは、平成・令和にかけて、このような「創唱宗教」だけではなく、段々と習俗(「自然宗教」)すらも廃れていることです。
現に、さきほどの結婚に関する価値観を見てみましょう。
この価値観でいえば、ここ数年で、急激に崩壊しています。
「結婚なんてしなくても良い。
結婚するのが幸せだというのは、古い根拠のない考えだ」
と考える方が増えていますよね。
また、結婚だけではなく、先祖をあまり大事にしない方も増加しています。
「先祖からの伝統なんて知らない。
家を絶やしたって良いし、自分の生き方が一番大事だ。」
と考える方が増えているのです。
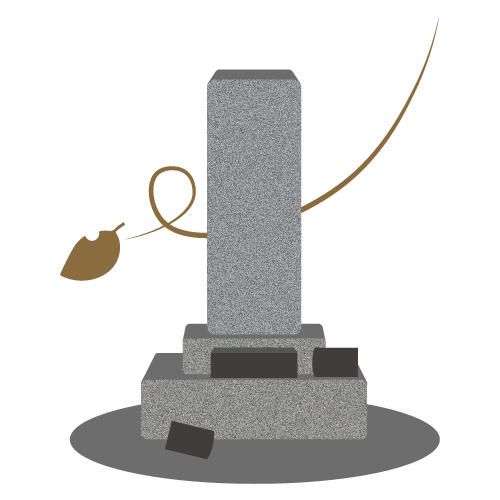
もちろん、今でも、伝統的な考え方を受け継ぎ、
「結婚すべき。
子孫を残すべき。
家を守るべき。
先祖を大切にすべき」
と考えている若い方々は一定数いらっしゃいます。
(特に、お寺の息子さん、娘さんはその傾向が強いですね。)
しかし、10年後にはどうなっているかは、全く読めません。
それくらい、習俗(「自然宗教」)は、ここ数十年のうちに急激に崩壊しているのです。
それが良い悪いということを言いたいわけではありません。
事実としてそうだということです。
今は、「自然宗教」すらも失われつつあるという、「日本人と宗教」の関係性がまた変わる、新たな代に入りつつあります。
ここからまた揺り戻しが起こるのか、
あるいはこのまま「自然宗教」の喪失が進むのか、
その場合、それが吉と出るか凶と出るのか
などについては、現段階では何ともいえません。
いずれにしても、今後私たちは、宗教というものにもう少しアンテナを張って、日本の行く末を見つめていかねばならないと思われます。
本節の内容をまとめておきましょう。
◎少なくとも(この記事を書いている)現段階では、宗教を広く「習俗としての宗教」(「自然宗教」)も含めて定義するのなら、「日本人は無宗教ではない」といえる。
◎しかし最近では、習俗すらも崩壊し、消滅しかけつつあるため、数年後にはどうなっているか分からない。
◎日本人が「創唱宗教」のみではなく、「自然宗教」も含めて無宗教となるのかは、今後の日本次第である。
何ともはっきりしないまとめになりましたが、現段階では、このように言うしかないのです。
今後、「日本人と宗教」がいかなる方向性に行くのか、僧侶として、また一日本人として、目が離せません。
最後に
本記事では、
大半の日本人が「私は無宗教だ」と言うようになったのはなぜか?
そもそも日本人は本当に無宗教なのか?
について、近年の諸研究を踏まえつつ、考察してきました。
私見では、「無宗教と主張する人が多いのが良いか悪いか」は別にして、いずれにしても今は、日本と宗教との関わりにおいて新たな時代だということが重要であると思われます。
先ほども述べたように、近代において宗教が人気を失っていく中でも、なお習俗は残っており、人々の拠りどころとなっていましたが、今はそれも崩壊しつつあるのです。
日本は近代以降、宗教や習俗という過去の遺産を、どんどん失い続けているといえましょう。
僧侶として、私個人の考えを申せば、「自然宗教」にせよ「創唱宗教」にせよ、宗教は人生に拠りどころを与えてくれるものとして、大切だと思います。
「全ての人に絶対必要だ」とまでは言いませんが、今後の日本にもあるべきものだと思います。
もっといえば、私としては、「創唱宗教」すらも崩壊していっている日本ではありますが、逆に、
「創唱宗教がもう少し頑張れたら良いな。
現代の方々と「創唱宗教」との関わりが増えたら良いな」
と思っています。
オウム事件などもありましたが、「創唱宗教」全てが危ないわけではありません。
過去に多くの人たちの心を救ってきた伝統ある教えを、大切に、誠心誠意受け継いでいる教団はたくさんあります。
また今現在、悩める人々に応えようと真摯に活動をしている教団もたくさんあります。
「宗教だからといって、何でもかんでも距離を取ってしまうと大変もったいない」というのが、私個人の率直な思いです。
現代の日本では、「無宗教だ」という方の中にも、熱心にお寺や神社に行き、手を合わせ、すがすがしい気持ちになって帰っておられる人がたくさんおられます。
「お坊さんの話を聞くのが好き!」という方もいるし、「仏像を見るのが趣味です!」という方もいます。
お坊さんの話もあまり聞かないという方でも、観光でお堂に入って仏像を見たときに、何ともいえない厳かさを感じ、心が落ち着いた経験はあるのではないでしょうか。
今の日本でも、「宗教と関わりたい」という方や、宗教によって良い生き方をされている方はたくさんいると思います。

とはいえ、確かに「宗教」というとハードルが高いです。
私は僧侶ですから、胸を張って「宗教者です」と言いますし、むしろそう明言する必要があります。
しかし、そういう環境でない以上、今の日本で「宗教を信じています」とはなかなか言いにくいです。
「無宗教です」と主張する方々の気持ちは、私にも分かります。
本記事で解説したように、私たちが「宗教を信じています」と言いにくいのは、私たちに原因があるというよりも、歴史的な要素が色々あるのです。
そのため、無理してまでも「私は宗教の信仰者です」という必要はありません。
「私は無宗教です」というスタンスのままで良いと思います。
私がこのブログで何度も言っている「世界観」という言葉を使うのも良いかもしれません。
宗教というのは気が進まないのであれば、
「この宗教の、この宗派の世界観がいいなと思っています。
この宗教のうち、この世界観を受け入れています」
というような言い方でも良いと思います。
いずれにしても、このように、「無宗教です」というスタンスのままで良いから、宗教に気軽に触れるということが、もっとしやすくなれば良いなと思っています。

宗教のおどろおどろしさ、ネガティブさ、壁みたいなものが少しずつなくなり、多くの方が気軽に触れることができるような未来の実現に向けて、このブログがその一助になれたら嬉しいです。
参考文献とお勧めの書籍
【参考文献一覧】(年代順)
本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。
いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。
学恩に心より感謝いたします。
◎阿満利麿『日本人はなぜ無宗教なのか』(ちくま新書85、筑摩書房、1996年)
◎島田裕巳『無宗教こそ日本人の宗教である』(角川書店、2009年)
◎島田裕巳『無欲のすすめ 無宗教な日本人の生き方』(角川書店、2010年)
◎島薗進『国家神道と戦前・戦後の日本人 「無宗教」になる前と後』(河合ブックレット39、河合出版、2014年)
◎礫川全次『日本人は本当に無宗教なのか』(平凡社新書924、平凡社、2019年)
◎中村圭志『西洋人の「無神論」日本人の「無宗教」』(ディスカヴァー携書214、ディスカヴァー・トゥエンティワン、2019年)
◎佐藤弘夫『日本人と神』(講談社現代新書2616、講談社、2021年)
◎岡本亮輔『宗教と日本人 葬式仏教からスピリチュアル文化まで』(中公新書2639、中央公論新社、2021年)
◎木村文輝『なんとなく、仏教 無宗教の正体』(大法輪閣、2021年)
◎佐々木馨「日本人は本当に無宗教か」(『日蓮教学研究所紀要』50、2022年)
◎藤原聖子編『日本人無宗教説 その歴史から見えるもの』(筑摩選書255、筑摩書房、2023年)
【お勧めの書籍】
では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。
内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。
◎阿満利麿『日本人はなぜ無宗教なのか』(ちくま新書85、筑摩書房、1996年)
有名な宗教学者の阿満利麿先生が、タイトル通り、「日本人はなぜ無宗教なのか」を徹底的に考察した本です。
本記事で用いた、「自然宗教」と「創唱宗教」という観点から、詳細な分析を行っています。
本記事の解説も、阿満先生の研究に多くを負っています。
新書で、分かりやすく書かれていますので、読みやすいです。
本記事で全体像は分かったが、もう少し学びを深めてみたいという方に、とてもおススメです。
◎礫川全次『日本人は本当に無宗教なのか』(平凡社新書924、平凡社、2019年)
歴史民俗学の研究者である礫川先生の著書です。
この書では、阿満先生の分析とは少し異なっており、習俗に注目したり、日本人が宗教に違和感を持ち出した経緯を探ったりするなど、様々な観点から、新たな興味深い分析を行っています。
本記事の作成をするに当たり、この書からも大変学ばせていただきました。
歴史学・民俗学的な観点から詳細に分析しているので、盆踊りやキリシタン、一向一揆、本居宣長など、具体例も多く出てきて、その意味でも大変興味深く、「日本と宗教」という問題について、楽しく学ぶことができます。
阿満先生の本に合わせて、こちらもおススメしておきます。
本記事はここまでです。
ではまたほかの記事でお会いしましょう!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!
本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!
また、いいねの数が大変励みになります。
本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!



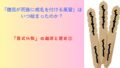

コメント