こんにちは、学問ボウズです!
本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!
「葬式仏教の起源と歴史」を学ぶ記事の、第二弾です。
今回の試みは、3つの記事に分けて、「葬式仏教はいつから、なぜ始まったのか?」を、学んでいこうというものです。
具体的には、3つの風習が、「いつから、なぜ始まったのか?」を考えていきます。
3つの風習とは、以下の3種です。
A「在家者が出家者にお布施をして、出家者に葬儀をしてもらうこと」は、いつから始まったのか。
B「在家者が出家者にお布施をして、死後に戒名を付けてもらうこと」は、いつから始まったのか。
C「在家者が出家者にお布施をして、追善供養をしてもらうこと」は、いつから始まったのか。
Aについては第一弾で解説しましたので、本記事では、このうちのB「在家者が布施をして、出家者(僧侶)に故人の戒名をつけてもらうことは、いつから始まったのか?」を取り上げます。
A、Cについては、それぞれ以下の記事をご覧ください↓
では、前置きはこれくらいにして、Bのテーマについての解説に入っていきましょう!
起源と歴史
前提知識
まず、前提知識の確認をしておきましょう。
戒名とは、本来、「戒を授ける時に与える名」です(後に詳しく述べます)。
しかし今の日本では、死後、亡者に戒名を与える風習が定着しています。
以下、「これはいつからなのか?」について、詳しく見ていきます。
ちなみに、戒名については別記事でも詳しく説明しています。
記事はこちらです↓
本記事は、「葬式仏教の起源と歴史」を探る試みの一環です。
そのため、「葬送儀礼」としての戒名が成立していく過程に焦点を当てて、上掲の記事とは異なる観点も加えながら、改めて解説したいと思います。
では、Bの起源と歴史について、古代インドに遡って、学んでいきましょう。
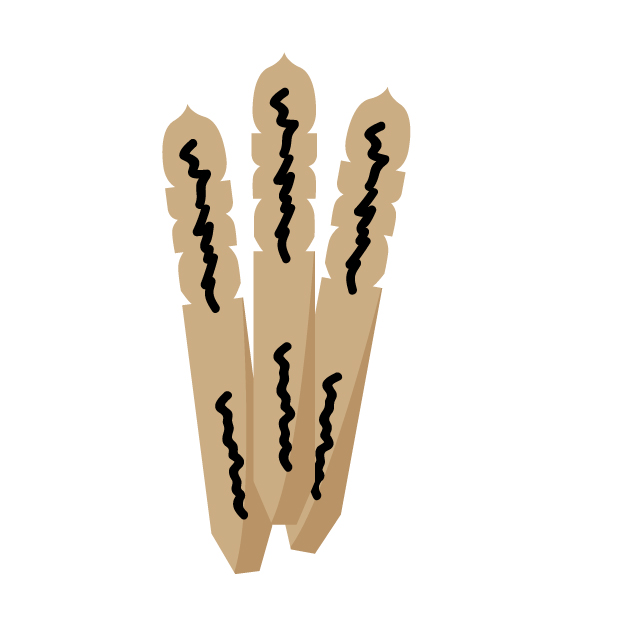
インド
「在家者が僧侶に布施をして、戒名をつけてもらう風習が始まったのは、古代インドからか?」と問われると、答えはノーです。
古代インドは、このような風習からはかけ離れた状況でした。
どういうことかというと、そもそも古代インドでは、「生者に戒を授ける際に、戒名を与える」という習慣すらありませんでした。
僧侶が亡者に戒名を付ける風習以前に、そもそも生者にすら、戒名を与えるという文化が存在しなかったのです。
では、生者に戒名を与える文化が生まれたのはどこかというと、古代中国です。
これについて、次節に詳しく見ていきましょう。
中国
中国では、生者に戒を授ける際に名を付けるという、古代インドとは異なる風習が生まれました。
これがなぜかというと、土着の風習によるためです。
中国では、成人した際に、諱(本名)のほかに、字(通称)を与えるという風習がありました。
ここでポイントになるのは、この風習が戒名にも応用されたことです。
すなわち、「成人になるという一つの段階を経過したときに新たな名を付けるのなら、仏教で戒を受けるという一つの段階を通過したときにも、新たな名を付けるべきだ」と考えられるようになったのです。
こうして、「戒を授かった者が、その際に新たな仏教徒としての名をもらう」ということが行われるようになりました。
しかし、注意すべきは、中国で成立したのは、あくまで「生者に戒名を付ける」という風習までだということです。
中国では、「生きているうちに戒を受けた者に、仏教徒になった証として、生前に戒名を与える」ということのみを行っていたのであり、死後の授与ではありません。
中国では、今の日本のように、「亡者に戒名を与える」という風習は生まれなかったのです。
日本
では、今のような「僧侶が亡者に戒名を与える」という風習はどこで始まったかというと、ここ日本です。
その理由は何なのでしょうか?
それを探るためには、平安時代のある出来事に注目する必要があります。
平安時代には、皇族や貴族が、生きているうちは俗世の生活を謳歌し、死が近づいてはじめて出家し、来世の幸せや悟りを願うという風習が生まれました。
これを「臨終出家」といいます。
臨終間際の駆け込みであるとはいっても、出家するわけですから、当然その際に戒名をもらうことになります。
これは、「臨終出家」と同様に、「臨終戒名」とでも名付けるべき風習です。
例えば、Aについての第一弾の記事でも触れた藻璧門院は、死産ののちに25歳で亡くなった人物です。
彼女がこと切れそうなとき、父の九条道家(1193年~1252年)は、「髪を下ろして戒を受けなさい」と言い、僧侶が戒を授けました。
藻璧門院はただ頷くしかできませんでしたが、無事戒を受け、合掌して命を終えたといいます(藤原定家の日記『明月記』、1233年9月20日条)。
臨終出家・臨終戒名だけでも興味深い風習です。
その上で、本記事で重要なのは、この後さらに、死後にはじめて出家するという「死後出家」という風習まで生まれたことです。
この「死後出家」の場合でも、「出家したのだから」ということで、生きている際の出家や「臨終出家」と同様に、戒名が授けられました。
すなわち、死後における戒名授与(「死後戒名」)という新たなパターンがここで出来上がったのです。
「死後戒名」の例を挙げておきましょう。
例えば、九条兼実(1149年~1207年)の嫡子の九条良通(1167年~1188年)は、22歳の若さで急死してしまいました。
その翌日には、高野山から仏厳という高僧がやって来て、戒を授け、出家させています(九条兼実の日記『玉葉』、1188年2月20日条)。
この他にも、「死後出家」や「死後戒名」の例は、平安時代後期以降の史料に多く見られます。
このような「死後戒名」の風習は、最初は都の上流階級において広まっていただけでしたが、しだいに日本全土に、またあらゆる階層に浸透していきました。
江戸時代初頭にはほぼ定着していたといわれています。

こういうわけで、今の日本では「死後に戒を授け、戒名を与える」というのがスタンダードになっているのです。
「生前の戒名授与」というおおもとの制度・風習は中国から受け継いだといえますが、直接的には平安時代の「死後出家」に端を発する、日本独自の風習だといえましょう。
ちなみに、少し脱線しますが、戒名については、近年、戒名料が問題になっていますよね。
「僧侶に、戒名料(良い戒名を付けるための代金)と称して、よく分からないままにかなりの金額を取られてしまった」と、仏教界への批判の声が上がっているのです。
この問題は現代的な問題かというと、そうではありません。
少なくとも江戸時代には戒名のランク付けが盛んに行われていました。
根が深い問題だといえましょう。
この問題について、もう少し詳しく説明しておきます。
江戸時代には、有名な檀家制度が作られました。
檀家制度とは、国民を家単位で特定の寺院に所属させて(檀家とならせて)、国民全体を統制する仕組みのことです。日本史で習いましたね。
檀家制度が整えば、各お寺がそれぞれの檀家を一定数持つようになります。
その際、本山に一定のお金を納めなければならない末寺は、自分のお寺の檀家をランク付けすることにより、安定した経済的な収益を得ようとしました。
つまり、経済的な貢献度が高い檀家を優遇することで、檀家からより多くお金を払ってもらおうとしたのです。
その顕著な例が、戒名をランク付けし、高ランクの戒名を付ける際に、戒名料をもらうことです。
現に、戒名のランク付けは、檀家制度が確立する享保20年(1735)頃から、盛んに行われるようになっています。
このような戒名のランク付けや戒名料の習慣が、現代の一部の宗派や寺院に伝わっているのですが、本当にこのままで良いかについては、今でも色々な議論があります。
現在進行形で、仏教界における大問題になっているのです。

いずれにしても、戒名については現在進行形で大きな問題があるということですね。
この点に触れておきたく、少し脇道に逸れました。
こうした戒名料の問題や、「現代の私たちは戒名についてどのように考えていけばよいのか?」については、さきほど紹介した別記事で踏み込んで述べていますので、ぜひ合わせてご覧ください!
記事を再掲しておきます↓
本題に戻り、本節の内容をまとめておきましょう。
◎B「在家者が布施をして、出家者に戒名をつけてもらう風習」は、インド・中国で生まれたものではない。
中国に起こったのは、あくまで戒を受けた生者に戒名を授けるというところまでである。
◎その後、日本では、「臨終出家→死後出家」という独自な出家のしかたが平安期に広まる中で、死者に戒名を授ける風習が生まれた。
その後、時代がくだるにつれ、この風習が全体的に浸透していった。
以上のように、本節では、死後出家の風習を起点に、「死後に戒名を付けられる」ということが、日本人にとってごく自然なことになったという流れを確認しました。
本節を終える前に、もう一点だけおさえておきたいことがあります。
それは、「死後出家」の場合は、本人というより、遺族などの残された人たちの望みによる出家だということです。
故人を出家させるということに遺族がこだわっているからこそ、本来の出家は生前に行うものなのに、死後であったとしても、言ってしまえば強引に、出家の儀式を行ったのですね。
ではなぜ遺族がここまで出家にこだわったかというと、出家には大きな功徳があるためです。
死後であっても、お坊さんに戒を授けてもらうことで、亡者を出家者として送り出すことができます。こう考えると、「死後出家」というのは、遺族が、「出家の功徳を具えれば、故人は良いところに生まれ、速やかに成仏できる」と信じて、「出家していない個人もなんとか出家させてやりたい」と願ったからこそ、生まれたのだといえます。
このように「死後に戒名を与える」という風習が広まっていった背景には、「亡者のために何かしてあげたい」という残された者たちの思いが要因としてあるといえますね。
ちなみに、第一弾の記事で考察したように、A「出家者を呼び、葬儀をしてもらう風習」が浸透した理由も、基本的にこれと同じです。
最後に
本記事では、B「在家者が出家者にお布施をして、死後に戒名を付けてもらうことは、いつから始まったのか?」について、詳しく解説してきました。
A「在家者が出家者にお布施をして、出家者に葬儀をしてもらうことは、いつから始まったのか?」、
C「在家者が出家者にお布施をして、追善供養をしてもらうことは、いつから始まったのか?」
についての解説記事(第一弾・第三弾)も用意しています。
まだご覧になっていない方は、ぜひ読んでいただければ嬉しいです!
冒頭にも貼りましたが、改めてリンクを載せておきます↓
全体の総括や、【参考文献】やおすすめ本については、第三弾の記事の最後にまとめて挙げていますので、本記事はこれくらいで終わりたいと思います。
ぜひ、第三弾の記事に進んでいただければ嬉しいです!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!
本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!
また、いいねの数が大変励みになります。
本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!
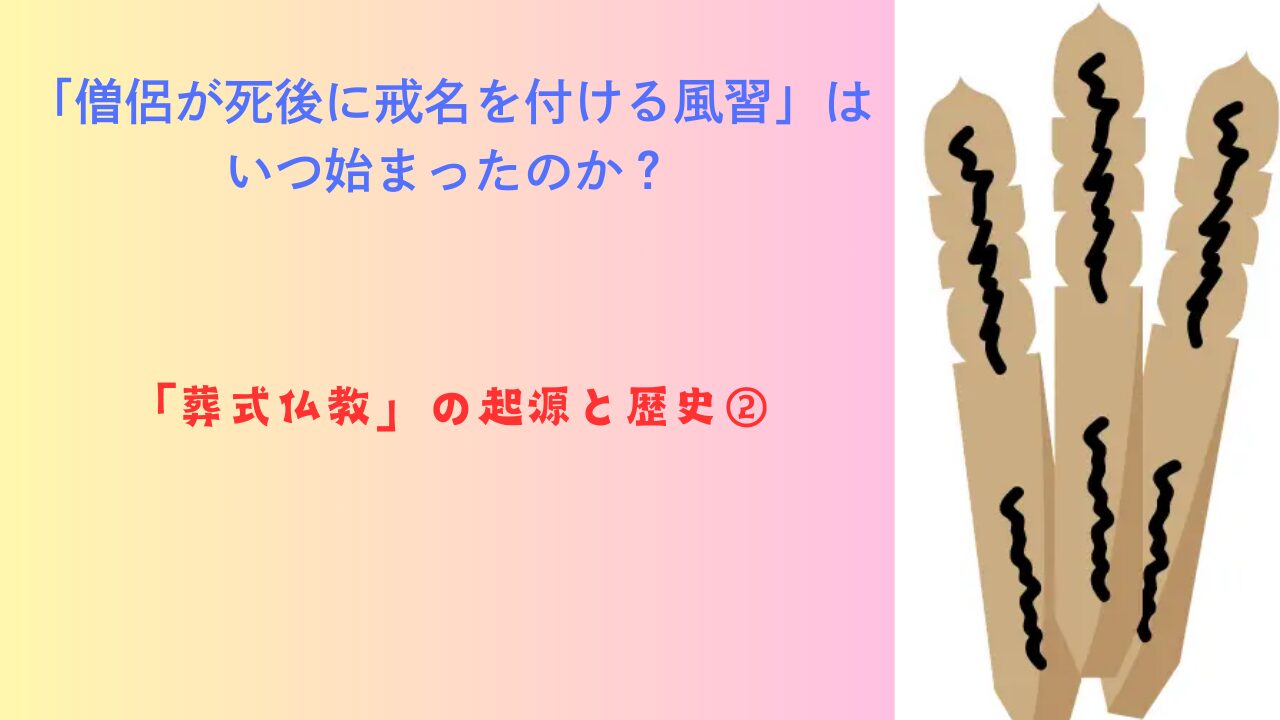





コメント