こんにちは、学問ボウズです!
本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!
「葬式仏教の起源と歴史」を学ぶ記事も、今回が第三弾となりました。
今回の「葬式仏教の起源と歴史」にフォーカスする試みは、具体的には、3つの記事に分けて、「葬式仏教はいつから、なぜ始まったのか?」を、学んでいこうというものです。
以下の3つの風習が、「いつから、なぜ始まったのか?」を考えていきます。
A「在家者が出家者にお布施をして、出家者に葬儀をしてもらうこと」は、いつから始まったのか。
B「在家者が出家者にお布施をして、死後に戒名を付けてもらうこと」は、いつから始まったのか。
C「在家者が出家者にお布施をして、追善供養をしてもらうこと」は、いつから始まったのか。
この3つのテーマです。
AとBについては、第一弾と第二弾で解説しましたので、本記事では、このうちのC「在家者が出家者(僧侶)に布施をして、故人の追善供養をしてもらうことは、いつから始まったのか?」を取り上げます。
A・Bについては、それぞれ以下の記事をご覧ください↓
では、早速、Cについての解説に入っていきましょう!
起源と歴史
前提知識
C「在家者が布施をして、出家者に追善供養をしてもらう風習」の起源や歴史を詳しく見ていく前に、前提知識の確認をしておきましょう。
そもそも「追善」とは、亡者のために、生きている者たちが善行を追加してあげることです。
仏教では、生き物は死ぬと、「七七日」の間(計49日間)はどこにも生まれ変わらずに漂っており、「七七日」を経過してはじめて生まれ変わるという考え方があります。
現在でも、人が亡くなった場合、基本的に七七日の法事(四十九日の法事・満中陰の法事ともいう)が行われますね。
それは、このような仏教的な「七七日」の考え方に基づくのです。
この49日間に遺族が善根を積み、それを亡者にふり向けて、良い処に生まれ変わらせようとするのが「追善」です。「追善供養」という言い方をされることもあります。

では、今確認した前提知識を踏まえ、Cの起源と歴史を、古代インドに遡って、見ていきましょう。
インド
Cの習慣・伝統がいつから始まったのかということですが、仏教発祥の地の古代インドではありません。
(第一弾と第二弾の記事で説明しているように、)A「在家者が出家者にお布施をして、出家者に葬儀をしてもらう風習」と、B「僧侶に布施をして、死後に戒名を付けてもらう習慣」は、いずれも中国か日本で初めて生まれたものでしたね。
Cの場合もこれと同じで、インドでは「僧侶が布施をもらい、追善供養をする風習」は生まれませんでした。
それどころか、「いまだどこへも転生していない亡者を、良い処へ生まれ変わらせるのは、悟ったブッダですら無理だ」とも考えられていたのです。
こうした古代インドの状況は、「在家者が布施をして、出家者に追善供養をしてもらう」という、今の日本で一般化している事態からは、ほど遠いと言えましょう。
中国
では、どこが起点になったのかというと、中国です。
中国の南北朝時代(439~589)において、在家者が布施をして、出家者に追善供養をしてもらうようになったのです。
しかし、さきほど見たように、古代インドでは、「いまだどこへも転生していない亡者を、良い処へ生まれ変わらせるのは、悟ったブッダですら無理だ」と見なされていたのです。
それなのに、いったいなぜ、中国で行われるようになったのでしょうか?
それは、ある経典に基づきます。
南北朝時代のうちの北朝の時代(386年~535年)には、ある経典が創作されました。
その名は『梵網経』です。
これは中国で新たに創作されたお経です。
このような新たに作られたお経を偽経といいます。
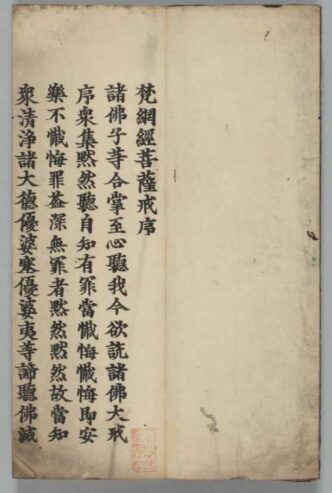
【『梵網経盧舎挪佛説菩薩心地法門品』(国文学研究資料館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200015318】
この『梵網経』には、追善供養の歴史において大変重要な、次のような記述があります。
「父母や経題、師が亡くなった際に、亡くなった日から三七日(計21日)、ないし七七日(計49日)の間、在家者が僧侶を招いて、『梵網経』の読誦や説法などをさせれば、その功徳によって、亡者を良い境遇に生まれ変わらせることができる」と。
さらにもう一つ、唐の時代(618年~907年)に成立した、『心地観経』という経典があります。
この『心地観経』にも、僧侶と追善を結び付ける重要な記述があります(『心地観経』も偽経です)。
「子が父母のために追善供養を行えば、大いなる金色の光明が地獄を照らし、光の中に妙なる仏法を説き、父母を悟らせ、苦しみから逃れさせることができる」と。
この他にも、追善の重要性を説く経典は多数ありますが、特にこの『梵網経』と『心地観経』が代表的だといえます。
今では「『梵網経』や『心地観経』は偽経だ」ということが明らかになっていますが、古代中国の人たちは分かっていませんでした。
そのため、当時の人々はみな、この『梵網経』『心地観経』を真実の経典、つまり釈尊(お釈迦様)直々の言葉として理解していたわけです。
このようにして、死後の追善の重要性を明示する、『梵網経』や『心地観経』などを読んだ古代中国の人たちは、「お釈迦様がこう言っているからそうすべき」ということで、出家者を招き、追善をするということを盛んに行うようになりました。
また、さらに時代が降り、南宋の時代(1127年~1279年)になると、浸透するだけではなく、さらに新しい風習も加わっていきます。
七七日の間に追善の仏事(法事)を行うだけではなく、百日・一年・三年の喪の終わりという節目でも、きちんと仏事を行うようになったのです。
今の日本でも、百箇日忌・一周忌・三回忌という年回忌を行う伝統がありますが、そのおおもとはこの南宋時代の風習にあるといえます(これについては、後にまた詳しく述べます)。
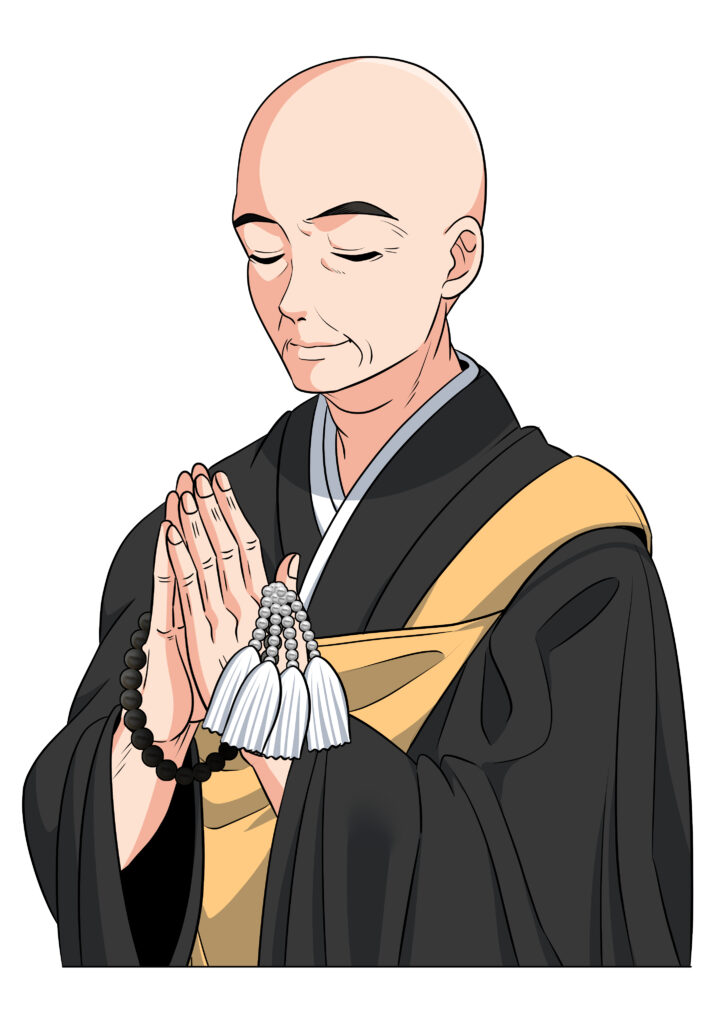
またここで、もう一点おさえておきたいことがあります。
『梵網経』の一節を振り返ってみると、その一節においては『梵網経』の功徳を説きつつ、出家者を呼ぶべきだということも明言していますね。
つまり、『梵網経』の功徳だけではなく、「聖者が追善を行う」ということも重視されているのです。
ということは、C「在家者が布施をして、出家者に追善供養をしてもらう風習」が浸透した背景には、「聖者崇拝」があったといえるでしょう。
これは、A「僧侶に葬儀をしてもらう風習」、B「僧侶に戒名を付けてもらう風習」と同じですね。
日本
日本でも、中国の影響を受けて、古くから追善供養が行われていました。
その歴史は古く、703年には持統天皇(645年~703年)の七七日の供養のために、法要が営まれたといいます。
その後も、聖武天皇(701年~756年)の没後、初七日から七七日の間に、七日ごとに仏事が行われ、一周忌も行われるなどの記録が見えます。
この他にも、古代の記録には、
「故人を埋葬し、墓標を立てた」、
「四十九日の追善と墓参りをした」
「一周忌を行った」
などの記録が散見します。
このように日本では古代から、中国同様に追善仏事を行っていたのです。
また、僧侶側も、積極的に追善を勧めていました。
例えば、平安後期に東大寺で活躍した、珍海(1091年~1152年)という僧侶がいます。
珍海は、人々に和語で分かりやすく教えを説いた『菩提心集』(1128年)という書で、次のように述べています。
「亡くなった人が、次の生まれがまだ定まらず、さまよっている間に、生きている者が死者のために、幡をかけ、火をともし、経典を読んでやると良い。
そうすれば、その功徳により、死者は諸々の苦しみを逃れて、仏のまします浄土に生まれることができるのだ。
また宝篋印陀羅尼という陀羅尼(仏教で唱える呪文)を七遍、亡き父母のために読んでやりなさい。
そうすれば、その陀羅尼の功徳によって、もし父母が地獄に堕ちていたならば、その苦しみから救われるのだ」と。
このように珍海は、追善について詳述し、どのような内容の追善をすべきを具体的に示しているのです。
また、平安末~鎌倉初期にかけて、説法の名手として活躍した澄憲(1126年~1203年)は、さきほど見た『心地観経』を踏まえ、追善が重要であることを強調しています。
また、追善の意義を説く際に『心地観経』を用いるのは、浄土宗の人物などでも同様です。
例えば、江戸期の浄土宗の大家である義山(1648年~1717年)の『円光大師行状画図翼賛』(1703年)では、さきほどの『心地観経』の文をもとに、「念仏を称えて追善を行えば、阿弥陀仏の光が苦しみの世界を照らして、亡者を救ってくださる」ことを説明しています。
つまり義山は、「念仏によって追善を行う」という、浄土宗における追善を意義づける際に、『心地観経』を根拠にしているのです。
これらの例から、日本で追善が盛んになった背景には、『梵網経』『心地観経』などの、中国で撰述された経典における「追善は重要だ」とする説からの大きな影響があったことが窺えますね。
このように、中国を起源として、日本においても「人々が追善の重要性を認識し、僧侶を招いて積極的に行い、僧侶のほうもそれを勧める」という風習が浸透しました。
ただし、中国に対する日本の特徴もあります。
それはすなわち、時代が降ると追善の回数が増えていくことです。
さきに少し触れたように、すでに南宋時代の中国で、追善の仏事が増えていました。
しかし、増えたといっても、百箇日・一周忌・三回忌までです。
これに対して日本の鎌倉時代には、一気に「十三仏事」にまで増加したのです。
「十三仏事」とは、以下の合計13回の追善のための仏事です。
初七日
二七日
三七日
四七日
五七日
六七日
七七日
百箇日
一周忌
三回忌
七回忌
十三回忌
三十三回忌
日本で仏事が13回にまで増えた理由については、よく分かっていません。
「寺院側の意図的な戦略だった」という学説もありますが、どのくらい信憑性があるかは不明です。
現に、「日本人には死や死者を恐れる感情が強かったためだ」という別の学説もあります。
また、私は「遺族の死者を大事にする気持ちが強かったため」という、遺族の気持ちという視点も大切だと思っています。
仏事が増えた背景には、こうした多様な理由があったと考えられます。
ちなみに、チベットも、中国の影響で追善供養を大事にする地域ですが、行うのは四十九日と一周忌の法事のみです。
こうしてみると、年回忌が急激に増えたことは、日本仏教の特徴だといえるでしょう。
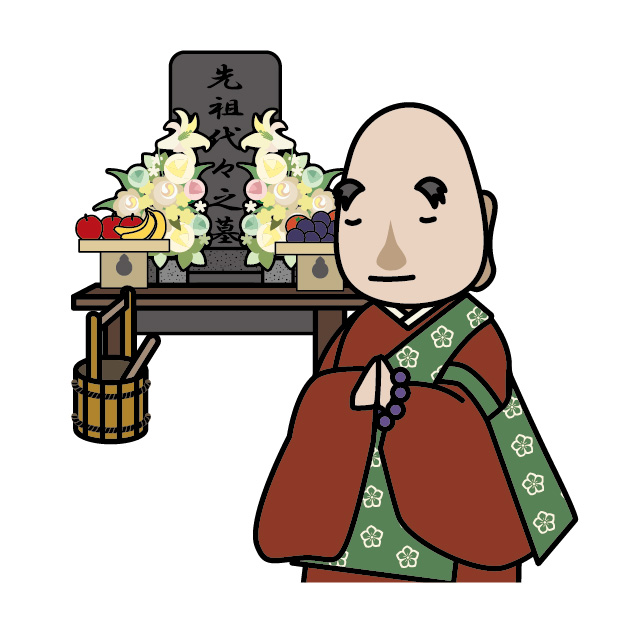
ここまでの内容をまとめておきましょう。
◎C「在家者が布施をして、出家者に追善供養をしてもらう風習」は、インドで生まれたものではない。
中国で、『梵網経』や『心地観経』などの偽撰経典を中心として、追善の重要性が説かれたため、人々は追善を積極的に行うようになり、Cの風習が浸透していった。
◎日本でも、こうした中国の追善の風習が受け継がれた。
また日本では、法事の数がいっそう増えるなど、より長く、より丁寧に追善を行うようになるという展開があった。
最後に ―「葬式仏教」の未来は?「葬式仏教」はおかしいのか?―
ここまで、3つの記事を通して、A・B・Cのルーツをそれぞれ考察してきました。
3記事全体を踏まえ、A・B・Cの内容をまとめると、次のようになります。
A「在家者が出家者にお布施をして、出家者に葬儀をしてもらうこと」はいつから始まったのか?
→明確にこの習慣が出来上がったのは中国からである(北宋時代の禅宗の影響による)。
これが日本にも伝わり、禅宗以外の各宗派にも広まり、今に至る。
B「在家者が出家者にお布施をして、戒名を付けてもらうこと」はいつから始まったのか?
→「生前に戒名を授与する」という習慣が出来上がったのは、中国においてである(土着の風習との融合による)。
これが日本にも伝わり、「臨終出家」との関わりの中で、「死後の戒名授与」という習慣が新たに出来上がる。そして、各地域、各階層に広まり、今に至る。
C「在家者が出家者にお布施をして、追善供養をしてもらうこと」はいつから始まったのか?
→明確にこの習慣が出来上がったのは中国から(偽経である『梵網経』の影響)。
これが日本にも伝わり、さらに仏事の数を増加させるという新たな展開がありつつ、今に至る。
このように、A~Cは総じて、中国に淵源があり、日本がそれを踏まえ、さらに定着させ、その内容も確固たるものにしたという構造であるといえます。
また、A「お葬式の習慣」とC「追善の習慣」は、明らかに、「僧侶が聖者であり、聖なる力を持っているから、葬儀や追善供養をお願いする」という、「聖者崇拝」がもとになっています。
B「戒名の習慣」も、これに当てはまると見ることができるでしょう。
では、以上の学びを踏まえて、「葬式仏教はおかしいのか?」「葬式に偏る日本の仏教に未来はあるのか?」ということを、最後に私なりに考えたいと思います。
今回見てきたように、A~C全て、本来のインド仏教からは逸れるといえますが、古代の中国に起源があり、かなりの伝統があるものだといえます。
単に「純粋な教理とは違うからダメだ」と一蹴できないような、歴史的重みがあると思います。
また、A~Cの行い(儀式)には、(各節で詳しく述べてきたように)それぞれ大事な意味があります。
例えば、戒名は仏教徒になった証ですし、葬儀は亡者を悟りへ浄土に導くための大切な儀式です。
A~Cのいずれも、決して、「何となく、特に意味もなくやられ出した」わけではありません。
さらに、故人を思う遺族がいてこそ、ここまで長く、かつ広く日本中で続けられてきたという面も重要でしょう。
根源にあるのは遺族の純粋な気持ちであるということも、重視すべきだと思います。
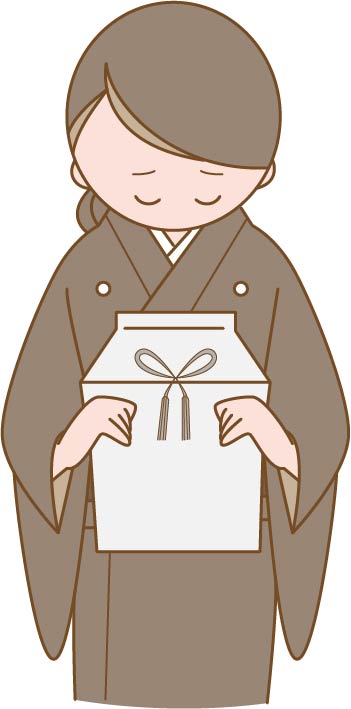
そのため私は、仏教が葬式を担うのは否定されるべきではなく、望む人がいる限り、仏教界は全力で行うべきものだと思います。
実際に、『葬式仏教』(大法輪閣、1963年)という本を刊行し、葬式仏教という語を定着させた圭室諦成(1902年~1966年)は、葬式仏教に肯定的でした。
圭室諦成氏は、当時の日本仏教のあり方を肯定的に捉え、そうした立場から、「葬式仏教」という語を用いていたのです。
ただし、「仏教が葬式を担うのは良い」とは言いましたが、単に今のままで良いかというと、そういうわけではありません。
私は、「伝統あることだから、そのまま続けるべき」などという古臭い意見を言うつもりは全くありませんし、今の時代にそれが通用するとも思えません。
現に、残念ながら、今では「葬式仏教はいらない」という声が大きくなっています。
なぜ葬式仏教が不要視されているのかについては、その理由は色々あると思いますが、一番は、信者さんが僧侶に対してがっかりしているためだと思われます。
ここまで度々お話してきたように、葬式や戒名の淵源にあったのは「聖者崇拝」でした。
崇拝とまではいかないにしても、聖者として僧侶に敬意を払っていたからこそ、僧侶を葬式に呼ぶ文化が生まれ、それが連綿と受け継がれてきたのです。
それが今、お坊さんへの不信感から、「こんなお坊さんにお葬式してもらってもな…」という声があがっています。
また、そもそも葬儀の意味自体も分からないため、「葬儀なんてしても、意味がない」と感じる方が一定数出てきているのです。
ではどうすれば良いのでしょうか?
私は、出家者が聖者としての性格やあり方、いわば「聖者性」を取り戻すことが必要だと思います。
信頼される聖者として葬式を行えば、お葬式も自然と行われるようになるでしょう。
とはいえ、浄土宗や浄土真宗などの、僧侶が特に聖者性を持たないような宗派もあります。
浄土宗や浄土真宗は、「みなが平等に凡夫(仏教的な能力に乏しい普通の人)」と考える宗派です。
そういった宗派は、葬儀や追善の意味をしっかりと伝えることが大事でしょう。
要は、遺族が「何かよく分からないままに、取られたくない人にお金を取られた」と思うのがまずいのだと思います。
「やってほしい人にお願いし、意味あることができた。故人のために何かできた、やって良かった」と遺族が思えるようになるのが一番大事なのではないかと思われます。
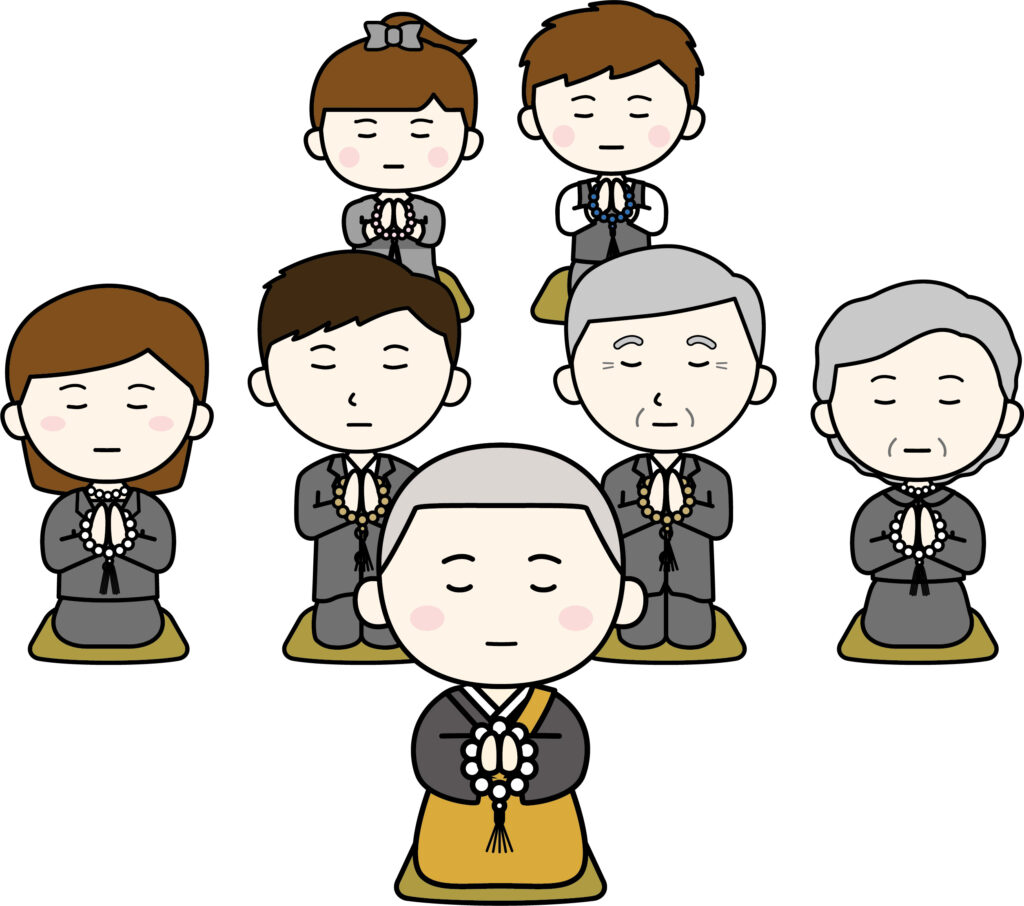
伝統を受け継ぐというのは、単に過去やられてきた風習をそのままやるということではありません。
葬式は相手があってこそなのですから、その時々の人々の声に応えて、その方たちが納得できる形を目指すというのが、最優先事項だと思います。
その試行錯誤の中で、伝統を受け継ぐということも可能となるのでしょう。
自戒を込めて、いつもとは違って少し厳しめに私の意見を書いておきました。
私も僧侶として頑張りたいと思います。
参考文献とお勧めの本
【参考文献一覧】(年代順)
本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。
いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。
学恩に心より感謝いたします。
◎圭室諦成『葬式仏教』(大法輪閣、1963年)。
◎山折哲雄『死の民俗学 日本人の死生観と葬送儀礼』(岩波書店、1990年)。
◎島田裕巳『戒名 なぜ死後に名前を変えるのか』(法藏館、1991年)。
◎島田裕巳『戒名無用 死に方を変えてみませんか』(メディアワークス、1999年)。
◎圭室文雄『葬式と檀家』(歴史文化ライブラリー70、吉川弘文館、1999年)。
◎保坂俊司『戒名と日本人 あの世の名前は必要か』(祥伝社新書49、2006年)。
◎藤井正雄『戒名のはなし』(歴史文化ライブラリー217、吉川弘文館、2006年)。
◎水藤真『中世の葬送・墓制 石塔を造立すること』(吉川弘文館、2009年)。
◎新谷尚紀『お葬式 死と慰霊の日本史』(吉川弘文館、2009年)。
◎藤井正雄『現代人の死生観と葬儀』(岩田書院、2010年)。
◎島田裕巳『戒名は、自分で決める』(幻冬舎新書162 [し-5-4]、幻冬舎、2010年)。
◎松尾剛次『葬式仏教の誕生 中世の仏教革命』(平凡社新書600、平凡社、2011年)。
◎菊地章太『葬儀と日本人 位牌の比較宗教史』(ちくま新書916、筑摩書房、2011年)。
◎島津毅『日本古代中世の葬送と社会』(吉川弘文館、2017年)。
◎松尾剛次『日本仏教史入門 釈迦の教えから新宗教まで』(平凡社新書997、平凡社、2022年)。
◎島田裕巳『葬式消滅 お墓も戒名もいらない』(G.B.、2022年)。
◎大竹晋『悟りと葬式 弔いはなぜ仏教になったか』(筑摩選書253、筑摩書房、2023年)。
【お勧めの書籍】
では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。
内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました!
まず、大竹晋『悟りと葬式 弔いはなぜ仏教になったか』(筑摩選書253、筑摩書房、2023年)です。
仏典翻訳家として有名な大竹晋先生が、仏教が葬儀を担うようになった過程を、詳細に考察しておられます。
本記事を書くうえで、この本には大いに学ばせていただきました。
大竹晋の御著書を読んでいて毎回感服するのは、その守備範囲の広さです。
インド仏教・中国仏教・日本仏教、ひいては仏教以外の諸思想や宗教など、何でも扱える、本当にすごい研究者だなと感じます。
本記事は「葬式仏教」の起源と歴史について、全体の見取り図を描いただけですので、もっと詳しく知りたい方は、ぜひこの御著書を手に取っていただければと思います。
これ一冊を読むだけで、仏教と葬式との関わりについて、かなり詳しくなれます。
次に、松尾剛次『葬式仏教の誕生 中世の仏教革命』(平凡社新書600、平凡社、2011年)です。
日本において、仏教が葬送の役割を担ってきた過程を、古代から詳細に解き明かしています。
松尾先生は、日本中世史がご専門ですので、特にその時代の仏教についての考察は大変詳細かつ独創的であり、とても興味深いです。
しかし、これは現在入手しにくくなっています…。
再版していただきたいところです…。
(ひとまず、図書館などでご覧ください💦)
次に、圭室文雄『葬式と檀家』(歴史文化ライブラリー70、吉川弘文館、1999年)です。
江戸時代の仏教界についての事例を研究した書です。
戒名の通史ではないのですが、江戸時代における葬送などについて、かなり詳しく書かれていますので、純粋に面白いです。
近世の事例に関心のある方、より具体的に学びたい方は、ぜひ手に取っていただければと思います。
A「在家者が出家者にお布施をして、出家者に葬儀をしてもらうことは、いつから始まったのか?」、
B「在家者が出家者にお布施をして、死後に戒名を付けてもらうことは、いつから始まったのか?」
についての解説記事(第一弾・第二弾)をまだご覧になっていない方は、ぜひそちらも読んでいただければ嬉しいです!
冒頭にも貼りましたが、改めてリンクを載せておきます↓
では、本記事はこれでおしまいです。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!
本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!
また、いいねの数が大変励みになります。
本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!
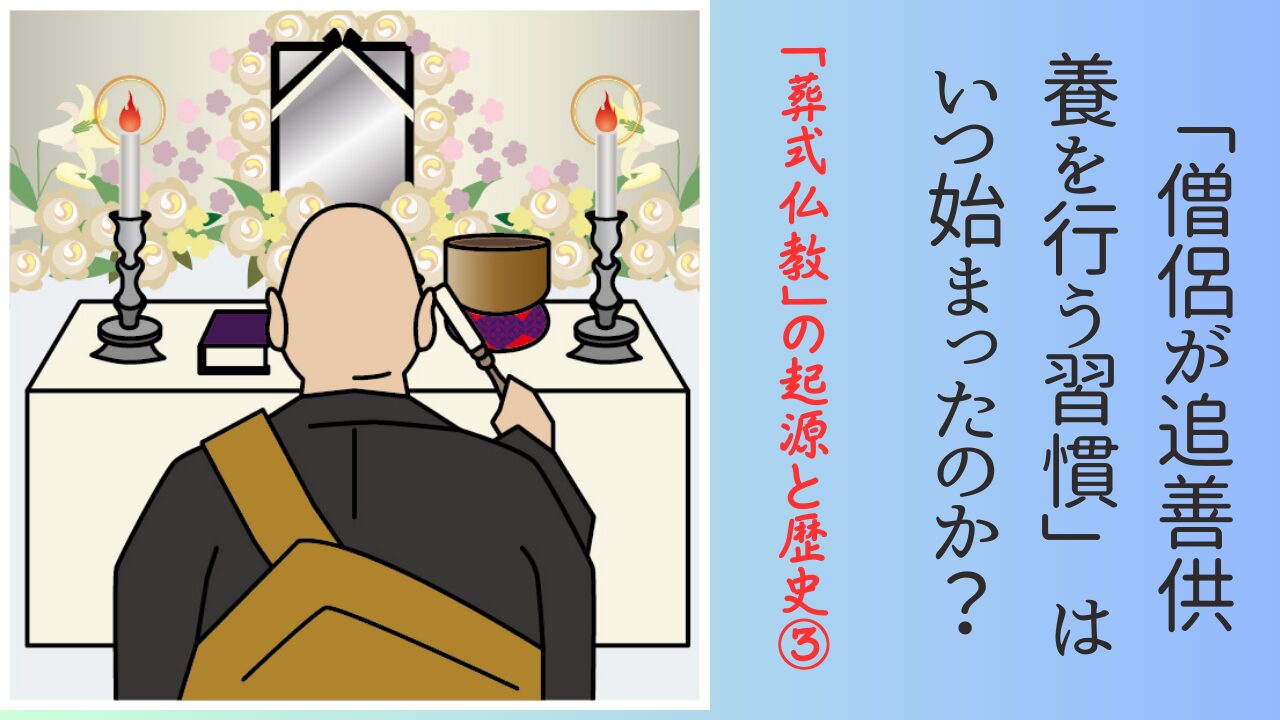

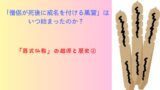




コメント