こんにちは、学問ボウズです!
本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!
「浄土教」では、この命が尽きた後、阿弥陀仏の浄土(極楽浄土・西方浄土)に往生する(生まれ変わる)ことを説きます。
その「浄土教」の主要な教えの一つに、「俱会一処」があります。
「俱会一処」とは、「浄土でともに出会うこと」です。
この教えは、『阿弥陀経』に、「浄土に往生すると、諸々の善人たちと、一つの処でに出会うことができる」とあるのに基づいています。
「諸々の善人たち」というのは、すでに浄土に往生し、そこで仏になるために修行をしている方々(聖なる存在である菩薩)を指します。
つまり「俱会一処」とは、「この私が往生すれば、すでに浄土にいる亡き方と、そこでまた会える」ということを意味するのです。
また、同じような意味で、「一蓮托生」という語もあります。
こちらのほうが、なじみ深いかもしれません。
「一蓮托生」とは、縁のあった人と、「浄土の一つの蓮の上にともに生まれる」ということです。
俱会一処と同じく、「亡き方との浄土での再会」を示す語ですね。

お寺で法務をしていると、「亡き方とまた会いたい」と願う方々に接する機会がよくあります。
かくいう私も、ここ数年、愛する家族を亡くしていますので、そのような願いを持つ者の一人です。
亡き方との再会を求める人は多いため、「俱会一処」は現代でも重要なテーマだといえます。
本ブログでは、別記事で、浄土に往生した方々と、生者との関係性を解説しています。
記事はこちらの二つです↓
この2つの記事では、浄土宗の開祖法然(1133年~1212年)の理解について解説することに重きを置き、話がややこしくなることを恐れて、浄土真宗の開祖親鸞(1173年~1262年)の「俱会一処」理解については、あまり詳しく述べませんでした。
しかし、浄土真宗の信者さんにとっては、「親鸞が俱会一処をどのように理解していたのか?浄土真宗では俱会一処をどのように考えるべきなのか?」は、大変重要な問題です。
今回は、それについて、近年の研究の新たな動きを紹介する形で、踏み込んで解説してみたいと思います。
近年、「親鸞の俱会一処理解」をめぐる研究に、新たな動きがありました。
今から詳しく説明していきますが、予め、近年の研究で何が新しく主張されているかを簡単に申し上げておきたいと思います。
近年、「親鸞には俱会一処の教えはなかった」という興味深い学説が出されています。
浄土真宗の信者の方々の多くは、「俱会一処」の教えを信じ、「また会いたい」と願っておられると思います。
しかし、「親鸞には俱会一処の教えはない」のであれば、浄土真宗では「俱会一処」を願っても意味がないこととになります。
もっと言えば、(宗祖親鸞の本意ではないのだから)願ってはいけないということにもなりかねません。
そのため、信者の方々はこの学説に触れると、大変びっくりされると思います。
「俱会一処」を願う浄土真宗の信者さんにとっては、この学説は衝撃的なものだと言えるでしょう。
こういう近年の研究動向が一般書に反映されるには、かなり長い時間がかかります。
研究者以外、なかなかタイムリーに知ることはできません。
私はこの学説は大変刺激的なものなので、浄土真宗の信者さんはもちろん、それ以外の方にもぜひ深く知っていただきたいと思っています。
そして、この学説の是非や、俱会一処をどのように理解すればよいかなど、自ら考えていただきたいです。
以下、「近年の研究では、親鸞の俱会一処理解について、どのような学説が出ているのか」について、徹底解説していきます。
この学説の影響で、「俱会一処」をめぐる議論は今現在行われていますし、今後いっそう盛んになると思われます。
ぜひ本記事によって、今後の議論に参加するための(参加はしないまでも議論についていくための)、前提となる知識を身につけていただければ嬉しいです!
ではやっていきましょう!
親鸞はどれくらい「俱会一処」を説いていたのか?
早速、「俱会一処」の話に入りましょう。
親鸞は『阿弥陀経』に説く「俱会一処」について、どのように理解していたのでしょうか?
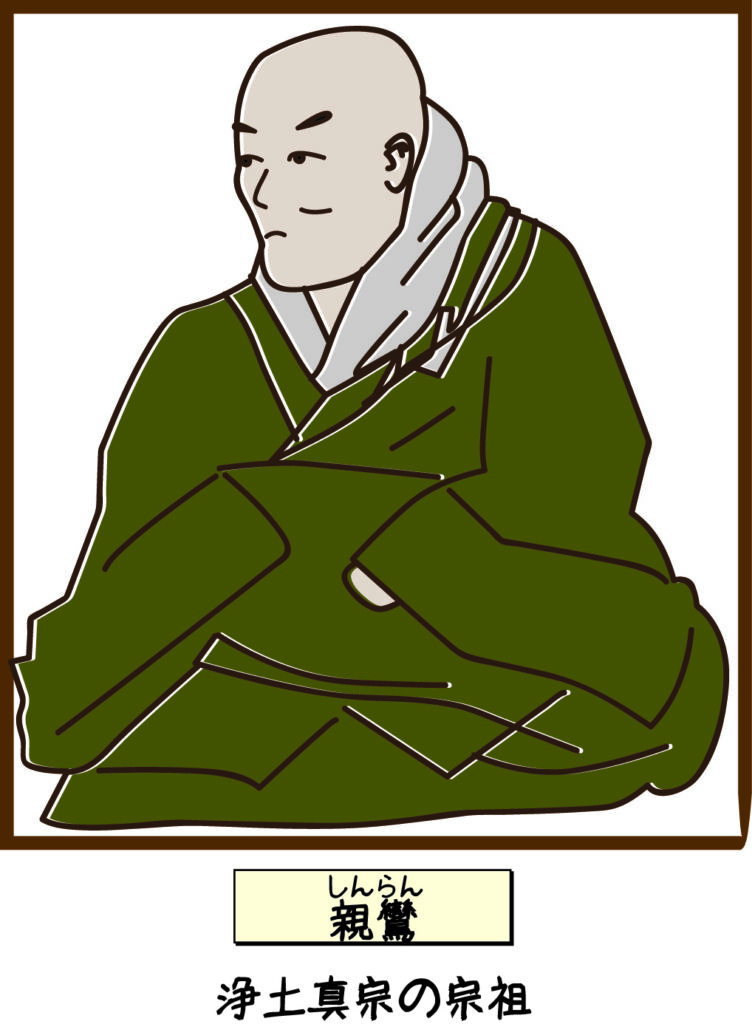
親鸞の著述の中、「倶会一処」の文言は、その引用文においてさえも見いだすことはできません。
このことは、第一におさえておくべきです。
しかし、親鸞の著述には、「俱会一処」に関連する記述はいくつかあります。
その代表例が、弟子に当てた手紙に見える記述です。
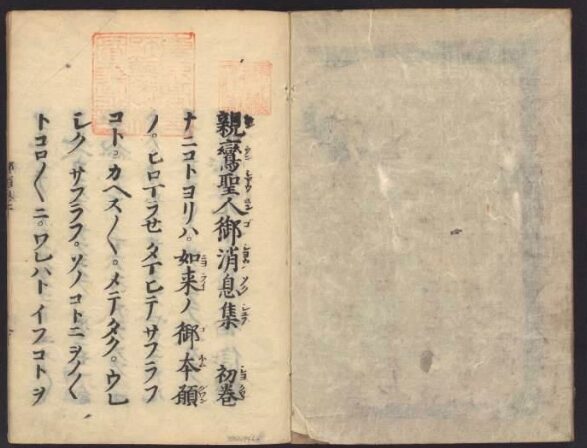
親鸞の消息を集めた『親鸞聖人御消息集』の冒頭部分(近世の版本)。
【『親鸞聖人御消息集』(筑波大学附属図書館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100309385】
その内容は以下の通りです。
「かくしんばう、ふるとしごろは、かならずかならずさきだちてまたせ給候覧、かならずかならずまいりあふべく候へば、申におよばす候」。
ここでは、「かくしんばう」(覚信房)という、すでに往生されたお弟子さんを思い出し、
「覚信房は先立って、浄土で待ってくださっている(かならずかならずさきだちてまたせ給候覧)。
それゆえ、私と覚信房は必ず浄土で再会できるのだ(まいりあふ)」
と述べています。
つまり、親鸞はここで、「浄土で弟子たちと再会できる」と、「俱会一処」を念頭に置いた発言をしているのです。
これまで、浄土真宗の学者の先生方は、そこに注目して、「親鸞も俱会一処を大切な教えとして説いていた」と理解してきました。
だからこそ浄土真宗の僧侶の方々も、
「死後、お浄土の蓮の上で亡き方と再会できます。
親鸞聖人も、そういう一蓮托生、俱会一処の教えを大事になさっていたのですよ」
と、法話の場などで積極的に説いてきたのです。

驚くべきことに、近年の研究では、こうした一般的な理解を覆しているのです。
では、いったいなぜなのでしょうか?
一番の理由は、資料の性格(資料性)です。
さきに見たように、たしかに親鸞は「俱会一処」に言及してはいます。
しかし、それはあくまで一個人への書簡で述べているにすぎません。
親鸞が、主著『教行信証』などの、自分の思想を確立するための教理書(教理を詳しく示した文献)で述べているなら、「確かに親鸞の重視する教えだ」とも言えるでしょう。
しかし、これはあくまで手紙です。
そのため近年の研究では、「親鸞が重視していたと結論付けるには、この一つの書簡がそれほど重要な根拠になり得るかどうか、疑問が残る」と主張しているのです。
また、先ほど申したように、親鸞の著述の中、「倶会一処」の文言は、その引用文においてさえも見いだすことができません。
以上を踏まえると、「俱会一処は親鸞の根幹となる教えだ」とまで、論証なしに言い切るのは難しいのです。
しかし、こういう反論もあるでしょう。
「確かに、親鸞は「俱会一処」について、あまり多く説いてはいなかったといえよう。
でも「俱会一処」の教えは『阿弥陀経』にちゃんと書いてある。
つまり「俱会一処」は神聖なお経に説かれていること(経説)なのだから、親鸞も当然、浄土に往けば「倶会一処」が実現されると考えていたはずだ。
となれば、親鸞も「俱会一処」の実現ということを念頭に置き、重視していたと見るべきだ」
と。
確かに「俱会一処」というのは、『阿弥陀経』に書かれている経説です。
親鸞が積極的に言及していなかったとしても、経説なのだから当然重視していてとも考えられます。
もっと言えば、親鸞は「俱会一処」をもう当然のものとしていたからこそ、わざわざ言及しなかっただけだという見方もできますよね。
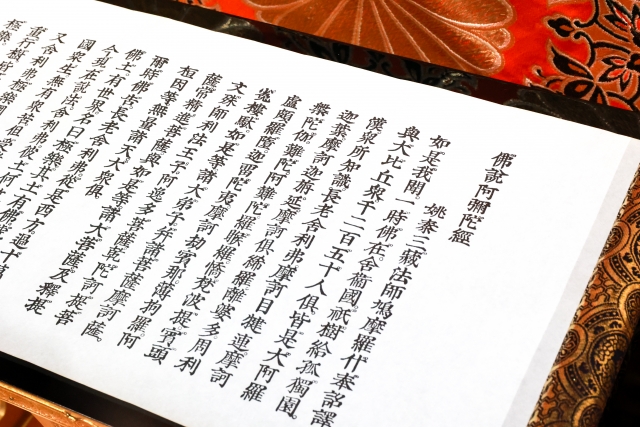
現に、昔の学者さんの中には、こういう理解をする方も多くいらっしゃいました。
しかし、最近の研究では、この考え方も否定しているのです。
すなわち、「親鸞は経説であっても、俱会一処を重視していなかった」と主張しているのです。
では、それはなぜなのでしょうか?
次節に詳しく見ていきましょう。
次節に移る前に、ここまでの内容を簡単にまとめておくと、以下のようになります。
◎親鸞は、「倶会一処」という文言を用いることはない。
◎しかし、「浄土で弟子たちと再会できる」と、「俱会一処」を念頭に置いた発言をしている。
◎これまで、こうした親鸞の発言をもとに、「親鸞は俱会一処を重視し、人々に説いていた」と理解されてきた。
◎近年の研究では、こうした通説に疑問を呈し、「親鸞は俱会一処を重視していなかったと見るべきだ」と主張している。
では、近年の研究で、「親鸞は経説であっても、俱会一処を重視していなかった」と主張し得るのはなぜか、詳しく見ていきましょう。
親鸞は「俱会一処」をどのように理解していたのか?
親鸞の浄土理解
近年の研究で、「親鸞は経説であっても、俱会一処を重視していなかった」と見なしている根拠は、は親鸞の浄土理解(西方浄土をどのように理解していたか)にあります。
そのため、「俱会一処」について見ていく前に、まず親鸞の浄土理解を確認しておきましょう。
ちなみに、本ブログでは、別の記事で、親鸞と師の法然における、極楽浄土についての理解の違いを解説しています。
記事はこちらです↓
この記事では、法然と親鸞の浄土理解には、「思いえがける具体的な色や形あるもの」として理解するか、「形なき光明の世界」と捉えるかという違いがあることを解説しています。
言うまでもなく、前者が法然、後者が親鸞の理解です。
今回のお話は、こうした浄土理解というテーマと密接に関わります。
ある昔の有名な学者の先生は「一つのことが分かれば芋づる式に分かる。これが面白いから研究はやめられない」と語ったといいます。
これは本当にその通りで、浄土教の各テーマはそれぞれ密接に繋がっています。
「浄土のことが分かれば、阿弥陀仏のことが理解でき、念仏について理解でき~」というように、「芋づる式に分かる」のです。
前掲の記事で、浄土宗と浄土真宗の浄土理解の違いを学んでいただいた方は、今からの内容を読んでいく中で、この芋づる式の経験をしていただけると思います。
とはいえ本記事でも、以下、確認も含めて再度説明していきますので、まだ読んでいない方もご安心くださいね。
では、親鸞の浄土理解について、踏み込んで見ていきましょう。
親鸞は『教行信証』において、「真(真仏土)と化(方便化身土)の2つの段階がある」という観点から、阿弥陀仏の身体とその浄土についての議論を展開しています。
ちなみに、「阿弥陀仏の身体と浄土についての議論」を、略して「弥陀身土論」といいます。
まず「真仏土」について、詳しく見ていきましょう。
親鸞は、「真仏士」の仏は「不可思議光如来」、土は「無量光明土」であると語ります。
つまり、「真仏土」を、はてない動的な「光明」(「ひかりの御かたち」)として理解していくのです。
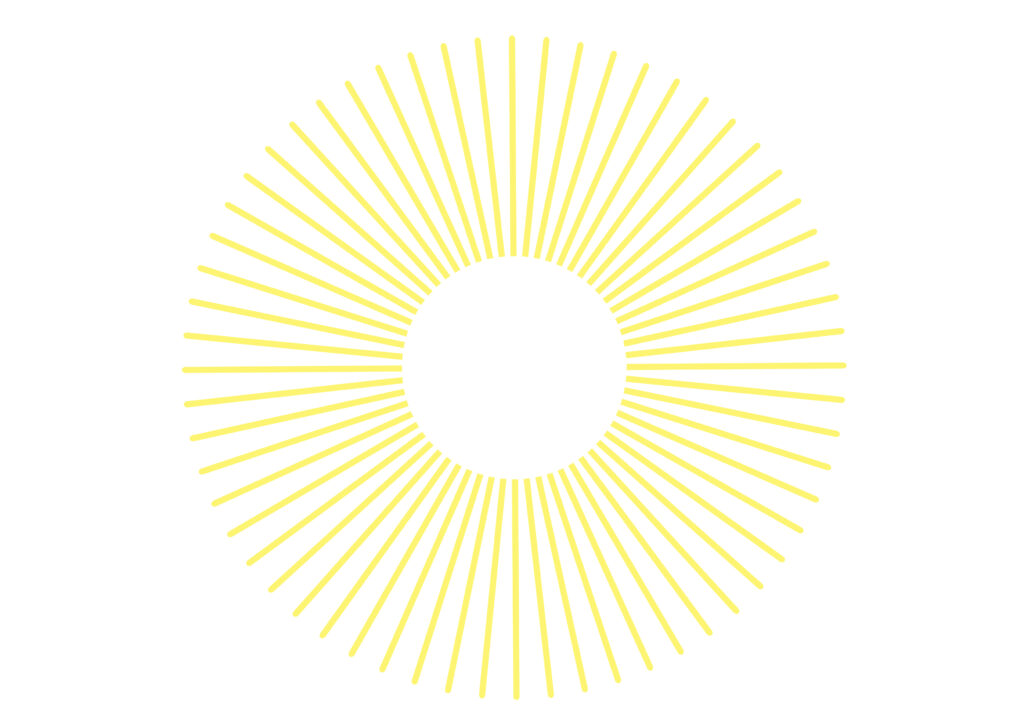
そのため「真仏土」には「いろもましまさず、かたちもましまさず」、すなわち具体的な色も形もありません。
一方、「方便化身土」はいかなるものなのでしょうか。
親鸞は「方便化身土」を、思いえがける具体的な色や形を持った、『観無量寿経』や『阿弥陀経』などに説く阿弥陀仏や西方浄土と見なしています。

色や形があり、私たちが具体的にイメージできる「方便化身土」とは、あくまで最終的に「真仏土」に引き入れるための「仮」の浄土にすぎません。
いわば、低い位置づけが与えられる浄土なのです。
このように親鸞は、「方便化身土は、衆生を導く仮の手立て、すなわち方便としては意義があるが、真実かつ最高の浄土としては真仏土のみ」という理解をしているのです。
「俱会一処」と「真仏土」「化身土」との関係
以上の内容から、なぜ親鸞は「経説であっても、俱会一処を重視していなかった」といえるのか、うっすら分かって来た方もいらっしゃると思います。
ポイントは、親鸞の浄土理解において、『阿弥陀経』に説くような形ある浄土、つまり「往生した方がそこで修行しながら、次に往生してくる者を待っていて、ともに対面し、再会を喜ぶ」というような浄土は、明らかに「方便化身土」に当たるということです。
つまり、「俱会一処」が実現されるような形ある浄土は、親鸞の示す教理体系においては、真ではなく「仮」にすぎないのです。
今申したことをもう少し具体的にイメージするために、さきの書簡に立ち返ってみましょう。
確かに、「高田の入道殿」への手紙における内容表現には、「形ある浄土で再会する」という理解を見ることができます。
したがって、この書簡の内容を「倶会一処」によって解釈することも可能でしょう。
けれども、やはりその場合にも、親鸞が根幹にする「真と仮を分別し、真を最上に置き、それを目指す」という立場からは、この書簡の内容はあくまで「方便化身士」における教えと見なすべきでしょう。
安易に、「書簡にこう書いてあるから、親鸞も俱会一処を重視していた!」と見なすことはできません。
親鸞は「仮に示して、人々を真に誘引させるための方便」として、「俱会一処」的な記述をしていると理解するべきなのです。
以上のような考察を根拠として、近年の研究では、
「親鸞が俱会一処を重視していたとはいえない。
浄土真宗における俱会一処の教えは、『教行信証』などの教理書に明確にかつ詳細に示している、「真と化を分別する」という親鸞の根幹的な立場をもとに、考えていくべきだ。
親鸞の思想体系においては、俱会一処はあくまで仮の教えということになる。
これを踏まえると、浄土真宗において俱会一処を(安易に)大変重視し、説法の場で積極的に説くのはいかがなものか」
と、これまでの通説に真っ向から反対しているのです。
本節の内容をまとめておきましょう。
◎親鸞は、色や形があり、具体的にイメージできる「方便化身土」を、あくまで最終的に「真仏土」に引き入れるための「仮」の浄土と理解する(低い位置づけ)。
◎つまり、「俱会一処」が実現されるような形ある浄土は、親鸞の示す教理体系においては、真ではなく「仮」にすぎない。
◎最近の研究では、この点に注目して、「親鸞の思想構造を踏まえると、俱会一処は仮の教えである。親鸞が俱会一処を重視していたと、安易に理解するのは良くない」と主張している。
法然の説との比較
ここまで見てきたように、親鸞の思想構造においては、「俱会一処がかなうような浄土は、あくまで方便」ということになります。
このような親鸞の立場との違いが際立つのは、法然です。
ここは法然と親鸞の相違点として興味深いところなので、法然の説にも触れておきましょう。

法然は「俱会一処」に関する発言を度々行い、「極楽において先だった人々と、同じ蓮に生まれて再会できる」と強調しています。
例えば法然は、正如房という、法然に深く帰依した方に送った手紙で、
「私たちはいつか極楽浄土という同一の浄土に往生するのです。
ですから、そこで再会できることには全く疑いの余地がありません」と述べています(「正如房へつかわす御文」)。
また法然は、
「同一の浄土の仲間となって再会しましょう」、
「同じ一つの浄土にともに生まれましょう」
など、弟子や信者たちに対して、「正如房へつかわす御文」と同様の発言を、繰り返し行っています。
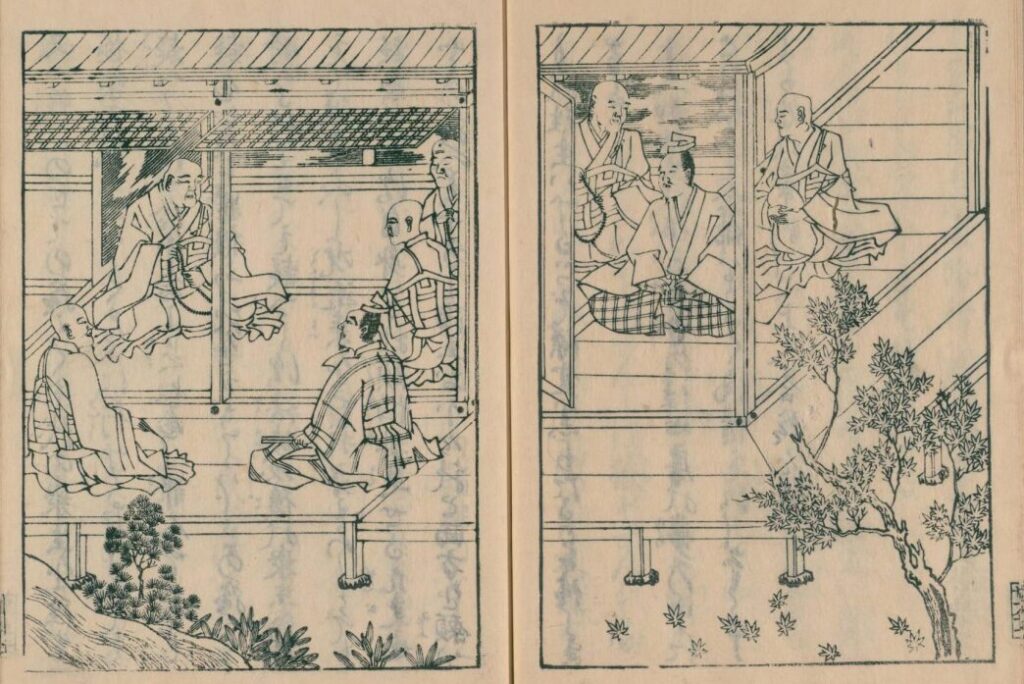
これは、法然が、「『観無量寿経』『阿弥陀経』は最高の教えを説く経典だ」と見なし、「極楽浄土とは『観無量寿経』や『阿弥陀経』に説く形を具えた浄土なのだ」と理解したためです。
(これについては、さきほど触れた法然・親鸞の浄土理解をまとめた記事で詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください↓)
つまり、「西方浄土とは、俱会一処のかなうような形ある浄土であり、それ以外に西方浄土というものはない」というのが、法然の根幹の教えなのです。
このような法然の理解を踏まえ、法然と親鸞の立場の相違について、要点をまとめておきましょう。
法然…「妙なる荘厳にみたされた、形ある極楽浄土に私が往生し、先に往生した人々と再会する」と理解する。
そのため、「俱会一処」を大変重視し、深く願っている。
親鸞…法然の考え方とは異なっており、「真仏や真仏土という、具体的な形なき世界が真実であり、形なき極楽浄土への往生が真の往生だ」と考えている。
そのため、法然ほどに「俱会一処」について積極的に説いてはいない。
このように法然と親鸞の説を比較すると、やはりこういう疑問が湧いてきます。
すなわち、「親鸞の説く形なき世界では、〈私とあなた〉というような関係性はどうやって成立するのか?」と。
法然の著述を読んでいると、法然が「同じ蓮の上に生まれて、一つの浄土で対面する」ことを大変重視し、それが必ず起こり得ると深く信じていたことが読み取れます。
卑近な言い方をすれば、ひしひしと伝わります。
こうした法然の「俱会一処」理解と比べると、やはり親鸞の思想構造においては、厳密に考えると、死後の再会は不可能なもの、言い換えればあくまで仮のものなのではないかという印象を持ちます。
これは言い過ぎにしても、少なくとも、親鸞が法然ほど、「俱会一処」を重視し、積極的に論じてはいないことは確かです。
このことは、法然と親鸞の著述を比較すると、大変よく分かります。
私はまだ親鸞の「俱会一処」をめぐる近年の主張が正しいのかを、はっきりと判断できる段階にはいません。
それをするためには、もう少し研究を重ねていかねばならないという状況です。
しかし現段階の印象としては、法然の「俱会一処」についての熱量と親鸞の説を比較すると、近年の研究で「親鸞の思想において、俱会一処は重要な要素ではない。それゆえ浄土真宗でも、俱会一処を安易に説くべきではない」と主張しているのも一理あるような気がします。
(これについては、今後いっそう研究を深め、私なりの答えを出せるようになりたいと思っています。)
最後に
本記事では親鸞の「俱会一処」理解についての最新の研究動向を紹介してきました。
最後まで読んでいただいた皆さまには、「親鸞は俱会一処をあまり重視してはいなかった。浄土真宗で俱会一処を積極的に説くのはどうなのか?」という、従来の真宗教学に一石を投ずる革新的な学説が近年において出てきたことや、その学説の論拠などについて、深く理解していただけたと思います。
実は最近、学会の中だけではなく、真宗のお坊さん達の間でも、この学説の是非が議論になり始めているようです。
学会・僧侶の世界では、大変ホットな話題になっているのですね。
私は「浄土真宗では俱会一処を説いて良いのか」という問題は、大変重要なテーマだと思います。
また、浄土真宗の信者さんたちの信仰に関わる問題でもあります。
このような重要な問題を、研究者や一部のお坊さまだけのものにしているのは良くないでしょう。
僧侶全体、ひいては門徒の方々までふくめて、色んな議論をしていくのが良いと思います。
(かくいう私も、今後いっそう勉強して、議論に参加したいと思っています。)
何が正しいかは別として、そうやって多くの方々が仏教に興味を持ち、仏教や信仰について自分なりに考えるというのが、日本仏教の未来にとって一番良いと思います。
本記事で、皆さまには、「今、俱会一処をめぐって何が問題になっているのか」を学んでいただきました。
ぜひ皆さまには、この学びを踏まえ、ご自身で考えていただきたいと思います。
それが、浄土真宗の、ひいては日本仏教の、より良い未来に繋がるはずです!
参考文献とお勧めの書籍
【参考文献一覧】(年代順)
本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。
いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。
学恩に心より感謝いたします。
◎渡邊了生「親鸞の思想にみる「倶会一処」の理解」(『印度學佛教學研究』47-2号、1999年)。
◎渡邊了生「「倶会一処」の浄土観と親鸞の弥陀身土思想」(『眞宗學』99・100号、1999年)。
◎林田康順「法然上人における俱会一処への視座—親鸞聖人との対比を通じて—」(石上善應教授古稀記念論文集『仏教文化の基調と展開』2、山喜房仏書林、2001年)。
◎細田季男「「おなじ蓮に」考」(『比較文化論叢 札幌大学文化学部紀要』11号、2003年)。
◎渡邊了生講述『親鸞の弥陀身土論 阿弥陀如来・浄土とは』(安居講義録シリーズ、安居「課外」講義録、真宗興正派宗務所教務部、2013年)。
◎渡邊了生「曇鸞が説示する「願生往生」の構造とその思想基軸 親鸞が語る「無生の生」義の意趣とは(その1)」(『岐阜聖徳学園大学仏教文化研究所紀要』14号、2014年)。
◎浄土宗総合研究所編『浄土宗の「浄土三部経」理解 法然上人と親鸞聖人の相違をめぐって』(浄土宗、2014年)。
◎平間尚子「法然上人絵伝研究 『国華本』「此界一人念仏名」考」(『国文学試論』24号、2015年)。
◎渡邊了生「曇鸞が説示する「願生往生」の構造とその思想基軸 : 親鸞が語る「無生の生」義の意趣とは(その2)」(『岐阜聖徳学園大学仏教文化研究所紀要』15号、2015年)。
◎梯信暁『お迎えの信仰 往生伝を読む』(法藏館、2020年)。
◎小谷信千代『法然・親鸞にいたる浄土教思想 利他行としての往生』(法藏館、2022年)。
◎赤松徹眞監修『親鸞と浄土真宗のこころ 親鸞聖人御誕生八五〇年 立教開宗八〇〇年記念』(別冊太陽、ムック、2023年)。
◎林田康順監修『図説 ここが知りたかった!法然と極楽浄土』(青春出版社、2024年)。
◎紅楳英顕『親鸞聖人はどんな教えを説いたのか? 浄土真宗の開祖・親鸞入門』(22世紀アート、2024年)。
【お勧めの書籍】
では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。
内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。
①法然と親鸞の思想を比較した書
お勧めは、浄土宗総合研究所編『浄土宗の「浄土三部経」理解 法然上人と親鸞聖人の相違をめぐって』(浄土宗、2014年)です。
法然と親鸞の教えの相違について、浄土宗の先生方が詳細にまとめておられます。
今回扱った、俱会一処の内容も詳細に書かれています。
執筆者は、今の「浄土宗の顔」というべき、浄土宗の第一級の先生方です。
初見では少し記述が難しいところもあるかと思いますが、本記事で学んでいただいた後で読めば、難なく理解できると思います。
もう少し詳しく知りたいという方は、ぜひ手に取っていただければと思いますが、これは今、大変入手しにくくなっています…。
再版に期待ですね。
再版までは、図書館などでご覧ください…。
また、そもそも「法然や親鸞の浄土理解などから、きちんと学びたい!」という方のために、以下の書もお勧めしておきます。
②法然の解説書
法然については、林田康順監修『図説 ここが知りたかった!法然と極楽浄土』(青春出版社、2024年)が有用です。
法然研究の第一人者の林田康順先生が監修しておられて、とにかく初学者向けに、分かりやすさにこだわって書かれています。
入門書として、もってこいです。
③親鸞の入門書
親鸞については、紅楳英顕『親鸞聖人はどんな教えを説いたのか? 浄土真宗の開祖・親鸞入門』(22世紀アート、2024年)が良書です。
長年、親鸞研究を行ってこられた、有名な紅楳先生による本です。
親鸞の教えの要点がまとまっていて、入門に最適です。
次に、赤松徹眞監修『親鸞と浄土真宗のこころ 親鸞聖人御誕生八五〇年 立教開宗八〇〇年記念』(別冊太陽、ムック、2023年)もお勧めです。
親鸞の生涯や教えを、ビジュアル資料をふんだんに使って、説明してくださっています。
文庫本に比べると少し高価ですが、個人的には載っている資料の豊富さ、有用さからいえば、お金を払う価値は十分あります。
入門書の紹介は以上になります。
法然や親鸞をきちんと学びたいという方は、ぜひ読んでみてくださいね。
また、法然や親鸞の著作などの、有名な浄土教文献の原文(書き下しや現代語訳など含む)に挑戦されたい方は、お勧めの書を別記事で詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください!
記事はこちらです↓
本記事はここまでです。
ではまたほかの記事でお会いしましょう!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!
本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!
また、いいねの数が大変励みになります。
本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押して応援していただけると、とても嬉しいです!
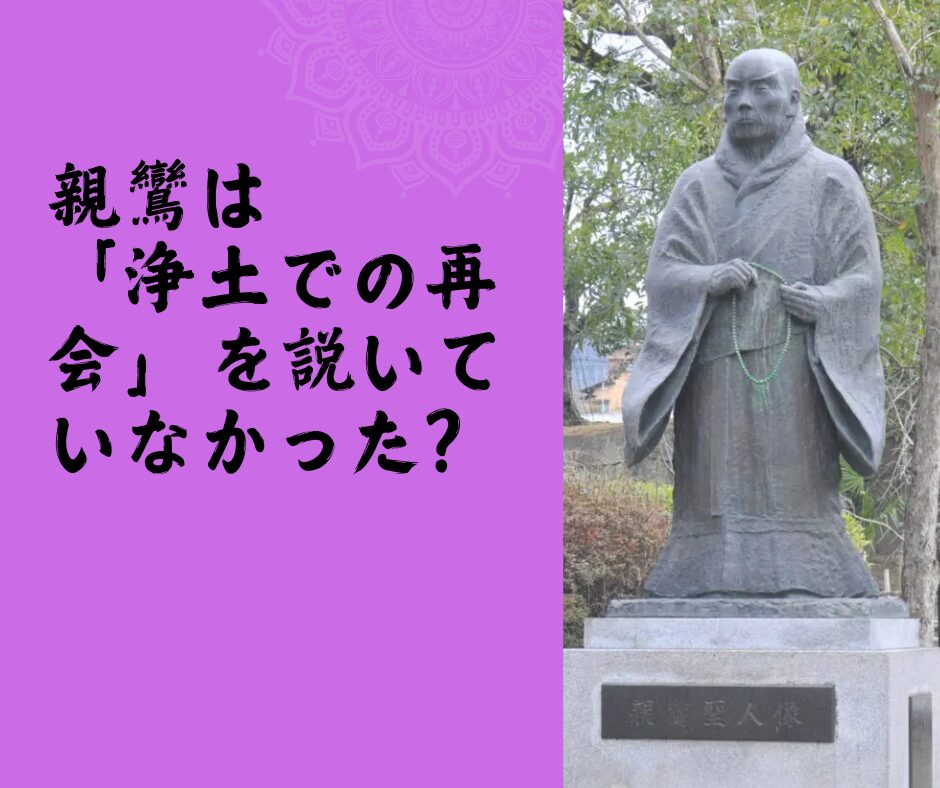







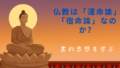

コメント